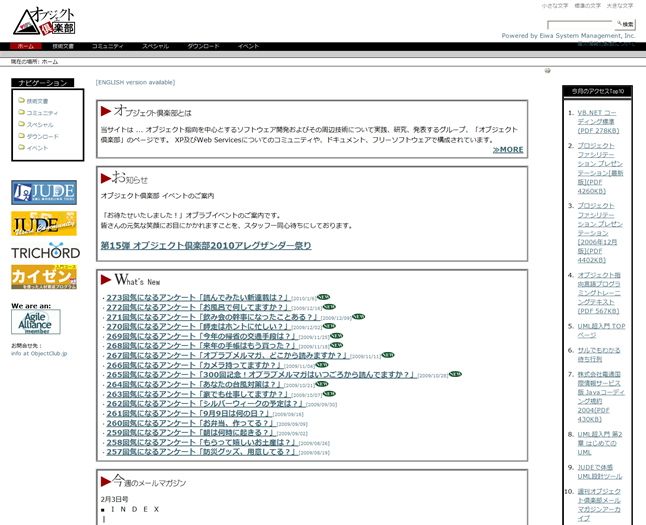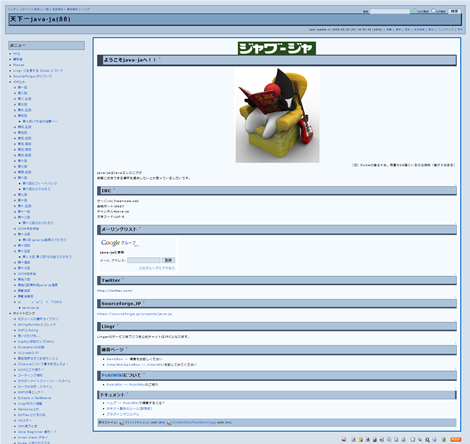本連載では、現在執筆中の技評SE選書には掲載していない、オリジナルのコンテンツをお届けしています。IT技術者が勉強をする場合のゴールとして、技術を身につけて自由自在にその技術を使えるようにする、というものがあると思います。今回はそれとは別の到達点として「転職」を取り上げたいと思います。勉強会を通じて適職を見つけ、転職をした人が周りに何人もいます。彼らを見てみると、転職が成立した条件として、次の3項目の共通項がありました。
- 実力、もしくは将来のための勉強の習慣を身につけた
- 自分の実力や将来性をきちんとアピールできた
- 受け入れ側のニーズとマッチした
今回は、勉強会に参加し転職のチャンスを掴んだお二人と、その転職先の社長さんを加えた三人の方々に、勉強や勉強会について語っていただきました。話に夢中で写真を撮り忘れました。文字ばかりですみません。
佐藤治夫さん(twitter:@haru860)
株式会社ビープラウド代表取締役。日頃は経営者とエンジニアの二足の草鞋を履く。2007年9月からWeb系技術勉強会であるBPStudyを開催し、毎月1回開催を続けている。
URL:恵比寿で働く社長のアメブロ
本記事を書いた筆者(渋川)と、今回のインタビューをお願いした岡野さんとはPython Developer Campというイベントで、文殊堂さんとはPython温泉という勉強会で知り合いました。それぞれ、フリースタイル形式で2泊3日という、本当にプログラミングが好きな人しか来ないだろうな、という勉強会でした。また、転職の受け入れ側として、ご自身もBPStudyという勉強会を立ち上げられている、佐藤治夫さんにも来ていただきました。
勉強会に行ったきっかけ
渋川:今日は勉強本の取材の一環として、勉強会などを通じて転職をした人に、動機やきっかけを聞きたいと思います。後は採用した側の方にも勉強会で会う人はどこが違うのか、という点についておたずねしたいと思います。勉強会で目立っているPythonの人は「さあ勉強しよう」という人がいないですよね?いつでも勉強しているイメージです。今まではどんな勉強をされてきましたか?
岡野:Smalltalkという言語を使って、大学の時にゲームを作りました。Pythonに触れたのは大学の時。Ploneというコンテンツ管理システムを大学の研究室のホームページ用に入れたのですが、Ploneは難しかったのでDjangoに移行しました。確か2005年ですね。それまでウェブの開発というと、Delphiを使ってCGIを作成したりしてました。CGIなのに、URLの最後が.exe(笑)とか。
就職した会社がRailsをやっていて、そこでRubyを始めました。その時にオープンソースカンファレンス2006北海道があり、それが初めて行った勉強会というかコミュニティ活動です。勉強会に行くようになったのはそれからです。
渋川:RubyKaigi2008の時に、Ruby札幌の方から「Rubyの勉強会でPythonの話をする岡野というやつがいる」というようなことを聞きましたw。
岡野:Ruby札幌の立ち上げもそのころだったと思います。Pythonのコミュニティへの参加は、まずはチャットなどに参加して、本州のイベントに行くようになりました。夏のPython温泉の最終日に、主催者の中居さん(@voluntas)に紹介されて、東京の品川のスターバックスで治夫さんと面接をしました。
佐藤:中居さんがずーっとしゃべってましたよねw。
渋川:東京と札幌では勉強会は何か違う点はありますか?
岡野:オープンソースのイベントでは、ユーザ(利用者)とデベロッパー(開発者)の2つの立場の人がいるのですが、全体的な人数が少ないせいか、開発者寄りの人と知り合いになるチャンスは少ないですよね。そのため、(開発側の人間としては)東京は勉強会の数も多く、開発者が多い勉強会もあって刺激があります。あとは、札幌の方は懇親会は夜ではなくて、スープカレーを食べながらランチで行うことが多かったです。安いし、夜だと参加できない人もいるので。
渋川:懇親会の方が大切という方もいますよね。昼にというのは初めて聞いたケースですがいいですね。
文殊堂:懇親会はポロリがあるから楽しいです。
渋川:確かに、懇親会でお互いいろいろさらけ出してから勉強会をすると、場が暖まるのも早そうですよね。
岡野:Ruby札幌では、懇親会のあとの勉強会の中でも自己紹介タイムもありました。札幌で厳しかった点は、場所がなかなかない点。お金を取ってしまうと人が来なくなってしまうという点です。
渋川:文殊堂さんはどうでしょうか?
文殊堂:JavaとJavaScriptをやってきました。最近は若手IT勉強会に行って、JavaScriptについて語ったりしています。それまでは、有名な人が見れるということで、ミーハーな感覚でオブジェクト倶楽部や、Shibuya.JSなどに参加していました。
本格的に勉強会に行くようになったのは2年ほど前からで、きっかけは1000スピーカー(趣旨などはhttp://d.hatena.ne.jp/amachang/20080107/1199707365参照)というイベントで、jQueryの話をしたことです。その時は、仕事に対して不安も感じていたりしたので、視野を広げるために他のコミュニティにも行きまくろう、と決意しました。amachangさんのストーキングをしてPython温泉に行ったら、岡野さんから転職した話を聞きました。それで興味を持って、BeProudが主催しているBPStudyという勉強会に参加して、その懇親会で(佐藤)治夫さんと話をして、転職することになりました。
オブジェクト倶楽部のWebページ
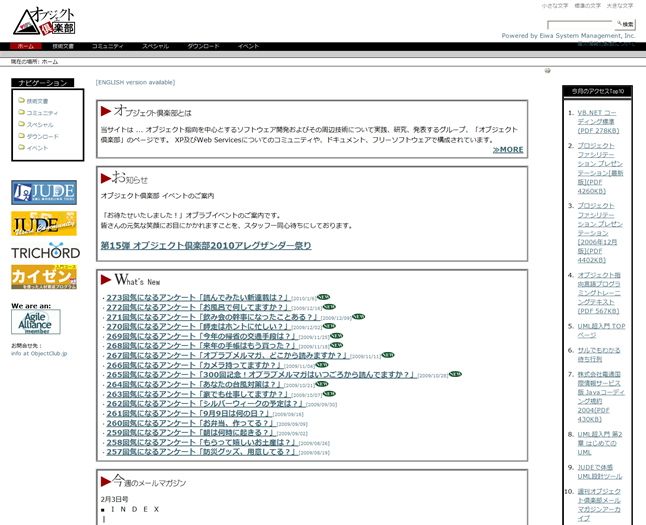
佐藤:(文殊堂さんはハンドルネームで活動しているので)本名で「この人どうですか?」と聞いたら反応がなかったので、ハンドルネームで周りに再度聞いてみたら「いいんじゃないですか?」と返ってきたので採用することにしましたw。
勉強会を立ち上げたきっかけ
渋川:BPStudyという勉強会を立ち上げられたきっかけは何だったのですか?
佐藤治夫:勉強会を開催し始めたきっかけは、技術者が話をできる場を作ろうと思ったことです。知人の紹介や仕事などを通じて、技術的に優れた人達と繋がりができたのですが、どうしても会う回数が年1回とかになってしまう。ですが、勉強会をやっていれば来てもらえるようになって、会う回数は増えますよね。そこで毎月勉強会をやることにしました。最近はTwitterでつぶやくだけで自然と集まってきます。
最初は内輪の会でしたけど、発表者もどんどん広がっています。この前はJava-jaの忘年会でt-wadaさんと知り合って、BPStudyの講師をしてもらうことになりました(2010年1月29日に開催済み)。
Java-jaのWebページ
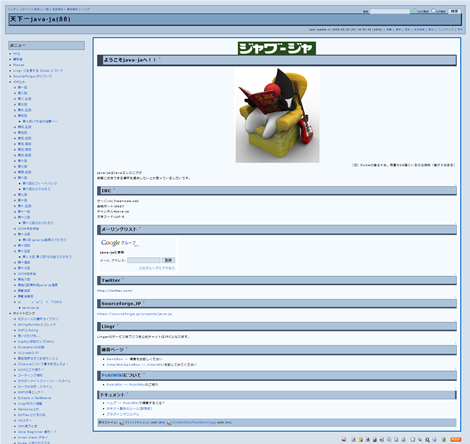
渋川:勉強会のどういう所に楽しさを感じますか?
佐藤:意識の高い人と話せることですね。
岡野:最初は会社でも話が合う人がいなかったし、興味を持つ人もいなかったのですが、勉強会に行くと「おおー!話が通じる!」というところがうれしかったです。
文殊堂:同じく。
岡野:最近では、もう知り合いの集まりに行く感覚ですね。
文殊堂:昔はミーハーで話を聞きに行くだけだったけど、最近は発表もするようになりました。会社の中で技術の話ができる人がいないというのにすごい不安を感じていました。大したことしてないと自分では思っていても、やたら褒められてヨイショされるのが余計に。
奥:不安という言葉を口にされましたけど、具体的にどんな不安があったんですか?
文殊堂:会社の中でできる人が少なくて、ちょっとやっただけで「すごい」「あの人はできるね」と持ち上げられたんですよね。でも、外部のコミュニティに行くと、できる人がたくさんいます。会社ではどんどん自分におんぶにだっこになっていくので、「この会社にいたらこの先どうなるんだろう?」という不安ですね。会社によって、スキルの平均値とか中央値はすごいバラバラ。努力していれば、実は上の1%に入るのは難しくないと思うんですよね。相対評価で高く評価されて、おごってしまうと伸びないです。
実力のはかり方
渋川:採用側はどういった尺度で決めているんですか?
佐藤治夫:話をした感覚ですね。いろいろな勉強会に参加して、多くの技術者と交流したら、見る目が肥えました。
岡野:話をしたら分かりますよね。
文殊堂:自分の中で体系として知識がまとまっていて、その上で自分の思いの丈が話せる人というのがすごい人。先人の知恵と、自分の固有の経験を足して、自分の言葉で話せますからね。
佐藤:面談の最初の1分でほとんど分かっちゃうんですよね。面談に時間がかかる時は「きっと出し切れてない良いところがあるはず」と、いろいろ話をして引きだそうとしている時になりますが、ほとんどは採用に到りません。本当にできる人は、聞く人の得意分野が違うジャンルでも、相手に合わせてポイントを伝えてくるんですよね。
仕事だけでやっている人と、好きでやっている人は明確に差があります。勉強会経由の人はとにかく意識が高い。プライベートと仕事の差がない。コミュニティ内での評判、ブログを見れば一目瞭然ですよね。
文殊堂:できる技術者の評判というのは分かりやすいですよね。コミュニティがあると、そういうのが出やすい。「このできる人が『あの人すごい』と言っている」というのは分かりやすい。
岡野:意識の差はありますよね。今の会社はそういう人が集まっているので、勉強会でしかできなかったような話題が社内で飛び交うのがいいと思っています。特に隣の席のイアンは英語が得意なので、海外からもたくさんネタを収集してきてくれます。
イアンのWebページ

佐藤:技術が好きな人は、懇親会の時もずっと技術の話をしていますよね。世間話などの話に流れることもなく。
勉強会経由以外だと、Moongiftさんのジョブボードで個人事業主の人に来てもらったこともありますが、蓋を開けてみたら知り合いでした。後は求人をTwitterに書いたら、RTされて、それを見て来た人もいます。
大切なのは自主性
岡野:うちの親が面白いんですよ。この前実家に帰ったら、数独を解くプログラムを作ってました。N88-BASICの互換環境。親は別にプログラマーではなくて、鉄鋼の管理職です。
渋川:N88-BASIC!僕もそこからスタートしました。最近はN88-BASICみたいな気軽にできる環境ないですよね。ブラウザのJavaScriptぐらい?
岡野:アウトプットが早いのが大切ですよね。
渋川:学生の方々に向けて何かメッセージはありますか?
岡野:勉強するのは、自分のやりたいことを実現するため。大学の後輩を見ても、勉強を自発的にやりたくなるような、そういうきっかけを掴める人はそれほど多くはないです。自分からアクションを起こす人はいない。
奥:ブレーキがないのが正しいですよね。
文殊堂:自分がやらなきゃ、という意志は大事。一生懸命やっていたら、気づいたら朝ということも何度かあります。言われてやるのではなく、勝手にやらなきゃいけない。努力をしないと、どんなに若くても3年で老害になれちゃう。
努力を楽しむことが大切
いかがでしたでしょうか?今回の座談会は、勉強した結果、チャンスを掴むことができた一例として、紹介しました。といっても、本記事では転職を積極的に推奨しているわけではありません。例えば、社内の評価、本の執筆依頼、勉強会の立ち上げをするなども、「スキルが人に評価される」という点では転職と同じでしょう。多くの人は、自分のスキルアップと、自分の仕事を良くしたいという目的を持って参加していますので、この記事だけ読んで「勉強会に行くのは禁止」なんて言わないように。
地方など、人が少なく人脈を広げるのがなかなか難しいところもありますが、勉強などの努力をしていなければ、さらにどんどんチャンスがなくなっていきます。勉強は「卒業したらおしまい」というわけではなく、頭を使う仕事をしているのであれば、社会人になっても継続しなければ、どんどん差をつけられてしまいます。現在執筆中の技評SE選書には、ラクをして成果を出す勉強法は書いていません。身につく勉強はそんなに簡単ではないでしょう。ですが、たとえラクではなくても、楽しむことはできます。できる人は「努力を楽しんで行う」という習慣を身につけています。自分を追い込むことなく、楽しく勉強をしていく方法を紹介します。また、今回ご紹介した内容とは別に行った座談会の様子も、本書の中で紹介します。