ビジネスモデル症候群 ~なぜ、スタートアップの失敗は繰り返されるのか?
- 和波俊久 著
- 定価
- 1,848円(本体1,680円+税10%)
- 発売日
- 2017.9.15
- 判型
- 四六
- 頁数
- 224ページ
- ISBN
- 978-4-7741-9216-1 978-4-7741-9273-4
概要
ビジネスモデルを考えれば考えるほど、起業は失敗する可能性が高くなる?
かつてない視点で大反響を巻き起こした「ビジネスモデル症候群」がついに完全書籍化。2度の起業経験を持ち、スタートアップのコンサルティングやメンタリングで活躍する著者が、これまでの常識を覆す視点から、スタートアップが失敗するメカニズムと対策を豊富な図解とともに解説します。
こんな方にオススメ
- 起業を考えている方
- スタートアップの経営者
- 起業支援者の方(投資家など)
目次
はじめに ~スタートアップはビジネスモデルを手にするから失敗する
- ジレットは替え刃で売上を上げようなどとは思っていなかった
- ビジネスモデルのコンテストは増えても、起業家は増えていない
- ビジネスモデルを考えれば考えるほど、起業は失敗する可能性が高くなる
第1章 ビジネスモデル症候群とは
症状その1:バイアス ――アイディアが仮説検証をダメにする
- 「協力者にバイアスをかけない」というアドバイスだけではうまくいかない
- 自分に都合のいいことだけを見てしまう「確証バイアス」の落とし穴
- 頭のなかで何を考えているかによって、ひとは視覚にも影響を受ける
- アイディアを持ってしまってから対策を講じても遅い
- 「集団化」「権威からのお墨付き」でバイアスはより強固になる
- コラム デザインファームがバイアスから逃れられる理由
症状その2:ヒューリスティック ――アイディアが“本物”かどうかがわからない
- 「直感的に手に入れた結論」が真実である可能性はとても低い
- 「熟考からしか得られない答え」も探すべき
- 「アイディアが浮かばない」のではなく「アイディアが自分の脳を欺し始める」から起業は難しい
症状その3:経営破綻 ――アイディアより先に経営が行き詰まる
- 「失敗」なのか、「まだ成功していない」なのか
- スタートアップは「経営」と「事業」の二重構造
症状その4:手段の目的化 ――課題を解決するほかの方法が目に入らない
- ひとは変化を無意識のうちに拒む
- なぜ、「手段の目的化」が進行し始めるのか
- 手段の目的化はメンバーの「サラリーマン化」を誘発する
症状その5:失敗のループ ――うまくいかない状況から抜け出せなくなる
- スタートアップでは「金銭」より「時間」の損失のほうが高くつく
- 「アイディアがよければ大丈夫」という思いで失敗がパターン化する
- 稼ぐ手段があるからこそ、ふりかえりの機会を失ってしまう
- 多数派の事例が研究されない
第2章 なぜ、ビジネスモデル症候群に感染してしまうのか ――原因と感染経路
「ビジネスモデルの神格化」が、ビジネスモデル症候群を招く
- 誤解その1「成功したスタートアップにはビジネスモデルがある」
- 誤解その2「スタートアップとはビジネスモデルでイノベーションを目指すこと」
- 起業家「以外」のひとが感染源になる
ビジネスモデルコンテスト ~「育成」の概念がないから弊害が生まれる
- ビジネスモデルコンテストとは「発掘と選別」の仕組み
- かつては発掘には価値があったが……
起業家育成プログラム ~不明確な「育成目的」が悲劇をもたらす
- スタートアップへの評価は3つに細分化される
- 育成プログラムが本物かどうかを見極める方法とは
ビジネスモデル関連書籍・メディア ~マニュアルで成功はつかめない
- 成功談は美化される
- 権威×ノウハウの罠
投資環境の変化 ~「アドバイスが育成につながる」という誤解
- 「投資は選別」と気づかない起業志望者
- 日本では放っておいたら優秀な起業志望者は集まらない
なぜ、起業支援家たちはビジネスモデル症候群から脱却できないのか
- 起業の目的の多様化についていけない
- 起業の目的は変わっていく
- コラム ホールインワン理論
第3章 ビジネスモデル症候群から脱却するには
「確証バイアス」「ヒューリスティック」「手段の目的化」に対処する
- アイディアと仮説は、意図的に反証することに意味がある
- 「最小努力の法則」に学ぶ人間の直感の落とし穴
- アイディアを探すのではなく、問題を理解する
よいメンターを手に入れよう
- 「成功の後押し」ではなく「大失敗させないためのアドバイス」をしてくれる人を
- 課題の当事者にメンターがいる
問題を可視化して「手段の目的化」を解決する
- 「マンダラチャート」で取り組む課題の本質を明らかにする
- 問題を正しく理解していないと、必ず回答をまちがえる
- コラム フレームワークのおかげで目に見えない要素が可視化される
第4章 起業の本質を知り、再スタートしよう
起業とは「経営」であり「ライフスタイル」である
- 起業とは経営である
- 起業とは「経営者という人生を選択すること」
- 起業とはダイエットのようなもの
やりたいこと・できること・求められること理論
- 「ビジネスが成功する」というのはどういうことか
- 「やりたいこと」の幅を広げ、「できること」を増やし、「求められること」を学習する
起業の目標と始め方を再確認する
- まちがった角度で発射されたロケットは、やがて失速する
- 目的によって、成功を測定する指標は異なる
- 目標は更新されていく
- オタマジャクシ社長でもいいので、とにかく経営者として生きていく
- チャンスは経営者だけに巡ってくる
- 「ビジネスの開始と終了」と「法人の開始と終了」を分離する
- 最初の法人格と収入源を適切に選ぶ
- 「売上ばかりを優先すると中小企業化してしまう」は正しいか?
失敗のループから抜け出そう
- ひとは、自らの正当性を維持するために、自分で自分にウソをつく
- 起業という探検は「いかに失敗から数多くのことを吸収できるか?」でしかない
- 再スタートの覚悟はできたか?
- 「不確か」な挑戦の成功率を上げたかったら、まず支援する側のレベルアップが必要
- 研究を重ねることによって、再現性が確認された適切な指導が可能になる
- アドバイスしても大丈夫なことと、しても意味はないことを理解しない限り、足を引っ張る可能性がある
- 成功者を産むことも大事だが、失敗者を出さないメカニズムの研究も絶対に必要
おわりに 「起業」はいつになったら「科学」になるのか
プロフィール
和波俊久
Lean Startup Japan LLC代表。国立大学法人琉球大学「ベンチャー起業講座」プログラム設計兼講師。
自身2度の起業経験と、IT企業でのプロセスコンサルタントとしての活動を経て、2012年にLean Startup Japan LLCを設立。日本の「トヨタ生産方式」を起源とするリーンスタートアップの考え方を利用した新規事業の立ち上げ支援を行っている。プロセスコンサルタントの視点を活かし、「どのような事業を始めるか」ではなく「どのように事業を始めるか」にフォーカスした独自のコンサルティングを提供する。クライアントはベンチャー企業や将来起業を目指すアントレプレナーのみならず、新規事業創出を手がける大企業や地方自治体にも及んでいる。
Lean Startup MachineやStartup Weekendといった世界的な起業家向けイベントなどで、メンター(アドバイザー)としても活動している。
ブログ:http://leanstartupjapan.org/
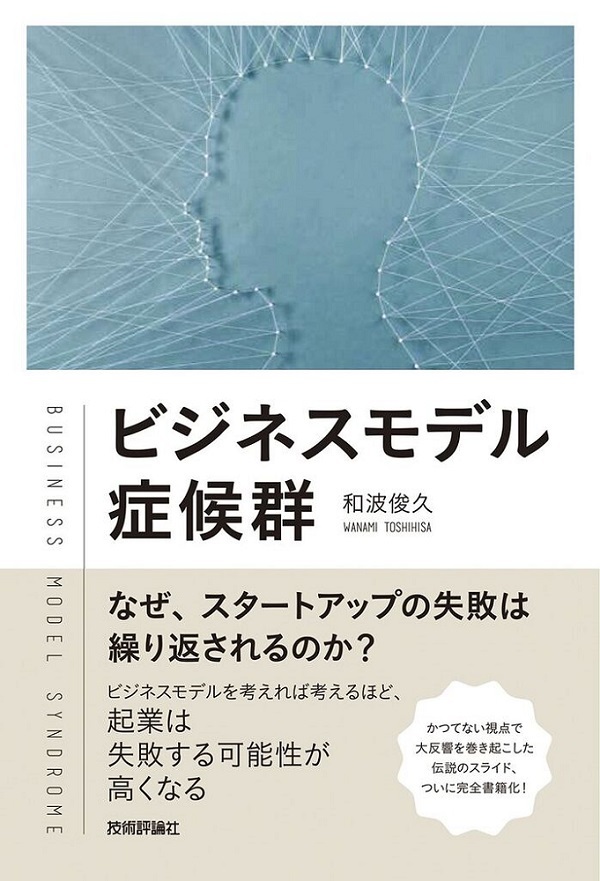
著者の一言
スタートアップはビジネスモデルを手にするから失敗する
「ビジネスモデル」という言葉のイメージは、起業を成功させる最も重要な要素だというものではないですか。ネットを見ても本を読んでも、はたまたイベントへ参加しても、「差別化されたビジネスモデルを考えることができれば起業は成功する」と言ってるし、事実、有名なスタートアップ(ベンチャー)は今までにはない画期的なアイディアで成功しています。彼らのような成功を手に入れるには、自分も同じようにアイディアを手に入れる必要があるはずです。そもそも、ビジネスモデルがなくて成功しているスタートアップなど1社も知らないのですから。
しかし、本書はその常識の逆を解説する書籍です。そう、「スタートアップはビジネスモデルを手にするから失敗する」のです。
ジレットは替え刃で売上を上げようなどとは思っていなかった
私だって、つい最近までは「起業を成功させるには競争力のあるビジネスモデルが絶対に必要だ」と信じ切っていました。しかし、最近読んだ論文に、ビジネスモデルの事例として有名な「ジレットの替え刃モデル」に関するとても興味深い話がありました。
ジレットの替え刃モデルとは、T字型のひげそりの販売において、握り手であるかみそり本体の販売ではなく、交換式の替え刃によって儲けを生み出そうというビジネスモデルです。本来は売り切りで完結してしまう「ひげそり」という商品から、「替え刃」という永続的に売上を上げ続けることができる優良ビジネスモデルとして、ビジネススクールなどでも頻繁にケーススタディとして利用されています。
仮にかみそり本体は無料で配布しても替え刃で儲けられることから、いわゆる「フリーミアムモデル」の原型にもなったと言われていますし、家庭用のプリンターと交換式トナーなど、消耗品からより多くの利益を得る手法のオリジナルだと言われています。また、家庭用ゲーム機とゲームソフトなど、ゲーム機本体を低価格で提供しても、機種依存のソフトから利益を得るという「ロックインモデル(ユーザーを自社商品から離れられないようにする仕組み)」の原型とも言われます。ジレットの創業者であるキング・ジレットは、いつの時代にも、このビジネスモデルを生み出した「稀代の起業家」として語り継がれています。
しかし、最近の調査・研究では、じつはキング・ジレットは替え刃という消耗品から多くの売上を上げようなどとはいっさい考えていなかったであろうことがわかってきました。
http://www.law.uchicago.edu/faculty/research/randal-c-picker-razors-and-blades-myths
当時の商品広告や競合他社の商品群、そしてキング・ジレットが取得した特許の内容といった客観的な事実を総合的に判断すると、そこに天才起業家としての姿はなく、ビジネスモデルが成立した可能性も低いというのです。
そもそも、替え刃で儲けるためのロックインは、ひげそりではおこなえないものでした。競合他社のかみそり本体がとても安く、乗り換えが容易であったためです。そればかりか、ジレット本人が「ジレットの替え刃は他社製品のひげそりでの使用を推奨しない」と広告を出すなど、替え刃から儲けようとしていたのであれば考えられないようなことが多数存在するというのです。
何かおかしいと思いませんか? 当事者であるキング・ジレットは「替え刃モデル」というビジネスモデルを発明したつもりもないのに、なぜか後世にはあたかも“天才起業家が産み出した画期的なビジネスモデル”として語り継がれています。真相の追求にはあまり意味がありませんが、「このビジネスモデルがあったからこそジレットは成功できた」というストーリーには大いに疑問が残る調査結果です。
ビジネスモデルのコンテストは増えても、起業家は増えていない
2010年代は、世界的なスタートアップブームだといわれています。スマートフォン、SNSといった2000年代から続く分野以外にも、人工知能(AI)やロボット、金融、IoTなどのさまざまな分野で、新しいスタートアップとサービスが誕生しています。グローバル化の流れとともに、私たちは常に新しい製品・サービスに触れ続けるようになりました。
一方で、2017年に中小企業庁が発行した『中小企業白書』によれば、日本の起業率は「起業家数」「起業準備者数」「起業希望者数」のいずれも1997年以降は減少を続けていて、起業家がいっこうに増えていません。この事実、あなたが直感的に感じている傾向とかなりズレていませんか?
しかも、起業家の平均年齢は上昇傾向にあり、まもなく50才を超えます。その反面、学生および若年層(白書では30代までが対象)の起業希望者数は年々減少し、実際に起業している起業者数に占める30代以下の割合は減少しています。どうやら、日本における起業のハードルは、世界的なスタートアップブームにも、クラウドサービスやコワーキングオフィスなどの普及にともなう大幅なコストダウンにも関わらず、依然としてとても高い状態で推移しているようです。
こうした状況を、行政も自治体もただ静観しているわけではありません。政府系金融機関や教育機関に対して起業家育成プログラムの開催資金を提供し、特に学生を対象とした起業家育成がおこなわれています。日本政策金融公庫が平成25年から実施している「高校生ビジネスプラン・グランプリ」では、参加校数、参加者数ともにわずか4年で倍増しており、明るい兆しも見えてきています。
しかし、私も全国のこうしたビジネスプラン、ビジネスモデルのコンテストにメンターや講師という立場で関わっていますが、日本で開催されるコンテストの最大の特徴は「優勝者がだれも起業しないこと」です。これは、学生、社会人を問わず、また主催の官民を問わず、コンテストを「起業の足がかり」として考えていない人が集まるイベントと化しているということです。優勝者も参加者も、イベントが終了すると元の生活へ戻っていきます。学生は就活へ、社会人はサラリーマンへ戻るのです。
おそらくはこの本を手に取った方の多くが、「日本も、海外と同様に、起業ブームの最中にある」と感じていると思います。SNSではスタートアップに関するメディア記事が大量にアップされていますし、各種イベントも盛んです。実際に起業した友人もいますし、そうした彼らのITサービスも使ってます。
でも、みなさんが観ているその世界は、じつは日本では「ごく限られた、狭い世界」であり、実際には大きくなってはおらず、ただSNSを通して「可視化」できるようになっただけかもしれません。少なくとも中小企業白書を見る限りは、そう判断せざるをえません。
ビジネスモデルを考えれば考えるほど、起業は失敗する可能性が高くなる
このように、有名な事例がじつはフィクションである可能性が指摘されたり、コンテストを足がかりに起業する人がほとんどいなかったりと、なんとなく「ビジネスモデル」という言葉がこれまで持っていた華々しさに陰りが生じています。
これまで、スタートアップを目指す人にとって、ビジネスモデルは成功を左右する最も重要な要素であり、決して欠かすことができない存在でした。エレベータピッチ(ほんの短い時間でおこなうプレゼンテーション)でうまくビジネスモデルを伝えて投資家の関心を引くことができれば、自分たちにも起業のチャンスが訪れるかもしれません。ビジネスモデルを考えることは、人生を変えるきっかけを作るものでした。
しかし、その一方で「ビジネスモデルを考えすぎると起業は失敗しやすくなる」としたら、どうしますか?
「ビジネスモデルを考えれば考えるほど、かなり高い確率で、起業は失敗する可能性が高くなりますよ。すべての人に当てはまるわけではありませんが」
私が起業家育成の場で、いつもお話ししていることです。
「? そんなことはあるはずがない」とあなたが思うのは、とても普通のことです。しかし、私の経験では、多くのスタートアップは「ビジネスモデルがイケてなかったから失敗した」のではなく、「ビジネスモデルを持ったから失敗した」のです。
私の言葉は、起業という人生で最も大きなイベントの1つを、ビジネスモデルという「アイディアの中身」に過剰に依存してはいけないということを意味しています。ここ数年の調査や経験によって、必要以上のビジネスモデルへのこだわりは、かえって起業の成否に悪影響を及ぼす可能性がわかってきたのです。こうした現象を、私は「ビジネスモデル症候群」と名づけました。
今まさに起業を目指してビジネスモデルを考え続けている方は大勢いると思いますし、すでに起業してビジネスモデルがあるという方もいると思います。ですが、どちらの場合でも、もし思うようにビジネスが立ち上がっていないようでしたら、ぜひこの本を読んでみてください。
「自分がなぜ、熱い想いとは裏腹に、空回りし続けているのか?」
それがきっとわかるはずです。
起業のノウハウを紹介する本は多数存在しますが、実際に起業した人たちがどのように失敗していったのかを「研究対象」にした本は滅多にありません。単なるエピソードとしてではなく、先輩たちの失敗の「分析結果」を知ることは、次に挑戦するみなさんにとって、とても貴重な知識になるはずです。
アメリカのルーズベルト大統領のファーストレディだったエレノアは、こんな言葉を残しています。
Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.
(他人の失敗から学びを得なさい。そのすべてを自分で体験できるほど人生は長くないから)
この本は、ビジネスモデルの構築を目指して失敗していった数々のスタートアップから、後に続くみなさんへ伝えるべきメッセージを私が「代筆」するものです。彼らも気づかなかった失敗の原因をいっしょに探っていきましょう。