問題地図
異文化理解の問題地図
~「で、どこから変える?」グローバル化できない職場のマネジメント
- 千葉祐大 著
- 定価
- 1,848円(本体1,680円+税10%)
- 発売日
- 2019.3.7
- 判型
- 四六
- 頁数
- 192ページ
- ISBN
- 978-4-297-10415-3 978-4-297-10416-0
概要
累計21万部突破の問題地図シリーズ最新作!
「指示したとおりにやってくれない。いつも中途半端な仕上がりで、期限も守らない」
「ことあるごとに文句を言って、やたら主張してくる。なかなか納得してくれない」
「個人プレーが目立ち、チームで仕事をしようとしない。報連相も不十分」
「空気を読めない。まわりが忙しくしていても、平気で連休をとる」
「問題があっても『大丈夫』と言う。とにかくウソが多い」
「自分が悪くても非を認めない。やたら言い訳が多い」
「せっかく時間と金をかけて教育したのに、突然辞められた」
改正出入国管理法(改正入管法)も可決され、日本の職場でもますます増えていく外国人材をどうマネジメントすればいいのか?
59ヵ国・地域、のべ6000人以上もの外国人への指導経験を持つ著者が、旧態依然の日本式マネジメントを変え、優秀な外国人従業員の力を引き出す方法を教えます。
【巻頭付録】異文化理解の問題 全体マップ
こんな方にオススメ
- 指示したとおりにやってくれない
- 中途半端な仕上がりで、期限も守らない
- 報連相も不十分
- 空気を読めない
- 問題があっても「大丈夫」と言う
- やたら言い訳が多い
- 突然辞められる
- といったことに1つでもあてはまる職場にいると思う方
目次
はじめに 職場が外国人だらけの時代がやってきた!
1丁目 指示が正しく伝わらない
- 指示が正しく伝わらない伝え方の3つの原因
- 根本原因は「聴き手に責任を押しつけられるコミュニケーションスタイル」にある
- 「部下のことを理解していない」からうまくいかない
- 重要なことは最低3回くり返す
- 言葉の量は5割増しで
- 「理由」と「目的」を必ず伝える
- 「イエス」「ノー」を明確にする
- 「口角2割アップ」を心がける
- 図やイラストで伝える時の4つのポイント
- 1日5回の問いかけを習慣にする
- コラム 笑いのツボは万国変わらない
2丁目 主張だらけ
- 主張の背景にある3つの心理
- 「ほめアプローチ」の3つのポイント
- 5回ほめて1回叱る(5対1の法則)
- ほめ言葉サンドイッチ法
- ほめる時は声のボリュームを2割増しに
- 理由を3つ重ねる
- 例外をつくらない
- 結論オウム返し法
- 「今週の評価」をフィードバックする
- 「主張は悪」の考えは捨てよう
- いまのうちから「異論があたりまえ」の職場環境をつくる
- コラム 政治の話題は避ける
3丁目 チームワーク不全
- 実力は折り紙つきの精鋭ばかり、でもつねにバラバラ……
- チームワーク不全には外国人材特有のワケがある
- 報連相は具体的にルールを決める
- 共通の仮想敵をつくる
- 全員の前で自己紹介プレゼンをしてもらう
- 仕事外のコミュニケーションの機会を増やす
- 「仲間に協力したほうが評価は上がる」と思ってもらえる制度をつくり、くり返し伝える
- コラム アジアの若者のなかには200万人の天才がいる
4丁目 空気を読めない
- 日本の職場に巣くう「暗黙のルール」
- 空気を読めない3つの背景
- ルールを「見える化」する
- 上司の「こだわり」を言語化する
- 日本人のホンネを教える
- コラム 「建前のマニュアル」は外国人に売れる!?
5丁目 自信過剰
- 日本人とは違う自信マンマンなリアクション
- 自信過剰のウラにある心理
- 質問はとことん具体的に
- マイナス情報の報連相を義務化する
- 日本の常識を教える
- コラム 遅刻が多い外国人材に時間を守らせるには
- コラム 外国人材が日本人の若手社員に与える好影響とは
6丁目 すぐに辞める
- 今日もまさかの退職表明「ワタシ、国に帰ります」
- 日本人とはまったく違う退職理由がある
- 2段階でこれから得られるメリットを提示する
- 「この仕事は将来あなたの役に立つ」というキラーフレーズ
- 本気なら「制度の変更」も検討していく
- 孤独にさせないしくみをつくる
- 何を期待しているか伝える
- 外国人にしかできない仕事を与える
- コラム ここまで来た! 職場の多様性の尊重
おわりに まずは小さなことから始めてみよう
プロフィール
千葉祐大
外国人材コンサルタント。一般社団法人キャリアマネジメント研究所 代表理事。
1970年生まれ。花王株式会社に12年間勤務。2002年に香港の同社現地法人に駐在し、前任者のいない副部長職を任されるも大苦戦。異文化マネジメントの知識やノウハウをもたないまま自己流の対応をおこない、惨憺たる結果に終わる。業績を大きく悪化させただけでなく、「あなたのような無能な上司のもとで働くのは無理」と面罵され、立て続けに部下に依願退職されてしまう。会社からも「マネジメント能力ゼロ」の烙印を押された。そのときの経験が、異文化の相手とどうすればうまく関わっていけるかを探求するきっかけとなった。
2006年に外国人材関連のコンサルタントとして独立。異文化対応に悩むビジネスパーソンに、価値観の違う相手とのコミュニケーション法を指導するコンサルティング業務を始める。並行して大学、専門学校で非常勤講師の仕事を始め、多くの外国人留学生を指導。その数は、これまで59ヶ国・地域、延べ6000人以上におよぶ。
現在は、この分野における第一人者の地歩を確立。全国にクライアントを抱え、企業研修講師としても年間50回以上登壇している。著書に『なぜ銀座のデパートはアジア系スタッフだけで最高のおもてなしを実現できるのか!? ~価値観の違うメンバーを戦力化するための17のルール~』(IBCパブリッシング)がある。
ホームページ:http://www.careermanagement.jp/
メールアドレス:chiba.yudai@careermanagement.jp
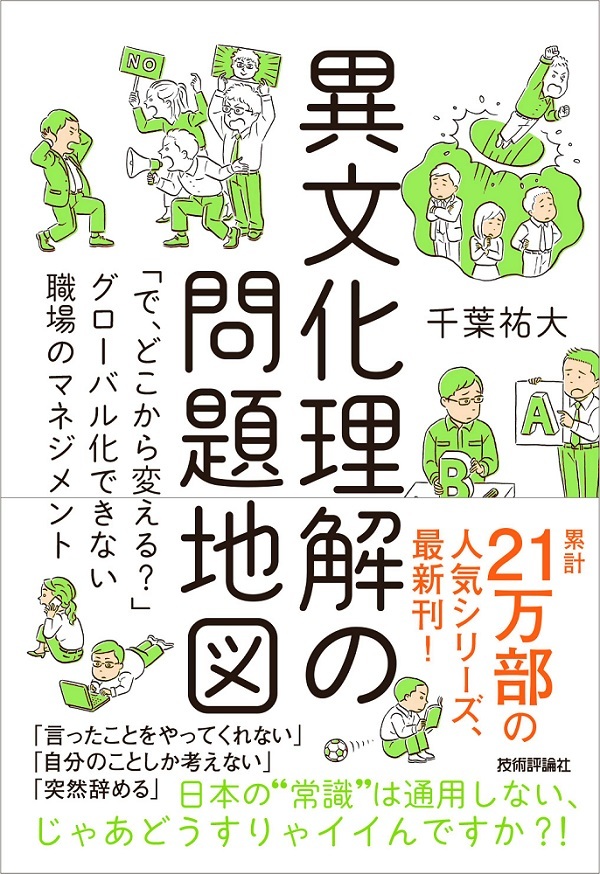
著者の一言
はじめに ~職場が外国人だらけの時代がやってきた!~
あなたは、日本国内でどれくらいの外国人が働いているかご存知ですか?
現在の外国人労働者の数は、過去最高の約146万人(2018年10月時点)。このわずか5年で倍以上に増えました。現在の日本社会は、空前の人手不足。9割近くの会社が人材の確保に苦労しています。そんな状況のなか、救世主となっているのが“外国人材”なのです。
そして2018年12月、この流れを加速する「歴史的出来事」が起こりました。単純労働を含む外国人材の受け入れを拡大する、入管法(出入国管理及び難民認定法)改正案が国会で成立したのです。新たな在留資格が創設されたことにより、これまで以上のスピードで外国人材が増えていくのはまちがいありません。まさに「職場が外国人だらけ」の時代がやってきたのです。
もっとも現状は、長年日本人だけの職場で働き、仕事で外国人材とかかわってこなかった人が多数を占めます。多くのビジネスパーソンは、異文化の職場環境にまだまだ免疫がありません。そのためはじめての外国人部下に、こんな違和感を訴える日本人マネージャーが続出しています。
「指示したとおりにやってくれない。いつも中途半端な仕上がりで、期限も守らない」
「ことあるごとに文句を言って、やたら主張してくる。なかなか納得してくれない」
「個人プレーが目立ち、チームで仕事をしようとしない。報連相も不十分」
「空気を読めない。まわりが忙しくしていても、平気で連休をとる」
「問題があっても『大丈夫』と言う。とにかくウソが多い」
「自分が悪くても非を認めない。やたら言い訳が多い」
「せっかく時間と金をかけて教育したのに、突然辞められた」
いまにも、職場に外国人材がいらっしゃる方から「ウチの外国人社員もまさにこんな感じだよ」という同調の声が聞こえてきそうです。
でも、ちょっと待ってください。それは外国人材が一方的に悪いのでしょうか?
断言します。多くのケースにおいて、異文化マネジメントの機能不全は、相手を理解しようとしない日本人マネージャーの側に責任があります。そして、日本人マネージャーしだいで解決できるケースが多く、やり方もそれほど難しくありません。ただ、やることは確実に増えます。日本人の部下には不要なアクションをたくさんしなければいけませんから。
「ああ、外国人の部下って、ホント面倒くさいなあ……」
外国人材のマネジメントに慣れていない多くの日本人マネージャーの方は、いまおそらく、こんなことを考えながら仕事をしているのではないでしょうか。はい、まさにそのとおりです。彼ら彼女らはとても優秀ですが、とても面倒くさい存在でもあるのです。
それに、ひとくちに“外国人材”といっても、その属性は多岐にわたります。国籍ごとに特性は異なり、日本語レベルや日本人への理解度も人それぞれ。100人いれば100通りの異文化問題が存在します。異文化理解の問題は、やたら「独自ケース」や「場合分け」が多いのが特徴です。
もっとも、すべてに共通する原則はあります。それは、
「受けとめ側の捉え方しだいで、異文化問題の本質やレベルはいかようにも変わる」
ということ。どんな事象に対しても「違いがあってあたりまえ」と考えられるようになれば、多くの問題は想定内にとどまるでしょう。
「違いを受入れ、それに合わせて少しずつ行動を変えていく」
そうすることができれば、どんな異文化問題も必ず解決に向かいます。
本書は、私が国内のマネジメントの現場で得た「異文化あるある」をピックアップし、それらを問題地図として描いたものです。あなたの職場にもあてはまる事象を見つけ、「これは」と思う解決策を試してみる――そういう使い方をする前提で本書を読み進めてください。あなたのやり方しだいで、外国人材は必ず変わります。そして、日本人以上に活躍してくれるようになります。その具体的な方法を、いまからいっしょに探っていきましょう。
私は長年、メーカーやサービス業の現場で異文化マネジメントに携わり、教育機関の講師としても、これまで延べ6000人以上の外国人材とかかわってきました。これから本文でご紹介する知見やデータは、高い妥当性があると自負しています。本書が少しでも、職場の異文化問題に悩むみなさんの一助となれば、これに勝る喜びはありません。