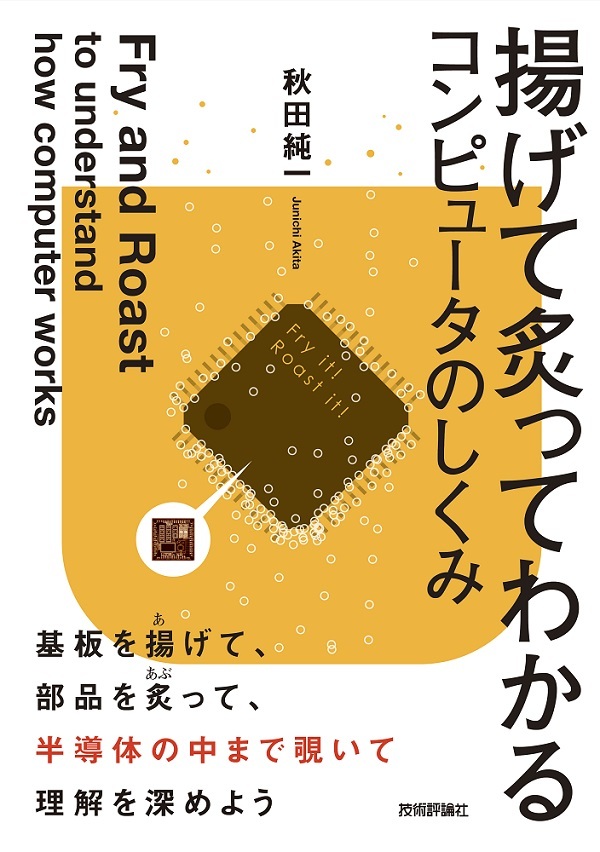揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ
- 秋田純一 著
- 定価
- 2,398円(本体2,180円+税10%)
- 発売日
- 2020.8.19
- 判型
- A5
- 頁数
- 160ページ
- ISBN
- 978-4-297-11601-9 978-4-297-11602-6
概要
技術が進むにしたがって、コンピュータの中身が見えなくなってきています。コンピュータの頭脳としてCPUがあって、OSがあってプログラムが動く…。漠然とわかっていても、実際にどういうしくみで意図したとおりに動作しているのかとなると、なかなかイメージできないものです。本書はこのように、ブラックボックスになっているコンピュータのしくみを、「炙る」「揚げる」などの過激な手法も用いつつ、半導体レベルから実際に目に見える形でひもといていきます。
こんな方にオススメ
- コンピュータの仕組みを知りたい人
- Maker(『ハードウェアハッカー』の読者層)
目次
第1章 ソフトウェアとハードウェアの世界の境界
1.1 コンピュータが「見えなく」なってきている
- むかしはパソコンと電子回路は一体
- コンピュータを理解する上での抽象化・ブラックボックス化
1.2 ブラックボックスの中身を見るといいことが?
- ブラックボックスの中身を見る=限界を知る
- ブラックボックスの中身を見る=原因を知る
1.3 コンピュータの歴史と表裏一体の「半導体の歴史」
- コンピュータの中身=集積回路
- コンピュータの歴史と集積回路の歴史
- ムーアの法則、その意義
- 限界が見えてきたムーアの法則
- トランジスタの挙動が「わからなく」なる
第2章 ソフトウェアから近づいてみる
2.1 IoT:モノのインターネット
2.2 インターネットの情報のやりとり
- 「Webページを見る」手順
- インターネット上の情報のやりとり
- インターネット上の通信を階層的に理解する
2.3 コンピュータの中へ
- コンピュータの動作の抽象化のレベル
- コンピュータの入出力
- コンピュータの記憶システム
2.4 マイコンの世界
- 小さなコンピュータ:マイコン
- コンピュータの動作を上から一通り見てきた
第3章 ハードウェアから近づいてみる
3.1 原子から論理回路へ
- コンピュータの最小単位:トランジスタ
- 便利なCMOS回路
3.2 集積回路
3.3 論理回路から演算回路へ
3.4 演算回路からCPUへ
- コンピュータのプログラム=命令の並び
- メモリも論理回路の集合体
3.5 CPUから実用的なコンピュータへ
- コラム 「相性」の正体
第4章 揚げて炙って中身を覗く
4.1 コンピュータの中身を覗く
4.2 基板の美味しい揚げ方
- 基板を揚げてみよう
4.3 炙って見つける半導体
- チップを炙ってみよう
第5章 取り出したチップを解析してみる
5.1 半導体の進化を解析してみる
- データシートから考察する
- ATmega328Pを実際に観察してみる
- ATmega328PBも観察して、考察を裏付ける
5.2 半導体チップのニセモノを解析してみる
- ホンモノとニセモノを比べてみる
- 考察
- さらに深みへ……
- 底なしのニセモノの世界
- コラム 半導体のコストとビジネス
第6章 コンピュータの再構成
6.1 電源ONのあとに起こること
- 割り込みから始まるコンピュータ
6.2 CPUの命令
- CPUが理解できる命令のカタチ
- CPUに渡す命令の意味
6.3 命令の実行
- 1クロックの間に起きていること
- クロックに合わせて次の処理へ
第7章 物理世界とコンピュータとの界面
7.1 コンピュータの進化がもたらした「コンピュータのお手軽化」
- Lチカのパラダイムシフト
- マイコンが道具になるということ
- 日常生活に溶け込んだマイコン
7.2 コンピュータと実世界との接点
- コンピュータへの入口と出口
- 広がる半導体センサの世界
7.3 コンピュータを半導体から使いこなすということ
- 誰でも半導体チップを設計できることの意義
- 「MakeLSI:」を通じた集積回路の民主化活動
プロフィール
秋田純一
1970年名古屋市生まれ。東京大学博士課程修了。公立はこだて未来大学を経て、現在は金沢大学教授。専門は集積回路(特にイメージセンサ)と半田付け、およびそれに関連して、「無駄な抵抗コースター」ほかMakerとして活動する。
- 好きな半田は、Pb:Sn=60:40
- 好きなプロセスは、CMOS 0.35μm
- 著書:『ゼロから学ぶ電子回路』『ゼロから学ぶディジタル論理回路』『はじめての電子回路15講(KS理工学専門書)』(いずれも講談社)