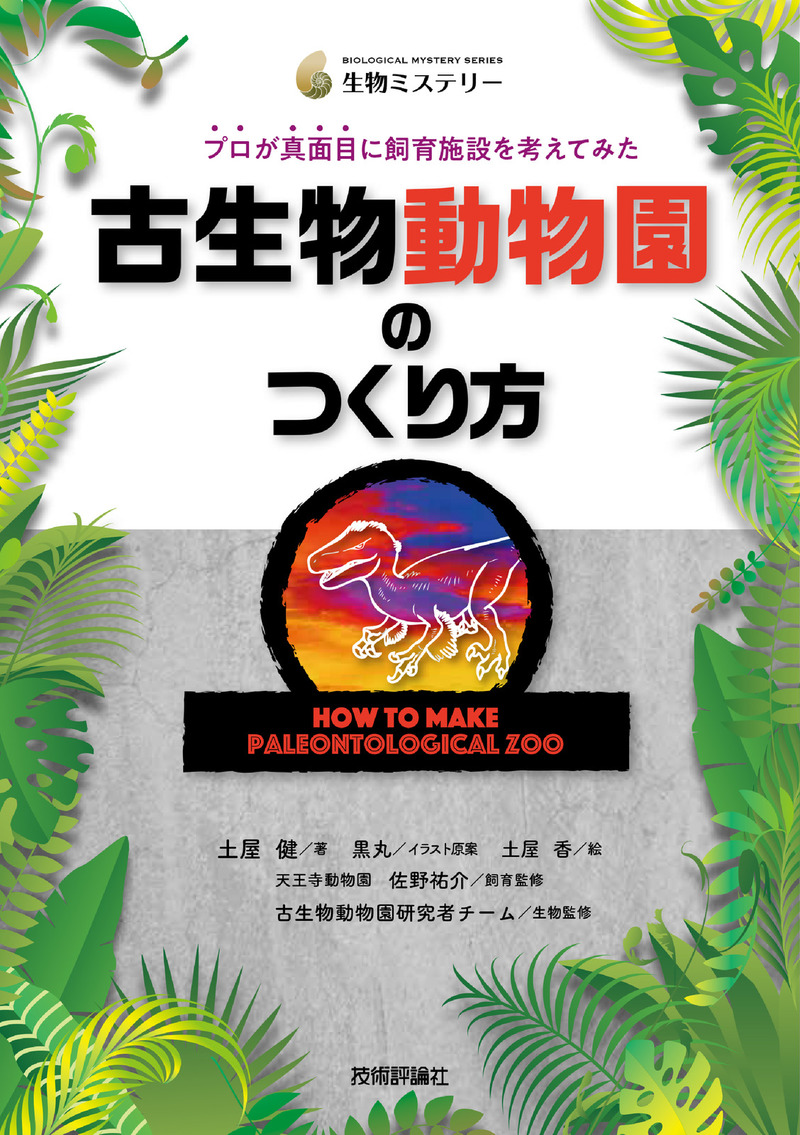生物ミステリー(生物ミステリーPRO)
古生物動物園のつくり方 プロが真面目に飼育施設を考えてみた
-
土屋健 著
黒丸 イラスト原案
土屋香 絵
天王寺動物園 佐野祐介 飼育監修
古生物動物園研究者チーム 生物監修 - 定価
- 2,860円(本体2,600円+税10%)
- 発売日
- 2023.12.23
- 判型
- A5
- 頁数
- 320ページ
- ISBN
- 978-4-297-13967-4 978-4-297-13968-1
サポート情報
概要
「恐竜をはじめとする古生物。やっぱり直接見てみたい!」そう思ったこと、ありませんか?『古生物動物園』は、そんな思いを本の中で実現させてみました。
- 「陸棲古生物を安全に展示できるフィールドとはどんなものだろう?」
- 「飼育や繁殖にはどんな環境が必要なのかな?」
- 「日々の体調管理はどうすれば良いの?」
「古生物動物園」を実現するには何が必要なのだろう?古生物の専門家、現生動物の専門家、そして動物園の獣医さんの叡智を結集し、リアル感満載の施設を生み出しました。(ただし、運営コストだけは度外視)
ついに実現した「古生物動物園」とは、いったいどんな施設なのでしょう?今まさに開園です。
こんな方にオススメ
- 古生物&恐竜ファン
- 古生物の生態や行動について興味のある方
- 動物飼育や管理の施設がどう運営されているのか関心のある方
目次
zone A「館ゾーン」
- 始祖鳥
- イー
- メイ
- ミクロラプトル
- コエルロサウラヴス
- ヴォラティコテリウム
- ミアキス
- ディプロカウルス
- スクレロセファルス
- エリオプス
- カストロカウダ
- プロトケラトプス
- オルニメゴロニクス
- デイノニクス
- パレオカスター
- ケナガマンモス
- ケツァルコアトルス
- ツパンダクティルス
zone B「平野ゾーン」
- ディメトロドン
- ステゴサウルス
- マメンチサウルス
- トリケラトプス
- ニッポノサウルス
- アンキロサウルス
- デイノケイルス
- ガストルニス
- エオヒップス
- ディイクトドン
- モスコプス
zone C「ふれあい広場」
- エウロパサウルス
- プシッタコサウルス
- ファルコーネリゾウ
zone D「ゾウの進化&肉食ゾーン」
- メリテリウム
- マムート・ボルサニ
- ナウマンゾウ
- アロサウルス
- イノストランケヴィア
- アンドリューサルクス
- スミロドン
- ティラノサウルス
zone E「水辺ゾーン」
- マチカネワニ
- コティロリンクス
- チャンプソサウルス
- ハイファロサウルス
- スピノサウルス
ようこそ! バックヤードツアー
プロフィール
土屋健
サイエンスライター。オフィス ジオパレオント代表。日本地質学会員、日本古生物学会員、日本文藝家協会員。埼玉県出身。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て、現職。2019 年にサイエンスライターとして初めて日本古生物学会貢献賞を受賞。愛犬たちと散歩、愛犬たちとの昼寝が日課。古生物に関わる著作多数。近著に『生命の大進化40 億年史 新生代編』(講談社)、『地球生命 無脊椎の興亡史』、『恐竜たちが見ていた世界』(ともに技術評論社)など。動物園で動物を見ると、つい、我が家の犬たちとのちがいを考えてしまう。
黒丸
漫画家。代表作は『クロサギ』シリーズ(原案/夏原武)『絶滅酒場』など。『東京サラダボウル』をパルシイ&コミックDAYS で連載中。
土屋香
茨城県出身。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号(地質学、古生物学)を取得。古生物を中心にイラストを描く。『ゼロから楽しむ古生物 姿かたちの移り変わり』(技術評論社)などのイラストを担当。ネットショップ「恐竜・化石グッズの専門店 ふぉっしる」店長。
佐野祐介
2005年に岩手大学農学部獣医学科を卒業後、大阪の天王寺動物園で獣医師として勤務。子どものころの愛読書は図鑑(笑)。恐竜等にもどっぷりで、恐竜展には足を運んでしまう。本書の監修にあたり、現生動物を基準に古生物の飼育条件を設定してみたが、こんな広さの飼育スペースを整備したら、コストがとんでもないことになるので、現代に恐竜がいたとしても絶対飼育できないなと改めて思い知らされた。そして、彼らが大きすぎるがゆえに、実際には獣医師の出番は少ないだろうな(手が出せないから)……と想像でき、少し寂しくもあり……。
奥村よほ子
栃木県佐野市の葛生化石館で学芸員をしています。石灰岩の中から見つかる古生代の小さな化石が専門です。とくに古生代ペルム紀に一番興味があります。化石でしか出会えない、今は生きていない古生物たちの姿を想像するとワクワクします。動物園の思い出といえば、ふれあいコーナーが大好きで、動物園に行ったときには必ずモルモットをだっこしてふわふわの毛並みをなでるのがルーティンでした。
北川博道
長野県長野市生まれ。島根大学総合理工学部卒、京都大学大学院博士課程修了。京都大学博士(理学)。京都大学大学院理学研究科教務補佐員を経て2012年から埼玉県立自然の博物館学芸員。その後埼玉県教育局文化資源課を経て、現在埼玉県立自然の博物館主任学芸員。赤ん坊の時に振り回して遊んでいたお気に入りのオモチャが、地元でとれたカキの化石だということに気づいたことから、化石に興味を持つようになり、古生物学の道に進む。専門は古脊椎動物学。特にナウマンゾウを中心とした第四紀哺乳類化石ほか、新第三紀中新世を代表する大型哺乳類化石であるパレオパラドキシアについても研究。近年は、文化財としての化石資料の保存と活用について積極的に取り組んでいる。
木村由莉
国立科学博物館地学研究部生命進化史研究グループ研究主幹。早稲田大学教育学部卒業。米国サザンメソジスト大学地球科学科にて修士号および博士号を取得。専門は陸生哺乳類の古生態と進化史。著書に『もがいて、もがいて、古生物学者!!』(ブックマン社)、監修に『きょうりゅうのたまごをさがせ』(理論社)など多数。ハイスピードカメラを片手にカピバラさんたちが餌を食べる様子などを眺めることが春の恒例行事になっている。
久保田克博
1979年、群馬県生まれ。2002年、筑波大学第一学群自然学類卒業。2008年、筑波大学大学院生命環境科学研究科修了。博士号取得。神流町恐竜センター学芸員を経て、現在は兵庫県立人と自然の博物館研究員。獣脚類恐竜を中心に、恐竜の記載や系統関係について研究している。
高崎竜司
カナダのトロント大学にて、ハドロサウルス科の記載分類・恐竜類の胃の進化などに取り組む。動物園の鉄格子と堀の向こうに熊がいると安心しますね。野生の熊は怖いです。古生物動物園が実現する際には、檻だけはしっかりしてもらいましょう。
田中公教
兵庫県立大学自然・環境科学研究所特任助教。県立人と自然の博物館の研究員を兼務。北海道大学大学院理学院にて博士課程を修了。博士(理学)。専門は古脊椎動物学で、原始的な角竜類の系統分類学や中生代鳥類の水生適応進化などについて研究しています。博物館で化石標本から動物の進化や体のつくりについて学んだあとは、動物園に行って生きた動物を観察してみましょう。きっと、新たな発見がたくさんあって楽しいですよ。
千葉謙太郎
1985年北海道札幌市生まれ。2011年北海道大学理学院修士課程修了。2018年トロント大学生態学進化生物学科にて博士号取得。現在、岡山理科大学生物地球学部講師。カナダやモンゴルで発掘調査をおこない、ケラトプス類恐竜の分類と進化を中心に研究をしている。動物園にまつわる思い出は、小学生のときに札幌市円山動物園で一日飼育員体験に参加し、ワニやダチョウの世話のお手伝いをさせていただいたこと。
林昭次
岡山理科大学生物地球学部生物地球学科准教授・博士(理学)。骨の内部構造から脊椎動物の大型化・小型化の要因や水棲適応について研究しています。
恐竜類・首長竜類・束柱類などの絶滅種から、現在生きている野生動物(シカ、ペンギン、オオサンショウウオなど)までさまざまな動物たちを研究対象としています。私が住む場所は動物園の近くであることが多かったため、子どものころから動物園はとても身近な存在でした。私にとって動物園は、生き物の不思議について考えるための場所であり、私の現在の原点の1つの場所であるといえます。
松本涼子
神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員。英国University College London(ロンドン大学)でPhD を取得。日本学術振興会特別研究員として国立科学博物館に在籍後、現職に至る。絶滅水性爬虫類のコリストデラ類を専門とし、現生動物の顎や首の解剖をしながら、絶滅した動物がどうやって獲物を捕らえて食べていたのかを復元している。自宅では研究用に動画を撮るためミツユビアンフューマを10年ほど飼育中。学生時代に動物園で撮影したいろいろな爬虫類の糞の写真が出てきました。糞化石の研究の参考に集めたものだったようです。動物園は研究題材の宝庫だと改めて思いました。