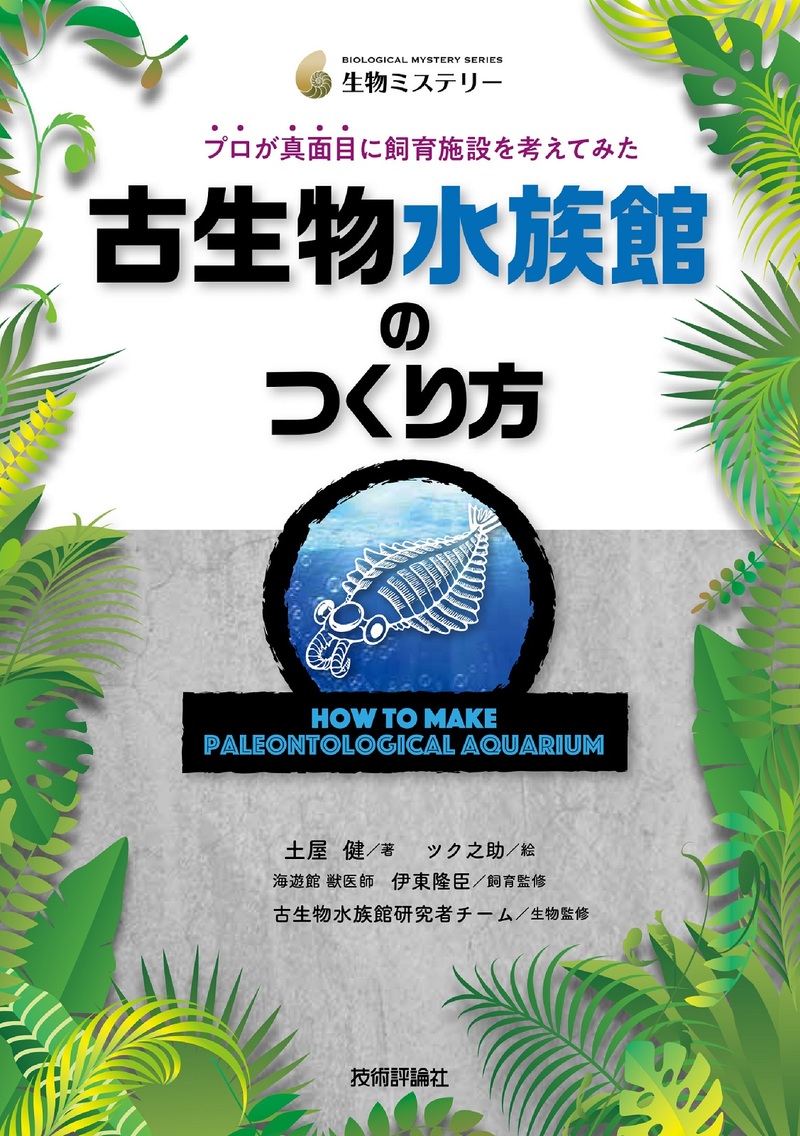生物ミステリー(生物ミステリーPRO)
古生物水族館のつくり方 プロが真面目に飼育施設を考えてみた
-
土屋健 著
ツク之助 絵
海遊館 獣医師 伊東隆臣 飼育監修
古生物水族館研究者チーム 生物監修 - 定価
- 2,530円(本体2,300円+税10%)
- 発売日
- 2023.12.23
- 判型
- A5
- 頁数
- 224ページ
- ISBN
- 978-4-297-13969-8 978-4-297-13970-4
サポート情報
概要
「クビナガリュウをはじめとする水棲の古生物。やっぱり直接見てみたい!」そう思ったこと、ありませんか?『古生物水族館』は、そんな思いを本の中で実現させてみました。
- 「水棲古生物を安全に展示できるフィールドとはどんなものだろう?」
- 「飼育や繁殖にはどんな環境が必要なのかな?」
- 「日々の体調管理はどうすれば良いの?」
「古生物水族館」を実現するには何が必要なのだろう?古生物の専門家、現生動物の専門家、そして水族館の獣医さんの叡智を結集し、リアル感満載の施設を生み出しました。(ただし、運営コストだけは度外視)
ついに実現した「古生物水族館」とは、いったいどんな施設なのでしょう?今まさに開園です。
こんな方にオススメ
- 古生物&水棲爬虫類ファン
- 古生物の生態や行動について興味のある方
- 水棲動物飼育や管理の施設がどう運営されているのか関心のある方
目次
zone A「メイン館1階 サメとその仲間たち」
- メガロドン
- ヘリコプリオン
- アクモニスティオン
- ファルカトゥス
zone B「メイン館2階 世界の水棲古生物」
- メトリオリンクス
- ショニサウルス
- ペゾシーレン
- ステラーカイギュウ
- フォスフォロサウルス
- ワイマヌ
- インカヤク
- パラエウディプテス
- アクセルロディクティス・ラボカティ
- フォレイア
- メタプラセンチセラス&プテロプゾシア&ニッポニテス
- アノマロカリス
- エーギロカシス
- アサフス&キクロピゲ&ツリモンストラム
- ユーリプテルス
- アクチラムス
- ドロカリス
- ダンクルオステウス
- ユーステノプテロン
- ボスリオレピス
- ケイチョウサウルス&オドントケリス
- フタバサウルス
zone C「身近なエリアとリサーチ館」
- フルービオネクテス
- デスモスチルス&パレオパラドキシア
- ホッカイドルニス&アロデスムス
- クラドセラケ
- プトマカントゥス
zone D「クジラのドーム」
- アンビュロケタス
- バシロサウルス
- ハーペトケタス
zone E「ビーチと入り江」
- アーケロン
- ストゥペンデミス
- モササウルス
- リヴィアタン
ようこそ! バックヤードツアーへ
プロフィール
土屋健
サイエンスライター。オフィス ジオパレオント代表。日本地質学会員、日本古生物学会員、日本文藝家協会員。埼玉県出身。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て、現職。2019年にサイエンスライターとして初めて日本古生物学会貢献賞を受賞。愛犬たちと散歩、愛犬たちとの昼寝が日課。古生物に関わる著作多数。近著に『生命の大進化40億年史 新生代編』(講談社)、『地球生命 無脊椎の興亡史』、『恐竜たちが見ていた世界』(ともに技術評論社)など。動物園で動物を見ると、つい、我が家の犬たちとのちがいを考えてしまう。
ツク之助
サイエンスイラストレーター。古生物の復元画や、爬虫類イラストを描く。イラストを担当した書籍に『ディノペディア』(誠文堂新光社)、『恐竜たちの見ていた世界』(技術評論社)、『恋する化石』(ブックマン社)、『恐竜・古生物ビフォーアフター』(イースト・プレス)。著書に『とかげくんのしっぽ』、『フトアゴちゃんのパーティー』(ともにイースト・プレス)。バンダイの爬虫類カプセルトイシリーズも展開。水族館めぐりが大好きで、日本各地の水族館を、大きなものから小さなものまであちこち巡っています。
伊東隆臣
岩手大学農学部獣医学科卒。大阪ウォーターフロント開発株式会社(現株式会社海遊館)入社。大阪・海遊館の海獣類や魚類、ニフレルの猛獣類の飼育係兼獣医師として従事。地球の表面積の約70%は海であり、ある論文の報告によると海洋に生息している生命の91% が新種だそうです。日本近海だけでも毎年新種が発見されており、水族館でも新種生物の飼育にチャレンジすることがあります。そういう意味では、今回の古生物の飼育方法を検討する機会を頂けたことは、水族館職員冥利に尽きる思いです。
安藤達郎
北海道大学では魚竜、ニュージーランドのオタゴ大学ではペンギン、そして現職の足寄動物化石博物館ではペンギンモドキと海生哺乳類、と「二次的水棲適応」を渡り歩いています。水族館の良くないところは、生きている動物の情報量に圧倒されて、いつまでも見ていても時間が足りないことと、写真やビデオを何枚とっても足りた気がしないことです(そしてあまり見返さない)。はじめて行った水族館は小樽水族館、開館3年目でした。本書が将来的に、バーチャル古生物水族館に発展すると嬉しいです。一日中遊びたいと思います。
栗原憲一
株式会社ジオ・ラボ代表取締役・CEO。北海学園大学非常勤講師。早稲田大学で博士(理学)を取得。三笠市立博物館および北海道博物館にて学芸員として勤務後、株式会社ジオ・ラボを設立。科学的な知識を生かした地域活動の支援を日本各地でおこなっている。水族館の好きな生き物は、やはりオウムガイ。ほとんど動かないし、えさもゆっくりと食べる愛くるしい姿は何時間見ていても飽きないので、水族館ゆるキャラ選手権があればダントツの一位だと信じている。
小西卓哉
アメリカ・シンシナティ大学生物科学科教育准教授。専門は古脊椎動物学。水族館には特別な思い出があります。地元・香川県の屋島の水族館には子供のころよく祖父母に連れられ通い、当時から大きな生物や爬虫類に興味をもっていた私はアマゾン川のピラルクーやワニの展示を見るのを楽しみにしていました。現在は子供を連れてよく水族館を訪れ、サメの泳ぎ方やフォルム、イルカの骨格などについつい見入ってしまい、あとから家族を追いかけることもしばしば。
薗田哲平
福井県立恐竜博物館研究員。茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。手取層群を軸足とした化石カメ類の系統分類や形態進化が専門。いつも水族館で爬虫類コーナーに長居する僕からすると、爬虫類だらけの古生物水族館は1日あっても足りないでしょうね。そして、レストランのメニューやバックヤードツアーもとっても気になります。空想の水族館なのに? 空想だからこそ? 楽しい妄想だけで時間が溶けていきますね。
田中源吾
島根大学卒業後、静岡大学大学院で博士(理学)を取得。日本学術振興会特別研究員、レスター大学研究員、京都大学研究員、群馬県立自然史博物館主任学芸員、海洋研究開発機構研究技術専任スタッフ、熊本大学合津マリンステーション特任准教授、金沢大学国際基幹教育院助教を経て、熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター准教授。幼稚園の頃、父親に連れて行ってもらった足摺海底館が心に残っています。
田中嘉寛
大阪市立自然史博物館・学芸員。北海道大学博物館資料部・研究員、沼田町化石館・特別学芸員、甲南大学・非常勤講師を兼ねる。ニュージーランド、オタゴ大学で初期のイルカの進化を研究し博士号(Ph. D.)を取得。専門は水生哺乳類の進化。最近は、大阪層群初のヒゲクジラを発表し、北海道のヌマタナガスクジラ(沼田町)、タイキケトゥス(大樹町)、フカガワクジラ(深川市)を新属新種として命名した。骨ばかり研究しているので、水族館で「生き物」を見ると癒されます。
冨田武照
1982年生まれ。神奈川県出身。博士(理学)。2011年に東京大学・理学系研究科地球惑星科学専攻・博士課程を修了後、フロリダ州立大学などの研究員を経て、2015年より(一財)沖縄美ら島財団総合研究所・主任研究員。水族館管理部魚類課兼任。ジンベエザメが泳いでいる大水槽を見ながら、ここにダンクルオステウスが泳いでいたらと想像するのが好きです。古代ザメの胎仔を人工子宮装置で育てる……そんな研究をするのもいいかもしれません。
林昭次
岡山理科大学生物地球学部准教授。恐竜をはじめとした脊椎動物の進化と生態について骨内部構造から研究しています。最近では古生物学の研究手法を応用し、水族館・動物園などと協力することで、ペンギンなどを含む野生動物の生態解明にも取り組んでいます。水族館では、多様な生物とその不思議に触れることができるので、とても好きな場所です。
宮田真也
専門は魚類化石の分類学です。大学に入学以降、地質学や古生物学を学んでいます。現在は魚類化石の展示数が日本一?! リアル化石水族館である城西大学大石化石ギャラリーで学芸員をやりつつ地学関係の授業もやっています。幼稚園の頃はサメが好きでしたのでよく水族館に連れて行ってもらっていました。ふと思うと、水族館にいる生き物たちのご先祖様は、古生物水族館で見られるような光景を見ていたのかもしれませんね。