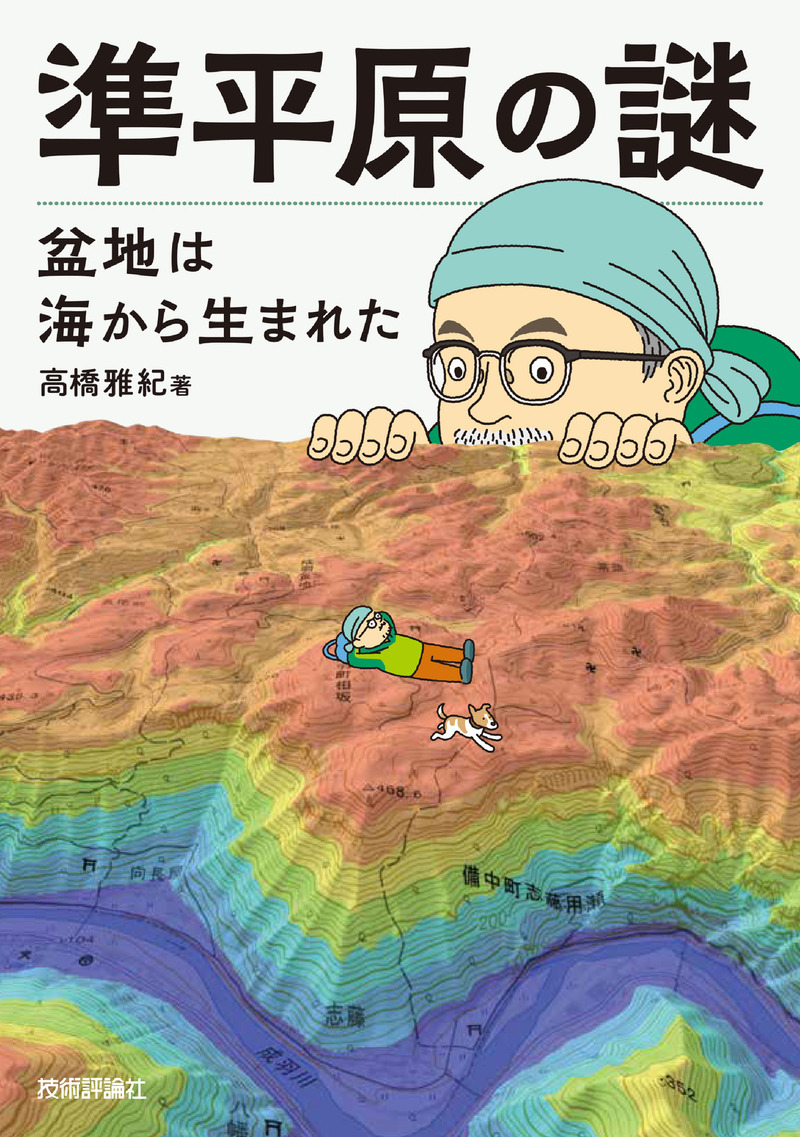準平原の謎 盆地は海から生まれた
- 高橋雅紀 著
- 定価
- 3,740円(本体3,400円+税10%)
- 発売日
- 2024.10.10
- 判型
- A5
- 頁数
- 368ページ
- ISBN
- 978-4-297-14437-1 978-4-297-14438-8
概要
100年間誰も疑わなかった「地形学の常識」に地質学者が挑む、第2弾!!
「準平原」とは、地表が長期にわたる侵食作用を受けて起伏が小さくなり、海面の高さ付近まで低下した、ほとんど平らな地形のこと(国土交通省東北地方整備局HPより)。アメリカの地形学者ウィリアム・モーリス・デービスが100年以上も前に提唱した侵食輪廻説における最末期の地形で、地殻変動(隆起運動)が停止後、河川による侵食によって海面付近まで低くなった起伏の小さいなだらかな平原を指す概念です。重要な点は、「準平原は陸上で河川によってつくられた地形である」と述べていることです。
日本列島には、標高の異なる起伏の小さい侵食小起伏面が知られています。とりわけ、中国地方にはかなりの広がりをもつ明瞭な侵食小起伏面が数段あり、それらはアメリカの地形学者デービスが提唱した「準平原が隆起したもの(隆起準平原)」であるとずっと信じられてきました。ところが、前著『分水嶺の謎 峠は海から生まれた』で考察したように、谷中分水界や片峠は、島と島の間の海峡が離水した地形でした。それらが標高1000mを超す山地にも確認されることから、かつての海峡(海底)が大きく隆起していることを意味します。中国地方の隆起準平原とされた地形を丹念に観察すると、平坦な地形はいずれも起伏の少ない分水界に囲まれていて、分水界には谷中分水界や片峠が確認されます。ということは、谷中分水界や片峠が海峡だったころ、分水界に囲まれている起伏の小さい地形は……浅い海底だったのではないでしょうか。
デービスが提唱した「準平原は陸上で河川によってつくられた地形である」という考え方は、本当に正しいのでしょうか?本書は、100年近く信じられてきた本邦地形学の常識(隆起準平原)を見つめ直し、谷中分水界や片峠を鍵として、その成り立ちの謎について解いていきます。
こんな方にオススメ
- 地形マニア
- 地形の形成過程に関心のある方。Twitterの地形クラスタはターゲットど真ん中
- 登山が好きな方
- 自然の謎解きを疑似体験したい方々
目次
旅の準備
侵食輪廻説と準平原
- 平坦な火砕流台地は堆積面/平らな平野の地形も堆積面/日本列島の侵食小起伏面//侵食小起伏面は隆起した準平原?/準平原は架空の地形/誕生間もない火山は原地形/デービスが描いた侵食輪廻説/侵食輪廻説でみる日本の幼年期地形(下総台地)/侵食輪廻説でみる日本の壮年期地形(房総丘陵)/侵食輪廻説でみる日本の壮年期地形(日高山脈)/侵食輪廻説でみる日本の老年期地形(北上山地)/〝老年期的〟な地形? 〝末期的〟な地形?/侵食輪廻説でみる日本の準平原/侵食地形は地質図で判断/準平原が見つからない/大陸はなぜ大陸?/デービスが見た準平原/ひとたび概念を仮定すると、概念は存在し続ける/日本の準平原問題は、吉備高原から始まった/侵食輪廻説から多輪廻仮説へ/準平原を仮定すると、準平原は存在する/複数段の侵食小起伏面をどう考える?
谷中分水界の成因
- 謎を解く一つ目の〝鍵〟は谷中分水界/スプーンですくったアイスクリーム?/片峠は二つ目の〝鍵〟/芭蕉が歩いて越えた堺田の谷中分水界/堺田の谷中分水界の成因/東北地方で最も低い分水嶺/片峠はちょっと特殊な谷中分水界/二井宿峠の河川争奪説/デービスの考えた河川の争奪/海がつくった片峠(丹生山地)/海がつくった片峠(福江島)/海がつくった片峠(島根半島)/〝二井宿海峡〟の離水/谷中分水界から片峠へ/眼鏡がないと見えないけれど、眼鏡を選ぶとその色しか見えない
第1日 思い出の場所で〝鍵〟のチェック
- 須知盆地で準備体操/低くても、雨水は縁からあふれない/一直線に並ぶ三つ子の谷中分水界/私には見える、かつての海原/〝須知灘〟から〝須知湾〟、そして入り江へ/盆地の底は海底だった
第2日 〝鍵〟を閉じれば背中合わせの盆地
- 縁の高い篠山盆地と縁の低い三田盆地/高い山並みからなる篠山盆地の分水界/分水していない谷中分水界?/団地の境も分水界/西縁が際どい三田盆地の分水界/平らな谷も、雨にとっては盆地の境界/畦倉池は小さな盆地/篠山盆地と三田盆地が海だった頃/先に陸化した篠山盆地/盆地を分けた〝牛ヶ瀬海峡〟の離水
第3日 海が削った吉備高原
- 吉備高原もやはり盆地/吉備高原の成り立ち/吉備高原は瀬戸内海だった/吉備高原は海がつくった/24時間365日、休むことなく侵食し続ける海/吉備高原は灘だった
第4日 海面は海底と陸地の間の関所
- 陸化を拒む海の関所/20年の時を隔てて/石油が採れるための四つの条件/ジオのテーマは石油に絞られた!/地下の褶曲が地形をつくった?/褶曲はお構いなしの侵食面/平らな地形は海がつくった/能代平野は侵食地形/地層は出てから削られる?/出る地層は削られる?/硬い基盤岩も何のその
第5日 水にとってはすべてが盆地
- 吉備高原より一段低い世羅台地/山岳地帯は盆地?/誰が見ても、盆地は盆地/平らな台地もやはり盆地/強調すれば盆地が見える/世羅台地の成り立ち/巨石群は海の記憶?/犯人の足跡が途切れてる/引っ掻き傷は海の痕跡?
第6日 4次元地形学への誘い
- 里芋のようにつながった盆地の宝庫/かつての海峡は交通の要所/ここかしこに海の景色/分水界の三重会合点/遅れてきた〝テクトニクス屋さん〟/雑談の導入はインド亜大陸の衝突から/大陸衝突の超ミニチュア版/気になってしまう三重会合点/2次元の地形図から4次元地形学へ/西条盆地が瀬戸内海だった頃/瀬戸内面は将来の瀬戸内海/出番を待っている盆地の卵
第7日 私が地形に夢中な理由
- 舐めるように地形を観察する理由/科学者の役割/何度でも地形を観察し続ける理由/〝サイエンスの種〟を拾うとき/川か海か、それが問題だ!/尾根の鞍部の礫層の謎/分水嶺を覆う礫層の不思議/山奥の礫層は、本当に河川成?/残された6m/真っ直ぐ進むプレートは回転運動/骨格はできたけれど……/衣装をつくるための生地が足りない/古地理図を描くには覚悟が必要/250万年前の日本列島は陸だった?
第8日 高所に残る海の痕跡
- 〝天空の聖地〟もかつては内湾/標高800mにある背中合わせの盆地/標高900mの〝ミニ吉備高原〟/分水界の月桂冠/ひと休みした〝海の腰掛け〟/2人がけのハイバックチェア/地滑り地形か区別できない/本当にカール?/海で見つけた〝海の腰掛け〟
第9日 川を下ればタイムトラベル
- 海から生まれた盆地/標高500mでも競っている最後の海峡/隆起準平原と紹介されている阿武隈山地/標高600mの盆地/標高1000m超えの侵食小起伏地形/高野山を超える〝天空の聖地〟大台ヶ原/隔離された標高1300m超えの盆地/標高1500m級のなだらかな盆地/出発は水深150mのタイムトラベル/追憶の〝花輪湾〟/かつての内湾は海岸平野、そして内陸盆地へ/平野の先には孵化を待つ日本海の海底
旅のおわりに
- 地質との出会い/秩父盆地との再会/〝炭〟も積もれば……/凹んで持ち上がった秩父盆地/〝炭〟が語る秩父盆地の成り立ち/興奮の卒業研究/40年前の違和感/40年後の視点で見れば/河成段丘? 海成段丘?
感謝
一周遅れの……
プロフィール
高橋雅紀
1962年、群馬県前橋市生まれ。1990年に東北大学大学院理学研究科博士課程を修了後、日本学術振興会特別研究員および科学技術特別研究員を経たのち、1992年に通商産業省(現経済産業省)工業技術院地質調査所(現産総研)に入所。専門は地質学、テクトニクス、層序学。大学の卒業研究以来、関東地方の地質を調べ日本列島の成り立ちを研究。NHKスペシャル『列島誕生ジオ・ジャパン』や『ジオ・ジャパン絶景100の旅』のほか、NHK番組『ブラタモリ』秩父、長瀞、下関、日本の岩石SP、つくば、東京湾、前橋、世界の絶景SP、行田、長岡に出演。著書に『分水嶺の謎 峠は海から生まれた』(技術評論社)や『日本地方地質誌3 関東地方』(朝倉書店、分担)のほか、『日本海の拡大と伊豆弧の衝突-神奈川の大地の生い立ち-』(有隣堂、分担)や『トコトンやさしい地質の本』(B&Tブックス日刊工業新聞社、分担)など。好きな言葉は「放牧、放任、放し飼い」、座右の銘は「退路を断たないと、つぎの扉は開かない」。いつも心がけている自身の矜持は「初代で一代限り」。