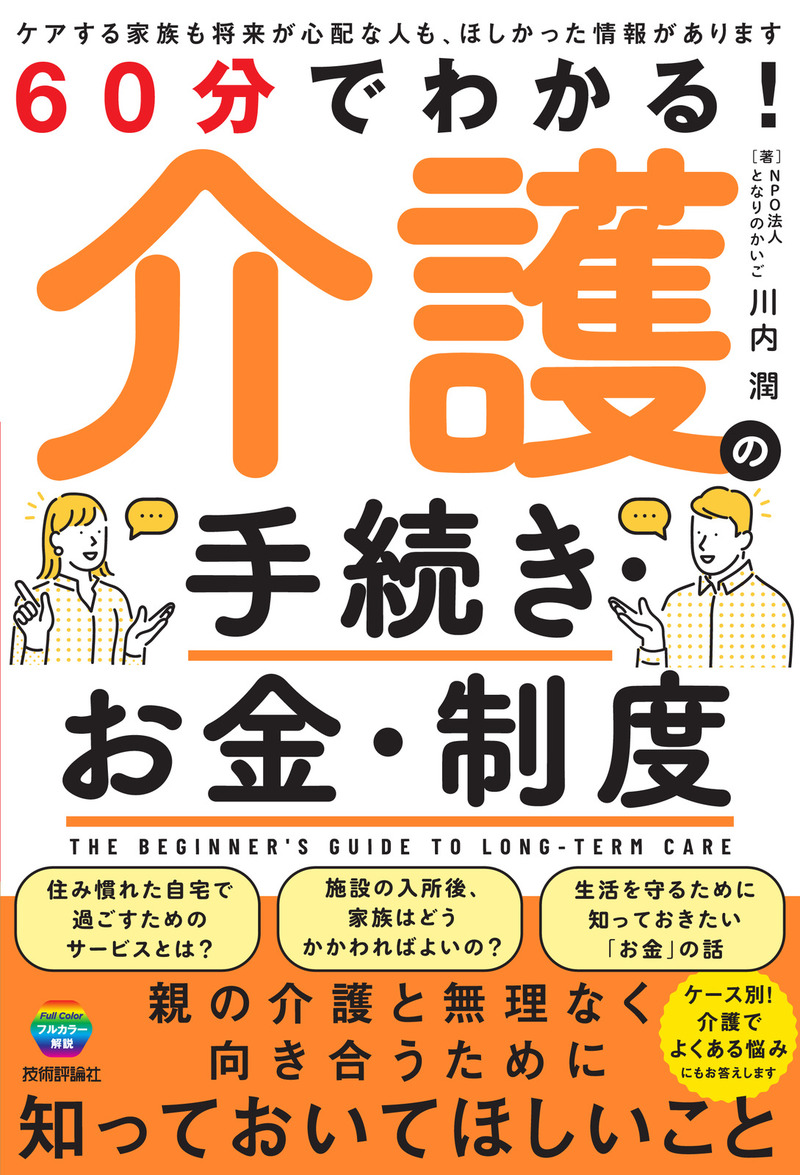60分でわかる!
60分でわかる!
介護の手続き・お金・制度
- 川内潤 著
- 定価
- 1,430円(本体1,300円+税10%)
- 発売日
- 2025.10.21
- 判型
- 四六
- 頁数
- 160ページ
- ISBN
- 978-4-297-15148-5 978-4-297-15149-2
サポート情報
概要
<コンセプト>親の介護と無理なく向き合うために、知っておいてほしいこと
「いつまでも親は元気」とつい思い込んでしまいますが、介護が必要な状況はゆっくりと、時には突然、訪れます。焦らず、少しでも早く介護のプロの手を借りるための手続きやお金のことなど、ケアする家族が知っておきたい情報をコンパクトなサイズにまとめました。介護保険制度のきほん的な知識である、サービスの紹介や利用料金ばかりでなく、家族関係を壊さないための介護との向き合い方、ケアする家族の生活を守るための情報も盛り込みました。認知症のことや、離れて暮らす親の日常生活を支援する「介護保険外のサービスや制度」についても紹介します。育児と介護のダブルケアや親族とのかかわり、親の免許返納に関するアドバイスなど、ケース別で“よくある家族の悩み”にもお答えします。
こんな方にオススメ
- 「まだ元気だと思っていた親が急に倒れた」「老親が日常生活を送るのが困難になった」という状況に陥った家族(50代を中心とする子の世帯)
- パートナーを亡くしてふさぎ込んでいる老親を支えたい家族(要支援認定を目指している人)
- 前者のような環境に陥っているが情報にアクセスできない人をサポートしたい人
目次
[巻頭]
- 介護には4つのフェーズがある
- 介護保険サービス利用までの流れ
Part1 親の介護と無理なく向き合うために
介護が始まる前に知っておいてほしいこと
- 001 介護を家族だけで抱え込んではいけない
- 002 介護はいつから始まる?
- 003 介護が始まる前に備えておけること
- 004 地域包括支援センターで相談できること
- 005 親に認知症の疑いがある場合の向き合い方
- 006 親が突然倒れ、入院することになったら
- Column 家族介護者の悩みや愚痴を相談できる場所
Part2 介護サービス利用の第一歩
介護保険の基本と仕組み
- 007 介護保険とはどういう制度なのか
- 008 介護保険はだれが利用できる?
- 009 介護保険で受けられるサービスは?
- 010 介護保険サービスにかかる費用
- 011 介護サービスを提供する指定事業者とは
- 012 介護保険サービスにかかわるスタッフにはどんな人がいる?
- Column 介護職員の負担を減らす、かかわり方の工夫とは?
Part3 要介護認定からサービス契約まで
介護保険を利用するための手続き
- 013 介護保険サービスを利用するには
- 014 訪問調査ではどのようなことを聞かれるのか
- 015 主治医意見書とは?
- 016 「要介護」と「要支援」はどう違う?
- 017 要支援・要介護認定の結果に納得できない場合は?
- 018 ケアマネジャーを選ぶポイント
- 019 介護サービスの利用計画「ケアプラン」を作成してもらう
- 020 介護にかかわるメンバーが集まるサービス担当者会議
- 021 サービス事業者と契約するときの注意点
- 022 要支援の場合に受けられるサービスは?
- 023 サービスへの苦情や相談はどこにすればいい?
- Column 家族が介護サービスを受けるのをいやがる場合
Part4 住み慣れた自宅で暮らすために
在宅介護で利用できる介護保険サービス
- 024 離れて暮らしていても在宅介護はできる
- 025 訪問介護員による日常的ケアを受ける「訪問介護(ホームヘルプ)」
- 026 訪問介護で依頼できないことは?
- 027 自宅で入浴するためのサービス「訪問入浴介護」
- 028 自宅で受けられる医療サービス「訪問看護」
- 029 自宅でリハビリができる「訪問リハビリテーション」
- 030 通院困難な人の自宅で療養指導を行う「居宅療養管理指導」
- 031 日帰りで介護サービスを受ける「通所介護(デイサービス)」
- 032 日帰りでリハビリを行う「通所リハビリテーション(デイケア)」
- 033 自立した生活を支援するための道具「福祉用具」
- 034 自宅で安心して暮らせるように行う「住宅改修」
- 035 24 時間体制でサポート「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
- 036 夜間の自宅での生活をサポートする「夜間対応型訪問介護」
- 037 介護施設で短期間サービスを受ける「短期入所生活介護」
- 038 医療施設で短期間サービスを受ける「短期入所療養介護」
- 039 通い・訪問・宿泊を1か所で受けられる「小規模多機能型居宅介護」
- 040 医療・介護サービスを1か所で受けられる「看護小規模多機能型居宅介護」
- 041 知っておきたい介護保険外のサービス
- 042 在宅介護に役立つ最新テクノロジー
- Column 家族介護にテレワークを活用する際の注意点
Part5 安全な環境で介護を受けながら暮らす
介護保険施設と高齢者向けの住まい
- 043 施設入所を検討するタイミングはいつがよい?
- 044 施設の探し方のポイント
- 045 施設の選び方のポイント
- 046 要介護3から入所できる「特別養護老人ホーム(特養)」
- 047 在宅復帰を目指してリハビリを行う「介護老人保健施設(老健)」
- 048 医療と介護が必要な人のための施設「介護医療院」
- 049 認知症の人のための入居施設「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
- 050 低コストで入所できる「軽費老人ホーム(ケアハウス)」
- 051 サービスや環境の選択肢が多い「有料老人ホーム」
- 052 高齢者向けの賃貸住宅「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」
- 053 施設入所後、家族はどうかかわればよい?
- Column 夫婦で同じ施設に入居する際の注意点
Part6 親と自分の生活を守るために知っておきたい
介護にまつわるお金と制度
- 054 介護サービス費以外にも必要な費用がある
- 055 介護費用はどこから出す?
- 056 医療費・介護サービス費の自己負担を減らす制度
- 057 住民税非課税世帯なら、施設の食費や居住費の負担が軽くなる
- 058 介護サービス費の一部も医療費控除できる
- 059 日常的な金銭管理をサポート「日常生活自立支援事業」
- 060 認知症の人のお金と権利を守る「成年後見制度」
- 061 将来に備えて資産の管理・処分を家族に託す「家族信託」
- 062 仕事と介護を両立するための制度「介護休暇・介護休業」
- Column 民間の介護保険に入っておいたほうがよい?
Part7 ケース別で介護の問題を解決する
介護にまつわるよくある悩み
- 063 親せきに「離れて暮らす親の面倒を見ろ」と言われたら?
- 064 父親を介護する高齢の母親 どうすればよい?
- 065 認知症の疑いのある親に免許を返納させるには?
- 066 親の介護をしていることを会社に言いにくいときは?
- 067 介護をしている家族が虐待しているかもしれないと気づいたら?
- 068 きょうだい間での介護トラブルを防ぐには?
- 069 介護と育児の時期が重なってしまったらどうしたらよい?
- 070 離れて暮らす高齢の親の防災はどうしたらよい?
- 071 看取り期を迎える家族が大切にしたいことは?
プロフィール
川内潤
1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員を経て、2008年に市民団体「となりのかいご」設立。2014年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。厚労省「令和2年度仕事と介護の両立支援カリキュラム事業」委員、育児・介護休業法改正では国会に参考人として出席。