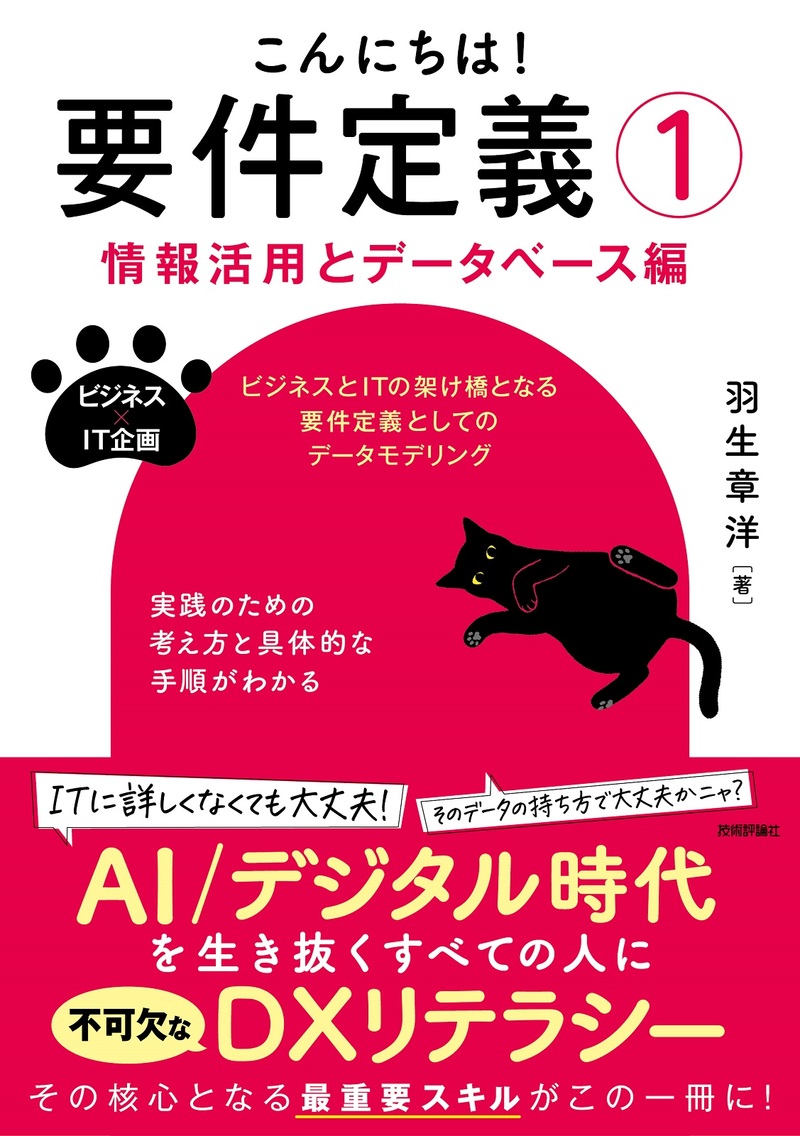ビジネス ✕ IT企画
こんにちは! 要件定義①【情報活用とデータベース編】
- 羽生章洋 著
- 定価
- 2,970円(本体2,700円+税10%)
- 発売日
- 2025.10.21
- 判型
- A5
- 頁数
- 392ページ
- ISBN
- 978-4-297-15237-6 978-4-297-15238-3
サポート情報
概要
「ITを活用できる人材」が求められています。私たちの仕事のすべてにおいて「情報」が関わっているといっても過言ではありませんが、ITは「情報を活用するための文明の利器」と言えます。情報は物理的な存在ではないため、扱うのが難しく、手間もかかります。それゆえ、ITという文明の利器によって、情報をしっかり記録し、その記録を縦横無尽に活用して、仕事をもっとスムースに行いたいのです。そしてそのための基盤・土台となるのがデータベースです。
そうした社会的要請、企業活動の根本的ニーズでもあるIT活用、さらにはデジタル時代の情報活用の土台としてデータベースを活用し、データベースに保管するためには、データの要件を定義するデータモデリングを行います。
本書では、IT、そして情報をどのように捉えればよいのか解説したうえで、データモデリングの手順をわかりやすく解説します。
STEP 1 IT 活用対象の仕事を決める
STEP 2 必要な情報を定義する
STEP 3 情報の中身=データ構造を定義する
STEP 4 情報のやり取り方法(API)を定義する
STEP 5 裏方のアクションの中身を考える
STEP 6 必要なデータがデータベースに保存されているか確認する
STEP 7 データ構造を正規化(整理)する
STEP 8 ERD(ER 図)を描く
実務でよく見かける場面を取り上げたサンプル集も収録しました。
「ビジネス × IT企画」シリーズ」第1弾として、ITを活用し、DX企画ができるようになるために必要な要件定義について、「情報活用とデータベース」にフォーカスしてお届けします。
こんな方にオススメ
- 業務のIT化/DXの推進に携わる非IT職能の方
- IT業界を目指す学生や、IT業界に入った新入社員の方
- 初級〜中級のITエンジニア全般
目次
第1章 仕事と情報とIT
- もっとITを活用したい!
- ITとは何か?
- 情報とは何か?
- 情報に囲まれた日常生活
- 情報がなくなるとどうなる?
- なぜ情報が必要になるのか
- 情報とは、残したいこと
- 情報を扱うためのテクノロジー
- 忘却との戦い
- 紙とデジタル
- コンピュータの登場
- 日常生活と仕事
- 仕事とは何か
- 仕事とは──活動と成果
- 仕事とは──インプット・活動・アウトプット
- 仕事の本質──変換、状態の変化
- プロセス
- 仕事を行うタイミング
- 他からのリクエストがあったとき
- ある条件を満たしたことを検知したとき
- ストア(保管)の重要性
- ストアをめぐる問題
- 仕事と情報
- 喫茶店の事例
- 仕事における情報とは
- 情報は事実の後追い
- 仕事における情報を扱うためのIT
- UI ──人とデジタルの接面
- ITを活用する目的
第2章 必要な情報を定義する
- そもそも情報とは何か?
- 情報の定義
- データとは
- データ構造
- データ構造とインスタンス
- データ構造=ひな形
- インスタンスとは
- 仕事に必要な情報を考える
- 要件を定義する
- 小さいレストランの仕事の流れ
- インプットから始める
- 情報屋さんとしてのITくんの仕事を考える
- 情報屋さんとしてのITくんの立場で考える
- 必要な情報を集めて名前をつける
- 情報を構成するデータ構造を考える
- データ構造名を考える
- データモデリングを行う
- 項目名の重要性
- 繰り返し項目の明示
- 窓口と裏方に分けて考える
- ゲット系の情報とプット系の情報
- APIの利点
- ゲット系のAPIとプット系のAPI
第3章 情報をつくる処理を考える
- データベースを扱うという仕事
- アウトプットのための処理を考える
- パターン1:そのままコピペする
- パターン2:計算する
- パターン3:変換する
- 絞り込む
- 集計する
- 並べ替える
- アウトプットする項目に値を設定する
- 保存系のアクション
- 取得系に必要なデータを正しく保存する
- データ構造を正規化する
- 正規化の必要性
- 人間は面倒くさがり
- データ(構造)を整理整頓しよう
- 1つの事実は1つの場所に
- エンティティを設定する
- エンティティ
- データ構造とエンティティの関係
- エンティティの定義=データ構造の定義
- 1つの項目には1つの値のみ
- @で繰り返しを表す
- 共通のデータを切り出して1つのエンティティにまとめる
- 明細部分を切り出して別のエンティティにする
- リレーションシップ(関係/関連)
- 削除する
- 更新する
- 複数のエンティティを同時に扱う
- ジョイン(結合)
- トランザクション(一括処理)
第4章 実務に沿ったデータモデルを考える
- 現実をエンティティに写し取る
- データモデリングの手順を再確認する
- データモデリング手順のポイント
- レストランの業務で実践してみる
- 知りたい情報の定義とAPI設計
- データの流れ(データフロー)とプット系API
- さらに記録が必要になったとき
- 情報の名前づけ
- エンティティの統合
- 存在系と活動系
- 「注文」データモデルに見る存在系と活動系
- 存在系と活動系の見分け方
- 「概念系」の導入
- 「状態」という概念
- 区分による状態管理
- 「区分」で見分けるのではなく、別々のエンティティと捉える
- 状態系エンティティの捉え方
- 「残」という概念
- 残系をエンティティとして扱う
- 仕事どうしの紐づけ
- 紐づけを管理する交差エンティティ
- 複雑な仕事への柔軟な対応
- 活動系は交差エンティティか?
- その他の交差エンティティの例
- 対応づけとしての「構成」
- 親子関係と同一エンティティ内のリレーションシップ
- 部品表
- 複雑な分類の構造を考える
- 分類も親子関係として扱う
- 交差と交差が交差すると?
- 交差エンティティの発展形
- プロセス系エンティティ
- ビジネスのデジタル化とデジタルツイン
第5章 エンティティの項目を考える
- 項目とは何か
- 項目名の決め方
- 定量化と単位の重要性
- 項目を分割する際の注意点
- 項目名に持たせる意味を統一する
- 「備考」という項目名をどう扱うか
- エリアス・ホモニム・シノニムの問題
- IT活用を成功させる項目名定義
- 入れてもよい値を制限する
- 値の制限とバリデーションルール
- データ型の設定
- 項目が持つデータ型は1つだけ
- 値の制約と列挙型
- 外部参照制約
- 値の決まり方を考える
- 導出項目と導出ルール
- 導出ルールの設定手順
- ビジネス要件による導出ルールの複雑化
- 初期値、デフォルト値
- リクエストパラメータにまつわる項目
- 表示にまつわる項目
- 並び順の管理
- 並び順を決めるのは「人間の仕事」
- 表示/非表示を切り替える
- 論理削除
- 値が定まらない場合
- NULL値とは何か
- NULL値の使用をめぐる論争
- NULL値を避ける弊害
- 「事実がない」という事実の記録
- NULL値による「事実がない」ことの表現
- 部分と一括と数
- 部分対応と一括対応:注文と出荷の例
- 数量(個数)という概念の再考
- 本質的な事実を捉える
第6章 キーとID
- キーとは何か
- キー(候補キー)の決め方
- プライマリーキー、セカンダリーキー
- ユニークキーと重複キー
- キーの定義=制約
- 複合キー
- 「事実の存在そのもの」を表現するためのID
- IDとキーの違い
- 事実、記録、キーのライフサイクル
- IDを識別の手がかりとする
- キーの値は人間が決める
- IDの値の決め方
- IDとキーは併存できるか
- 本章のまとめ
第7章 サンプル集
- 本章のはじめに
- 異なるコード体系を紐づけて統一的に扱う
- 商品とオプションの対応関係
- 有効期間と事前登録
- 区分と種別
- 契約エンティティ
- 所属エンティティ
- 履歴やバージョン管理の扱い
- 階層構造と親子関係
- 状態の遷移
- 状態の表現
- 期間とNULLの扱い
- 未登録あるいは事後登録の扱い
- 残系エンティティ:在庫と残高
- 横持ちデータ
第8章 まとめ
- データモデリング手順のまとめ
- STEP 1 IT活用対象の仕事を決める
- STEP 2 必要な情報を定義する
- STEP 3 情報の中身=データ構造を定義する
- STEP 4 情報のやり取り方法(API)を定義する
- STEP 5 裏方の活動(アクション)の中身を考える
- STEP 6 必要なデータがデータベースに保存されているか
- 確認する
- STEP 7 データ構造を正規化(整理)する
- STEP 8 ERD(ER図)を描く
- エンティティの分類
- 基本的なエンティティの分類
- エンティティ同士の紐づけとしての交差エンティティ
- エンティティの項目
- 項目の設計視点:6W3H
- 意味のブレ防止
- データ型と制約(バリデーション)
- キーとID
- キーの定義と目的
- IDの本質(キーとの違い)
- 「こんにちは!」の日々の証に
コラム
- スキーマ
- 混ぜるな項目名!
- 繰り返しを表す「@」について
- 情報伝達とデータベースの関係
- インターフェイスという考え方
- SQLを使う:SELECT文
- INSERT文
- ID項目の命名規則
- データモデルの表記法について
- エンティティとテーブルの話
- テーブルと表計算ソフト
- データのライフサイクルを考える
- DELETE文
- UPDATE文
- 更新禁止?
- 実際には削除していない?
- JOIN ... ON
- RDB以外のデータベース
- SQLノススメ
- 存在系/活動系とリソース系/イベント系
- 「在庫」は最大級のグローバル変数
- リレーションシップとは何か?
- 「関係というインスタンス」のライフサイクル
- 本書の例における顧客マスターのこと
- 交差エンティティをマトリックスで表現すると
- プロセス系エンティティの名前づけ
- ロングトランザクション
- プロセス系エンティティと状態管理
- 汎用的なリファレンスモデルとしての飲食業
- 事業/業務の複雑さはエンティティ数とリレーションシップに現れる
- ビジネスや業務のすべてをデータモデルだけで表せるわけではない
- 定量化ということ
- 人間は面倒くさがり
- 項目名をエンティティ名で修飾するかどうか問題
- ブール値とブール型
- 可変長と固定長
- COBOLが根強い理由
- 「数値のみ」という想定の落とし穴
- すべてを文字列型にする?
- 制約ルールの明記とモデリング
- 導出ルールのドキュメント化とデータモデル
- 導出項目は排除すべきか
- 「率」という導出項目
- 入力支援について
- 論理削除についての私見
- マイクロトランザクション
- GROUP BYで考えると
- UIで入力した数量分だけインスタンスを作る作戦
- ビッグデータは細かい?
- キーの本性
- アスタリスクとインスタンス
- IDとCREATE TABLE文のPK制約
- サロゲートキーの話
- IDは必ず列として持つ!
- データ構造を疎結合に保つ
- 「いつ」「誰が」「どのように」コード体系を決めるのか
プロフィール
羽生章洋
著者。エークリッパー・インク代表 1968年6月1日生まれ、大阪育ち。1989年、桃山学院大学社会学部社会学科を中退後、2つのソフトウェア会社にてさまざまな業種・業態向けシステム開発を経て、アーサーアンダーセン・ビジネスコンサルティング(当時)に所属。その後、トレイダーズ証券株式会社(当時)とマネースクウェアジャパン株式会社(当時)の新規創業に参画、両社にて当時としては先進的なリッチクライアントとOSSによるオンライントレーディングシステムを実現。2006年から2011 年まで、国立大学法人琉球大学の非常勤講師。現在は、企業向けにデジタル人材育成を中心に活動、現場主導による問題解決の企画立案や業務とITの架け橋としての要件定義などの支援などを行っている。
カード式業務モデリング図法「マジカ」やアプリケーション要件モデリング図法「IFDAM」の作者。著書に『はじめよう! 要件定義』、『はじめよう! プロセス設計』、『はじめよう! システム設計』、『ビジネスデザイン』、『すらすらと手が動くようになるSQL書き方ドリル』(以上、技術評論社刊)、『楽々ERDレッスン』(翔泳社刊)、『いきいきする仕事とやる気のつくり方』(ソフト・リサーチ・センター刊)など。
可世木恭子
本文イラスト担当。法政大学経済学部卒。複数のソフトウェア会社でプログラマを経てエークリッパー・インクに参画。業務のイラスト化を中心に活動中。イラストに『はじめよう! 要件定義』、『はじめよう! プロセス設計』、『はじめよう! システム設計』、『ビジネスデザイン』(以上、技術評論社刊)、『原爆先生がやってきた!』(産学社刊)など。著書に『サーバサイドプログラミング 基礎』(共著、技術評論社刊)がある。