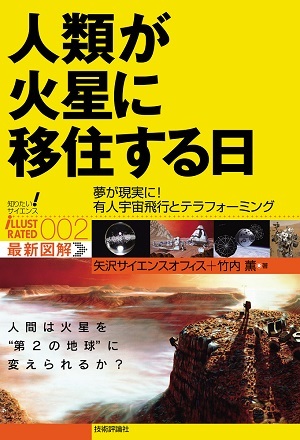知りたい!サイエンス イラストレーテッド
人類が火星に移住する日
--夢が現実に!有人宇宙飛行とテラフォーミング--
- 矢沢サイエンスオフィス,竹内薫 著
- 定価
- 2,178円(本体1,980円+税10%)
- 発売日
- 2015.5.21
- 判型
- 四六
- 頁数
- 288ページ
- ISBN
- 978-4-7741-7315-3 978-4-7741-7415-0
サポート情報
概要
火星に着陸して活躍し続ける探査機キュリオシティ。それから送られる画像は地球の砂漠のようだ。どんどん進む調査につれ、火星に生命の痕跡があったとしても、もはや不思議ではない。本書は、キュリオシティから送られる写真やデータを紹介し、分かってきた火星の様子や基本情報をビュアルで解説する。また今後検討が本格化する、火星の有効利用について、深く掘り下げる。火星改造やテラフォーミングはもはやSFではない。そんな火星への科学の挑戦やロマンを浮き彫りにする。
こんな方にオススメ
- 宇宙開発に興味のある方
- 天文に興味のある方
目次
巻頭・火星最新報告
- 探査機キュリオシティーの火星探査活動
- 人類が火星に到達する日
- 竹内薫のPoint of View.1
- そもそもなぜ宇宙探査をするのか?
第1部 火星有人飛行の計画と課題
パート1 火星はどんな惑星か
- 1.もっとも新しい火星接近マップ
- 2.火星生命の存在の可能性
- 3.南極で見つかった火星の隕石
- 竹内薫のPoint of View.2
- 火星は誰のものか…宇宙法のお話
パート2 宇宙輸送システム
- 1.化学ロケットで火星有人飛行は可能か?
- 2.火星に向かう“宇宙の道”
- 3.2018年に飛び立つ巨大ロケット「SLS」
- 竹内薫のPoint of View.3
- 火星への旅はヒッチハイクで?
- 竹内薫のPoint of View.4
- 誰が火星への第一歩を記すのか?
- …アポロ11号を振り返る
- 4.火星に“39日”で到達するヴァシミールロケット
- 5.宇宙推進の主役となる原子力ロケットの開発
- 6.文明の未来と核融合ロケット
- 竹内薫のPoint of View.5
- なぜ人類は冒険したがるのか?
パート3 人間は火星環境にどこまで適応できるか
- 1.火星有人飛行と宇宙放射線被曝
- 2.宇宙放射線被曝を最小化する画期的な方法
- 3.無重力環境下での長期生活
- 4.無重力空間で植物は育つか
- 竹内薫のPoint of View.6
- JAXAってどんなところ?
第2部 火星テラフォーミングと“第2の地球”
パート4 火星テラフォーミングへのプロローグ
- 1.生命の存在を許すハビタブルゾーン
- 2.始まりは金星テラフォーミング
- 3.カール・セーガンの火星の「長い冬モデル」
- 竹内薫のPoint of View.7
- 火星人の進化
パート5 火星の“修復”計画
- 1.人類はなぜ火星をテラフォーミングするのか?
- 2.火星を温暖化させる3つの手法
パート6 惑星工学で実現する急速テラフォーミング
- 1.50年で火星を“第2の地球”にする
- 2.“急速テラフォーミング”の3要件
- 3.火星のレゴリスを気化させて大気をつくる
- 4.レゴリスが融けた火星
- 竹内薫のPoint of View.8
- 星ではゴミを出さないようにしよう
- …宇宙のゴミのお話
パート7 人類の火星改造の能力
- 1.地球環境から類推する火星テラフォーミング
- 2.人類が操作する物質とエネルギーのスケール
- 3.火星に“暴走温室効果”を生み出す2つの手法
- 4.非現実から現実的なシナリオへ
- 竹内薫のPoint of View.9
- 火星に行く方法
- …宇宙エレベーターのお話
パート8 パラテラフォーミングと「ワールドハウス」
- 1.すぐに居住可能になるパラテラフォーミング
- 2.ワールドハウスのつくり方
プロフィール
矢沢潔
矢沢サイエンスオフィス。
科学雑誌編集長などを経て1982年より科学情報グループ矢沢サイエンスオフィス(㈱矢沢事務所)代表。内外の科学者・研究者、科学ジャーナリスト、編集者などをネットワーク化し30年あまりにわたり自然科学、医学(人間と動物)、核エネルギー、経済学、科学哲学などに関する情報執筆活動を続ける。物理学者ロジャー・ペンローズ、アポロ計画当時のNASA長官トーマス・ペイン、SF作家ロバート・フォワードなど海外著名人を講演のため日本に招いたり、「テラフォーミング研究会」を主宰して「テラフォーミング・レポート」を発行したことも。編著書100冊前後(記憶不確か)。本書では全体の構成のほか主要記事を執筆した。
金子隆一
矢沢サイエンスオフィス。
生物学・進化論・古生物学・天文学・物理学・医学など科学全般にくわしく、一般向け科学出版物、テレビなどで活躍。北米、ヨーロッパ、中国、南アフリカなどを頻繁に現地取材。著書(含共著)に『図解クローン・テクノロジー』(同文書院)、『哺乳類型爬虫類』(朝日新聞社)、『軌道エレベーター・宇宙へ架ける橋』(早川書房、文庫版)、『大量絶滅がもたらす進化』(ソフトバンククリエイティブ)、『アナザー人類興亡史』(技術評論社)など数十冊。2013年死去。
新海裕美子
矢沢サイエンスオフィス。
東北大学大学院理学研究科(放射化学)修了。1990年より矢沢サイエンスオフィス・スタッフ。科学の全分野とりわけ医学関連の調査・執筆・翻訳のほか各記事の科学的誤謬をチェック。近著(共著)に『正しく知る放射能』『よくわかる再生可能エネルギー』『放射線・放射能の問題』(学研マーケティング)、『薬は体に何をするか』『ノーベル賞の科学』(技術評論社)、『始まりの科学』(ソフトバンククリエイティブ)、『これ一冊でiPS細胞のすべてがわかる』(青春出版社)など。
竹内薫
1960年東京生まれ。サイエンス作家。東京大学教養学部教養学科(科学史科学哲学)、理学部物理学科卒。マギル大学大学院博士課程修了(高エネルギー物理学専攻)。科学書の執筆のほか、日本で唯一の本格科学番組「サイエンスZERO」(NHK Eテレ)の司会、「ひるおび!」(TBS系)のコメンテーターなど、お茶の間にも科学の楽しさを発信。近著に『屋根から猫が降ってくる確率』(実業之日本社)、『素数はなぜ人を惹きつけるのか』(朝日新書)など多数がある。