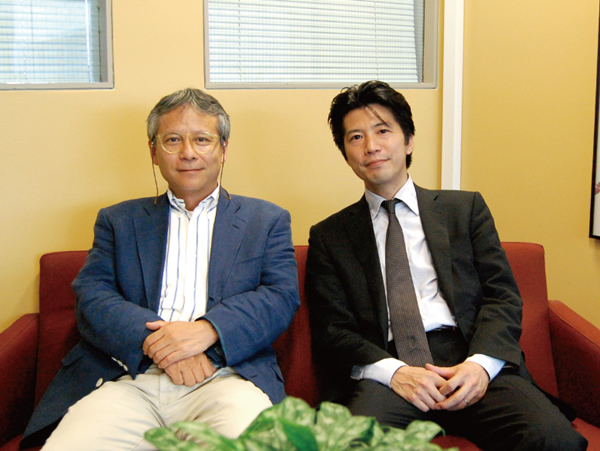毎回、さまざまな分野の方をゲストに迎え『関心空間』代表取締役 前田邦宏氏との対談をお届けする『Web Site Expert Academia』 。
今回の対談場所は、なんとアメリカ! マサチューセッツ工科大学メディアラボ教授 石井 裕氏との対談を、いつもよりもボリュームを増してお届けします。
右:関心空間代表取締役 前田邦宏氏(撮影:土屋一樹)
MITメディアラボ
前田:
個人的な話なのですが、13年前、知り合いを訪ねてここに来たことがあります。私自身、Stewart Brandが書いた『メディアラボ[1] 』を読んで「ここに行けるんだ」と思い、興奮した記憶があります。'95年の1月ごろで、まだ私自身もWebには詳しくはなかったものの、同時に強い可能性を感じていました。そこで、「 Webがこれからおもしろくなっていくけど、みんなどんな風に接しているの?」「 Webについての良い本はないの?」などと質問したところ、「 WebのことはWebに聞くのが一番だよ」とあっさり言われ、愕然としました。13年前にここで触れた、そういったWebのカルチャーというものが起点になって、この仕事にのめり込むようになったのです。
石井:
なるほど、ここへの訪問が今の仕事のきっかけになった、と。
前田:
そうですね、当時はメディアラボとATG ( Art Technology Group, Inc.)というMITの卒業生が中心になって作った会社に往訪しました。ATGではOXYGENというコミュニケーションツールを作っていました。当時PPPで接続していた私に比べ、今のSkypeやTwitterを使うようにWebを活用してコミュニケーションをとりながら仕事をしている彼らの姿を見て、カルチャーショックを受けました。
当時からすでに、メディアラボには“ Inventing a better future” というコンセプトはあったと思います。そもそも、メディアラボはどのような目的をもって設立された研究所なのでしょうか?
石井:
メディアラボは、基本的に、未来について研究するところと言えます。アラン・ケイの言葉である“ The best way to predict the future is to invent it.” ~未来を予言する最良の方法は、未来を創造することである~をよく引用しますが、天気予報やマーケティングのように観察から予測するのではなく、夢に描いた未来を実際にプロトタイビングとして形にし、それを他の人にも体験してもらい、選びとってもらうこと。つまり、当たるか当たらないかではなく、自分たちで創りだし、人々に納得してもらうとともにイメージをふくらませてもらい、未来への流れを創りだすこと。それがメディアラボの基本的なスタンスです。
逆に言うと、すでにメインストリームになってしまったものは追わない、そういう研究所です。
前田:
所属する学生にそのようなマインドを持ってもらうために、最初はどのようなメッセージを送るのでしょうか? そして、どのように導いていくのでしょうか?
石井:
幸い、メディアラボには世界中から優秀な学生が願書を送ってくれます。そして創造性を発揮できる学生かどうかは、ポートフォリオを見れば自明です。面接でも、3分も話せばどのようなクリエイティビティを持っているのかはだいたいわかります。
そういう意味で、ここに来てから方法を教えるのではなく、はじめからそういう資質を持った人を選ぶようにつとめています。
Things That Think, Tangible Bits
前田:
具体的に、石井先生の作品のコンセプトであるTangible Bitsや、Things That Thinkについてお話しいただけますか。
石井:
未来を映し出すビジョンは時代とともに変わってきます。'70年代にはNegroponteが提唱した、デジタルコンバージェンスと呼ばれるビジョンがありました。このビジョンに対する次のパラダイムとして、Things That Thinkというメディアラボの新しいコンソーシアム活動が'95年ころから開始しました。
デジタルコンバージェンスとは、「 通信・出版・計算技術といったバラバラだった業界が、デジタルというテクノロジーをベースにインテグレートされていくだろう」という予見でした。それによって消えていく大陸もあるし、新しく現れる大陸もあるというような、いわば産業界のプレートテクトニクスとも言うべきパラダイムシフトが起こるだろうということを'70年代に予見し、そのビジョンをもとに'80年代にMITにメディアラボが開設されました。'90年代には、そのようなビジョンが実際に起こるところを私たちは見てきたわけです。
そのころのNegroponteの著書『Being Digital[2] 』に代表されるように、「 デジタルはすばらしい」という大きな流れがありました。しかし、それに対する揺り戻しとして、私たちが生きている空間や身体、つまりアナログでフィジカルな空間に対してデジタルへのトンネルが通じているような状況を設定したことが、私の研究 “ Tangible Bits” のスタートになっています。
デジタルなビットと、アナログなアトムの融合が次のテーマになるだろう、ということで、Things That Think、一般的な言葉で言うと、“ ユビキタスコンピューティング” を考え始めました。Tangible Bitsというコンセプトは、さらに、ヒューマン・コンピュータ・インタラクションの立場から、ビットとアトムの世界の融合を目指して始めたプロジェクトです。
前田:
コンセプトはとてもわかりやすいのですが、日常生活に入ってきた際にどのような変化があるのか、ちょっとわかりにくいところもあります。具体的にはどのような変化を狙った研究なのでしょうか。
石井:
現在、ビジネスとしてのWebは盛り上がっていて、振り子はそちら側に大きく振れていることが、私たちの研究にとってはチャンスとなります。現在のWeb上で実現しやすいビジネスは、私たちの「アトム」というコンセプトから離れたところで、コストが安くスケーラビリティはあるものの、変わったハードウエアやメカトロニクスとは無縁になってしまっている、そんな状況であると言えます。メインストリームを追うのではなく、その次に来てほしい波を創りだすことが、私達の研究テーマです。
そして、この研究がつながる先ですが、私たちのメッセージをどう発展させる人が出てくるのかにかかっていると言えます。
ContextとAffectを理解する
前田:
Things That Thinkについての短い説明をメディアラボのWebサイトで読んだときに、「 u nderstanding of context and affect」という言葉が気になりました。このContext(文脈)とAffect(情動)を理解することをプログラミングするうえで、どのようなアプローチをとっているのかが気になったのですが。
石井:
Contextは非常にオープンな概念ですから、ソフトウエア的に、またセンシング的にどのようにやるかというアプローチはたくさんあるでしょう。今どこにいるのかという位置情報もそうでしょう。また声のトーンにしても、100名ほどの講堂でのレクチャーであればもっとフォーマルになると思いますし、小さな部屋でのディスカッションではもっとピンポンのようなやり取りになるでしょう。この対談のような形では、それらよりはパーソナルな会話ですが、今日初めてお会いするわけですし、この2人の距離もありますので、ある程度はフォーマルな形になります。
そういった調子をシグナルプロセッサからピックアップするとか、オプティカルプロセッサからさまざまな空間配置だとか、服装やここに名刺がおいてあるということなどをピックアップするということを通して、この状況からコンピュータがコンテクスト情報を活かして推測できることはたくさんあります。それらを使えば、たとえば撮影のときの照明をこの雰囲気に合わせてオートマチックにコントロールするなど、さまざまなことができそうです。
一方で、より凝ったことを推測していくためには、心の状態(Emotional State)が重要になってきます。広告を例にすると、送り出したメッセージがどのように受け手に影響を与えているか、そもそも受け手は注意をメッセージに向けていてくれているのか、そのメッセージを覚えていてくれているか、次に同じメッセージを違うメディアから発信した際にも同じものとして結びつけてくれるか、そういった受け手の内的な興味や感情の理解なしには先に進めないとも思っています。つまり、どこにいる、とか、今何時か、という単純なことだけではなくなってくるわけです。
そのために、心の状態をうまくピックアップしていくことで、何かの操作をしたときにシステムがどのような結果を返すべきかというようなことについても、より深いフィードバックが可能になるのではないかと考えています。
前田:
その点はとても興味のあるアプローチだと思っていますし、私自身、現在Webが先に進もうとするときに、場所とかモノとか人間関係のようなセマンティックなものをどのように捉えるかについて様々なアプローチをしています。
Webの世界は、ゆるやかに構造化された世界として発展してきたと思いますが、今の発言にあった文脈の理解のためには、これまで扱ってきたデータよりも何倍も膨大な、状況記述のためのメタデータが必要になってしまうと思っています。
石井先生は、たとえばオントロジーのような形でそのように膨大なデータを構造化することなく、このような状況を把握されようとしているのでしょうか。
石井:
基本的にコンピュータという環境で処理するには、記号表現、数値表現に落とし込む必要があります。
完全にアナログの世界の中だけでループを閉じてしまう方法もあるでしょう。しかし、デジタルとして行う以上、メタデータでも生データでも、必ずなんらかの形でデータを変換してコンピュータが処理できるようにする必要があります。
Webに使用するかどうかということは必ずしも本質ではなく、コンピュータがアクセスできるサーバにデータがありさえすれば、膨大なメモリと高速な計算性能を用意することで、あとは低レベルのデータを抽象化する方法を探すことになると思います。たとえば、私がある動作をしたときにこの動作をどう捉えるか考えてみましょう。私はペンを取ろうとしている、それは何かを書きたいから、それは今の会話での良いアイデアを書きとめ、あとで反芻したいから、まとめてインデックス化したいから、というようにあらゆる低レベルの動作は上位の目的構造の中で行われています。しかし、どのような意図で私がこれを行ったかということ自体は非常に曖昧です。
Webに話を戻すと、ページにアクセスしたという行動履歴がどこかのリポジトリに保存されるとして、低レベルなそういった行動データからどのように上位の「意図」をとりだすか、そこの見極めが大事になってきます。
したがって、非常に状況限定的な、汎用性は高くない形のシステムになっていくのではと思います。
コミュニケーションビジネスの在り方
前田:
この連載の中では、見えない関係性、言語化できない文脈をどのように可視化するか、ということも共通して出てくる話題なのですが、石井先生の研究でもそのようなテーマでの研究はありますか?たとえば、記述しにくい感覚や感触を可視化して、コンピュータにもう一度フィードバックするというようなことになるでしょうか。
石井:
今の質問には2つの解釈があると思います。1つは、たとえば米ソ間の緊張感を想像してください。核の先制攻撃に対する恐怖感が世界を支配していた頃、この恐怖はインビジブルでありインタンジブルで、それをわかりやすく可視化したいということでしょうか。もう1つは、そういった概念すらない、なんとなく頭に浮かぶような、捉えられないもやもやしたアイデアを可視化したいということでしょうか。
前田:
後者のほうですね。英語で言えば、“ tacit(暗黙)” という言葉に近いと思います。
石井:
すると次は、それをコンピュータが理解できる形にするのか、人間が読める形にするのかというアプローチを考える必要があると思います。どう表現したいのか、ということです。コンピュータに理解できるような処理を考えるだけでも、テキスト形式にするだけなのか、データとして抽象化・構造化した形にするのか、など、これもアプローチがさまざまにあります。
そもそも、この抽象化や構造化に対して具体的なアルゴリズムやプロトコルがない場合には、検索性という意味はあるかもしれませんが、無理にコンピュータが理解できる形にしても意味がないように感じます。写真のように生データの状態で保存し、弱いタグをつけてクラスタリングするという程度でしょう。
結局、情報はストレージにたまっていくけれども、何を行うためのものかというアルゴリズムやプロトコルがないと、“ 情報” は“ 知識” になっていかないと思います。それだけでは、ワインのように自然発酵してはいかないですよね。
前田:
私自身はソーシャルメディアやCGMを専門にやってきていたのですが、多くの人が客観的に理解できる事実と個人的な体験のちょうど間の、今までは間主観的とか集合主観だとか呼ばれてきたようなデータがコンピュータで処理できるような形式になったとき、「 この部分のデータは間主観的なデータだ」と言えそうになることが多くありました。
つまり、コンピュータが処理可能な形にすることで、今までは親しい人とだけ共有できた「あのさぁ、あれあれ」「 あぁ、あれね」とパッとつながるようなことを実現できないかなと考えているのです。こういう共感を、夫婦の間だけではなく、もっといろいろな人との間に広げて行きたいな、と。
石井:
なるほど。別の例で考えてみましょう。シュールレアリズムに傾倒していて、世の中のある出来事に対して「これはシュールだ」と表現する人がいたとします。ある画家の絵をさして「シュールだ」と分類するのではなく、メタな形容として特徴を抽出し、パタン認識をした上で「シュールだ」と表現できるようになるには、それなりの体験が必要になると思います。これは、単純なキーワードマッチングのようなものではなく、もっと深い「あうん」の呼吸というか、スポーツのプレーにおける「間合い」のようなものと言えるでしょう。
先ほど出たtacitという言葉が指す内容であっても、記号表現にしたとたんに陳腐な百科事典的な解説になってしまうものもあるし、好みのレストランの傾向のように、アグリゲーションを行ってタグをつけていけば、なんとなくその人の好みを記述するとか分類できるようなものもあります。先ほどの繰り返しになりますが、どこまで何をやるのかが本当に重要です。
コンピュータ屋さんはコンピュータでやれることしかしませんし、コンピュータでやれることがすべてだと言いたいと思います。しかし、コンピュータでは処理できない、けれども人間には理解できるという例はたくさんあるわけです。
私は宮沢賢治の詩集を活字で読んでいました。そして、日本を離れるときに花巻の宮沢賢治記念館に行ってみたのです。そこで出会ったのは、肉筆原稿が持つパワー、そこから想起されるそこに存在したであろう身体、作品が創られた痕跡を示す色のあせた青いインク、黄ばんだ紙。それらによる感動は、もちろん人間にしか理解できない情動です。そういった感動というのは、今のASCIIやEUCのようなフォーマットや、スクリーン上には存在しない情報です。だからコンピュータやWebではそれは絶対太刀打ちできない。
しかし、それはデジタルだから太刀打ちできないということではなく、そういうものを表現するためのビジョンや美学を持った人がデザインしていないからだと考えています。
前田:
私は音楽をやっていましたが、サンプリングの技術の向上でピアノの音にどんなに近づいていったとしても、より生ピアノのよさが逆に際立ってしまう、そういう感覚でしょうか。たとえば、湿気を帯びた空気の中でピアノを弾いた時に指に返ってくる、少し重い雰囲気、のようなものですが。
石井:
そのような情報は最終的に振動に還元できますが、もっとエモーショナルな側面ですね。
ツール・ド・フランスで何度も勝っているLance Armstrongという選手がいます。彼は一流の選手であると同時に、ガンを克服したというエピソードもあります。彼の勝利についてどこから感動を得たかといえば、そういうストーリーです。
ピアニストであれば、汗をかいて必至で演奏しているというような、そういうもっと違う側面で感動が生まれているように思います。誰と行ったのか、隣の人と何を共有できたのか、何がずれていたのか、そしてコンサート会場を出た時に感じた冷気。そういうあらゆるものがあるから感動できる気がします。
そういうエモーショナルな状況は、サンプリングとは違う次元ですよね。歴史、記憶の積み重ねから感動するものかもしれません。そこは逆に、蓄積が得意なWebでも、結構いけるのではないかとも思っています。
あらゆる眠っている記憶、感情、それらを起こすためにあらゆるところから信号を送り込むこと。広告会社が送るメッセージが記憶と共振して、私たちの中に眠っているものがむくむくと起きていく、そして、購買意欲とか幸せにつながっていく。たとえばコミュニケーションビジネスとはそういうものだと思います。
だから、一方的に送るメッセージ、受信されるメッセージをサンプリングないしデジタイズするということだけでは、Claude Elwood Shannonの通信理論的な世界としては成立するかもしれませんが、ヒューマンコミュニケーションの世界やコミュニケーションデザインの世界ではすごく低レベルなことでしょう。C++コンパイラを使うのかObjective-Cのコンパイラを使うのか、RFIDがいいのかBlueToothか、というようなそういう次元の話ではないということと似ています。
メディアラボという環境
前田:
だとすると、私自身にメディアラボへの偏った見方があるかも知れません。メディアラボは、ヒューマンなものを超えるテクノロジーを研究しているものだ、とばかり思っていたのですが。
石井:
メディアラボでも、Marvin Minsky[3] は、何十年もAIを研究してきましたが、彼はそういった永遠のテーマにロマンを持って取り組んでいますよね。なんらかの知識、それも表現可能な知識、それらを計算することができるアルゴリズム。そういった夢を実現しようとしている人もここにはいます。
メディアラボはこう考えている、ということではなく、メディアラボの30人くらいの教授はそれぞれみんなバラバラの別の夢を見ていますし、その夢を比較することはできません。
メディアラボという環境がすごく大切にしているのは、そのようないろいろな違う夢を見ている人間が集まっていて、そこから議論が生まれていることです。差異が大切なのです。
金太郎飴のように、研究員全員が同じ夢を見て同じ方向に進むような環境では、イノベーションは起きないですよね。ちょうど、みんなWebだ、2.0だと言っている状況と似ているかもしれません。別の例を挙げるなら、みんなが同じCADツールを使って、同じベジエ曲線、スプライン曲線を描くようになると、なにか味気なくて「やっぱり鉛筆だよな」となってしまう。しかし、それはイノベーションではありません。
前田:
石井先生がアメリカに来て研究されている動機も、やはりそのような部分からですか?
石井:
たぶん、日本も研究には非常にすばらしい環境ですし、リソースも潤沢だと思います。しかし、批評的、建設的な環境かという面で大きな違いがあると思います。
アメリカの独創性を支える風土として“ オリジナリティ” が挙げられます。それは、人と違っていること、違っていることで世の中にインパクトを与えることと言えます。そこに対して非常に執着しますし、同時に先人たちが積み上げてきたクレジットに対しても非常に厳しく明確にしていく必要があります。日本は本当の競争がなかなか生まれにくい文化だと思います。
前田:
以前、日本の新聞でイノベーションとはどう起こし得るものですか、という質問に、石井先生は「異なる視点の間を行き交いする力」といった言い方をされていたように記憶しています。
石井:
そうですね、イノベーションには違った視点からの批評というものはとても重要で、このペンをどのような視点で見るのか、実用性、芸術性、デザイン、そしてサイエンスな視点や特許をとったような技術が背後にあるのか、そしてこれをもつ私にどのようなアイデンティティを付加してくれるのか。
そういったあらゆる視点を高速に切り替えて絨毯爆撃のように徹底的に議論ができることが本質で、そのためには各人が幅広い視野をもち、違った価値観・価値体系を切り替えられなければならないと思います。また、異なる価値体系の間でアイデアをわかりやすく翻訳して伝えることも必要です。
Web、デジタル、シグナルという技術的に主流となっているスレッドもあるわけですが、同時にアナログ、朽ち果てるもの、死んでしまった人の想い出というようなエモーショナルなスレッドも世の中にはあります。そういった部分に気がつくかどうかで、より深いレベルに、哲学的なところへ昇華していけると思います。
日本の場合には、電子工学科とか化学科とかの専門分野に進んでいく中で、価値観が狭められていっていると思います。こちらでは、メジャーとしてのコンピュータサイエンスの裏で彫刻を学ぶというように、違った視点や違う価値観を5つ6つともっていないとやっていけません。
セレンディピティの提供
前田:
私自身もWeb 2.0といったような日常の仕事に埋没している感じですが、現在希有なクライアントと一緒に、“ セレンディピティ” を追求することを仕事にできています。このセレンディピティは偶発的なものですが、関心空間というソーシャルメディアの構築を通して、さまざまな人にそのようなセレンディピティのある、価値ある情報との出会いを提供してきました。その中で法則性というところまではいかないのですが、なにか共通性のようなものを感じ取っており、そのクライアントさんと追求しているところです。
石井:
「セレンディピティを体験して良かった」と思うような例にはどのようなものがあるのでしょうか?
前田:
私たちは“ つながり” という情報を重視しています。あるコンテンツとあるコンテンツの間の、私だけにしか見えない“ つながり” というメタデータをゲームのように付与できる、そういうシステムが関心空間です。そのつながりを見ていると、客観的なものから間主観的なものなどいろいろあるのですが、“ つながり” には重みがあるのではないかということを感じ始めました。これは日本語でいうと、“ 編集” という言葉に近いのかなと思っています。
石井:
松岡正剛さんの言う、編集工学的なものでしょうか。
前田:
そうです。アルス・コンビナトリア(結合術)です。構造化されたコミュニティを構築していく中で、あるルールに則って、あるコンテクストをつくっていくと、普段であれば相対的に見える行動の中に、ある意味で類型的で、集合的な行動をしているような状態が見えてきます。いわゆる集合知(Collective Intelligence)です。
そうしてできた集合知の中でも、ある基準でハイコンテクストといえるつながりと、ローコンテクストといえるつながりを提示すると、ぱっと見ると2つの違いはぼんやりとしかわからないのですが、どちらが高い関係性をもっているかという質問をすると受け手はハイコンテクストなほうを選ぶということを実験で確認しました。現在は、それをもっと細かく観察しているところです。
これがうまく理論化できると、近接領域的でセレンディピティな発見や個別適合化された情報の提示をすることが可能になるのではないかと考えています。ある人にとっては周知の事実と感じているような結果を提示しない、というように、うまく受け手が必要としている情報の周辺部分を提示できるのでは、と思っています。“ セレンディピティ・オン・デマンド” といったところでしょうか。未来の検索技術と推奨技術の中間のようなものですね。
石井:
そのあるコンテンツとあるコンテンツの因果関係は、人間が手で抽出したり付与しているものなのですか? または、あるセマンティックな空間のなかから自動的に抽出しようとしているものですか? ちょうど、AIの人たちが'60年代、'70年代にアブダクションと呼ばれる学習方法に挑戦していたことに似ていますね。この分野は死屍累々とも言えるのですが。
前田:
確かにその通り(笑) 。個人的に第五世代コンピューテングの話[4] やMarvin Minskyの『心の社会[5] 』を読むと心が惹き付けられつつ、不可能性について考えざるを得ません。ただ、私があの時代と違うと感じているのは、コンピュータで処理可能なデータを多くの人とWebを介してシェアすることができていて、私たちも研究の際に今まで捉えられなかった層の人とコミュニケーションできることだと思います。
たとえば広告会社でも、これまでも一般的なパネラーに対してはお金を払ってコンタクトをとってきたと思いますが、アーリーアダプターのようなお金を払ってもリーチしなかったような人たちと、blogのような彼らの自発的な行為をとおしてコミュニケーションできるようになったことは、10年前、20年前と大きく違う部分だと思います。
石井:
なるほど、コンピュータが抽出するというのではなく、人間が意図を持ってつけたタグに注目するのであれば、ドラマティックに違うでしょうね。自動化された中で辞書を見ているだけだと確かに実現できない部分ですし、AIの頃と同じアプローチです。
しかし、人間がつけたタグ、そしてそのタグの裏にある意味の構造を考えていくのであれば、人間の知的生産とコンピューティングを組み合わせるということですから、おもしろい取り組みになっていくかもしれません。どのように類推・連想のためのライブラリを持ち、豊かにしていくか、それが重要ですね。
キーワードで新しいソーシャルメディアを
前田:
そのクライアントさんからお声がけいただいたのは、単にコンセプトだけでなく、すでに関心空間には24万件のキーワードのエントリーが、なんのインセンティブもないままに投稿され、そのキーワードに45万個を超えるつながりやコレクションというユーザー投稿型の編集データがついているからだと思います。
「このキーワードとこのキーワードは○○つながりである」または「○○とかけて○○ととく」というような、単なるタグとは異なる、人を喜ばせよう感動させようとする気持ちのはいったメタデータになっているのです。
石井:
それをどのように使っていくかというのは、まさにチャレンジングですね。
前田:
ただ、24万件というキーワードでも、世の中の関心事に対しては量が少ないのです。日常生活でTVの前に座っている受動的な人に対してインパクトを与えられる数ではありません。
このキーワードやメタデータを生活の中で活用しようとしたときに、たとえばこの人はアルコールを呑まれないからなにか甘いものを、というようなおもてなしの気持ちのようなものに組み合わせていきたいのですが、まだそこまではいきません。
また、blogを書かせたりするような積極的な活動なしに、そういったものを自然に抽出できるようにするにはどうしたら良いだろう、というのが最近の議論です。自分が発信しているつもりがないのに発信しているようなものが人間には多いはずです。それを今の安くなったセンサーでピックアップできて、ユビキタスな環境の中でつながっていくことが新しいソーシャルメデイア、CGMになっていくのであれば、おもしろくなるかなと思います。
偶然の出会いが創造につながる
前田:
最後に、この“ セレンディピティ” という言葉から石井先生が想像されることはなんでしょうか?
石井:
やはり、偶然の出会いということですね。人間や情報、作品。もう死んでしまった人の作品との出会いかもしれません。または、運が良ければその作品をつくった人にも会えるかもしれません。
いつ誰に、どのようなタイミングで出会えるかということは予測できませんが、正しいタイミングで会うべきものに出会うことこそ、セレンディピティです。そのときには気がつかなくても、いつか、なぜそこで出会ったのかという必然性がわかる。そういうものがクリエイションやインベンションには非常に大切で、そのすべてに理由があり、その理由がわかってくる瞬間には価値が外化されてくるのだと思います。
すばらしい人に会う、すばらしい作品をいっぱい見る、それをいっぱい自分の栄養にする、すぐにできなくてもワインセラーに貯蔵するように寝かせておく、それが大切な燃料になると思います。
人と人が出会い系サイトで直接出会うということ以外でも、ある情報に共通するトピックスを違った視点から提示し、そのトピックスを介して人と人がつながったときには、別の大きなうねりとなります。Howard Rheingoldが書いたようなことですね。
関心空間が今やっている実験というのは、未来のクリエイティブなソサイエティにおいて、どういった触媒が必要になるのかを調べているのだと思います。人と人との化学反応の閾値を下げるために、どのような触媒が見つかるのか、貴重だと思いますし興味があります。
一方で、デジタルに乗らないところにも百倍、千倍の価値があります。旅をすること、良い作品に対峙することもそうですね。その価値を、偶然見つけることができるなら、本当は一番良いことなのかもしれません。
前田:
人の感動といった抽象的な領域にまで研究を進めていくということですね。わざわざボストンにまで来た甲斐がありました。お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
AN APPLICATION IMAGE INSPARED FROM THIS TALK(対談からインスパイアされたWebサービスイメージ)
昨今、小型の機器を通じて脳波(EEG)をスキャンして、パーソナルコンピュータのコントローラとして利用する技術が登場している。またこれらをマーケティングに利用するニューロマーケティング(Neuro Markerting)なる分野も萌芽し始めている。
これらを利用して、たとえば、モニターの前にいるユーザの感情や意思をネットワークを通じて転送したり、それらのユーザーの共通した感情をコンテンツ推奨やコンテンツ内容に反映することもいずれできるようになるに違いない。
しかし、もっとも重要なことはひとの感情を正確にマーケティングする技術ではなく、“ ひとをワクワクさせる技術” に他ならない。感動の裏に何が潜むのか、それこそが永遠のテーマである。
MITメディアラボについて
MITメディアラボは、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)建築・計画スクール内に設置された、米国内外の企業がコンソーシアム形式で共同研究を行う機関です。人間とコンピュータの協調をテーマにしたさまざま研究開発を行っています。また、その研究分野には、新しいテクノロジーの開発だけでなく、発展途上国のための技術支援も含まれます。
URL:http://www.media.mit.edu/