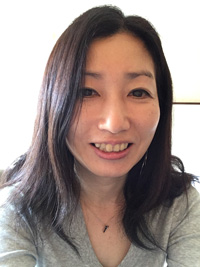2014年を迎えるにあたり、
すぐれたソースコードがすぐれたコミュニティを作る
- ──ここでPostgreSQLコミュニティの話を伺わせてください。オープンソースプロジェクトとして、
PostgreSQLは比較的長い歴史を誇ります。長く続いた要因としては、 MySQLのように1社が開発の主導権を握っているのではなく、 多くの開発者が集って開発しているからだと思っているのですが、 石井さんはどう見ていますか。 石井:まったくその通りだと思います。ほかのオープンソースプロジェクトもPostgreSQLをお手本にしてほしいですね。そのプロダクトが黎明期のころは1社だけがバックについて開発するというスタイルもありかもしれませんが、
ある程度成熟してきたら、 ひとつの企業が開発を100%コントロールしようとするべきではない。みんなで開発するというスタイルのほうがより多くのユーザに使われるようになり、 コミュニティも発展し、 ビジネスとしても伸びていく余地があるように思います。 - ──石井さんは日本PostgreSQLユーザ会の初代理事長で、
いわば日本のPostgreSQLコミュニティの育ての親ともいえる存在です。その石井さんから見て、 現在のコミュニティのあり方はどのように映っているでしょうか。 石井:そんな大層なものじゃないですよ
(笑)。ただ、 国内のコミュニティは順調に発展していると感じています。他のオープンソースプロジェクトと比較しても、 非常に質の高い、 また密度の濃い活動ができているのではないでしょうか。開発者の若返りもかなり進んでいますし、 個人的には日本のコミュニティに関してはもう何の心配もしていないですね。 - ──日本のPostgreSQLコミュニティの質の高さが世界にも波及しつつあるように思えるのですが。
石井:そういう面もあるかもしれませんね。PostgreSQLのコミッタは世界中にいますが、
彼らを講演などで日本に招待すると、 「日本のコミュニティで話せるなんて本当に光栄」 と非常に名誉なことに思ってくれるようです。世界各地のPostgreSQLコミュニティの成長を促してきたという意味では、 日本が果たしてきた役割はたしかに大きかったと思います。 PostgreSQLを初期から見ている人間としては、
日本のコミュニティが順調に発展してきた背景には、 PostgreSQL自体が本当に純粋なオープンソースであることが挙げられると思うんです。コードがシンプルなので、 さまざまな機能を実装しやすく、 拡張性にすぐれている。そしてライセンス体系もシンプルなので誰もが臆せず利用できる。数あるオープンソースの中でもこれほどシンプルで、 さまざま人にとって使いやすいプロダクトはそうないのではないでしょうか。先ほどの繰り返しになりますが、 その使いやすさに惹かれて多くの開発者が集まり、 すぐれたコミュニティが育ち、 ビジネスとしても伸びる結果につながったのだと思います。 - ──わかりやすい具体例を挙げていただければ。
石井:たとえばPostgreSQLには、
外部のPostgreSQLサーバに対して標準的なSQLで検索を実行する外部データラッパのfdw (foreign data wrapper) という機能があります。これは、 ユーザからの 「アドホックに外部データを使いたい」 というニーズを受けて生まれたわけですが、 ほかのデータベースでfdwのような機能を実装しようとするとかなり大変だと思います。でもPostgreSQLは標準的であること、 シンプルであることを徹底しているので、 こうした機能もさくっと実装できる。コードが素直だからこそ実現できるわけです。そしてそうした成果物を多くのユーザや開発者が享受できる。非常にすぐれたソースコードを元にしたエコシステムがあるからこそ、 すぐれたコミュニティが発展してきたといえます。 - ──すぐれたソースコードだからこそ、
すぐれたコミュニティが育つわけですか。その発展の基盤となったのが日本であるにもかかわらず、 国内ではまだ8. x系が主流だというのはすこし残念な気もします。 石井:たしかにそうです。先ほども触れましたが、
やはり米国などに比べると先進性という意味では日本は2年くらい遅れているように感じます。たとえば海外でよく見かけるHadoop×PostgreSQLやNoSQLデータベース×PostgreSQLといった組み合わせで高トランザクションのWebデータベースシステムを構築しているという事例なども日本では非常に少ない。ユーザがインハウスでシステムを設計できる米国に比べ、 日本のユーザは基本的にSIerに依存する部分が大き過ぎることが原因だと思っています。 日本では仮にユーザが
「最新バージョンを試してみたい」 と言っても、 安定性を保証できないからとSIerが止めるケースも少なくありません。これはSIをビジネスにしている我々の責任でもありますが、 ユーザ自身ももう少し積極的になる必要がある。世界がお手本とするようなコミュニティがあるのだから、 導入事例でも日本が世界をリードするような存在になっていきたいですね。

オープンソースは使う人も作る人も幸せにする
- ──最後に2014年を迎えるにあたってのメッセージをいただければ。PostgreSQLにかぎらず、
ITのトレンドについて思うところがあればぜひお願いします。 石井:最近読んだSF小説に
『順列都市』 (グレッグ・ イーガン 著) というのがあるのですが、 人間の脳をスキャンしてコンピュータ上に仮想空間をつくり上げるという、 まさに人間をリソースとした近未来のクラウドを舞台にした内容でした。作者のグレッグ・ イーガンは前職がプログラマなので、 リソースの分散と集中という概念を非常にうまく描けていると思います。 いま、
クラウドが世界を席巻していますが、 もう少ししたら、 人間の脳まではいかなくても、 ほとんどのリソースが仮想化されて、 それらを扱うマーケットが新たに発展するかもしれません。そのときIT、 とくにデータベースはどんな役割を果たすようになっているのか、 非常に興味深く思っています。 もうひとつ、
2014年に期待しているのはITとリアルの融合事例として、 自動車の自動運転が実用化の段階に入るのではと期待しています。この分野ではGoogleのパワーはすごいですね。AWSがクラウドで世界を変えたように、 Googleが同じような力を発揮するのではないでしょうか。 個人的な話をさせてもらうなら、
実は最近、 還暦を迎えまして。まさか自分がコードを書きながら、 それもオープンソースのビジネスに関わりながら定年になるとは思ってもいませんでした (笑)。PostgreSQLとオープンソースが好きでひたすらコードを書いていて、 気がついたらPostgreSQLをビジネスにするSRA OSS, Inc.の日本支社長になっていました。いまはPostgreSQL以外にもZabbixやHinemosなどのオープンソースをビジネスにしていますが、 本当にオープンソースを仕事にできてよかったと思っています。オープンソースは使う人も作る人も幸せにします。2014年はその幸せをいまよりも多くの人に届ける仕事をしていきたいと思っています。