エンジニアと経営のクロスオーバー 記事一覧
-
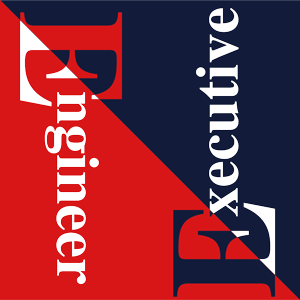
第12回
(最終回) エンジニアが 社長に なるのは あまり 得策ではない、 それでも その 道を 進むか? 2018-06-13
-
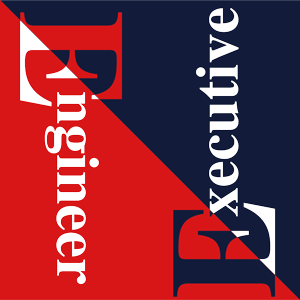
第11回
営業を やると エンジニアライフに 絶対に プラスに なる 2018-04-05
-
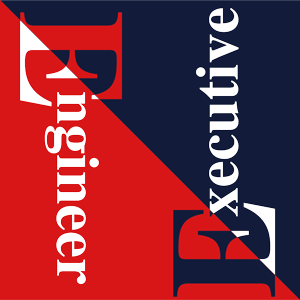
第10回
アクセルを 踏む 決断を いかに 下すか 2018-01-22
-
-
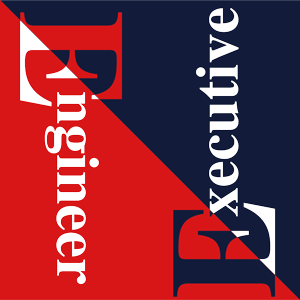
第9回
委任が 苦手だと 会社は 成長しない 2017-12-20
-
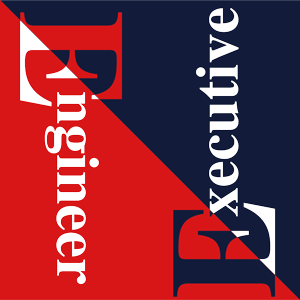
第8回
教育に おける エンジニア出身社長の 得手不得手 2017-11-24
-
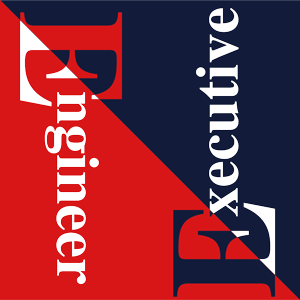
第7回
エンジニアにはどんな 教育が 必要か 2017-11-06
-
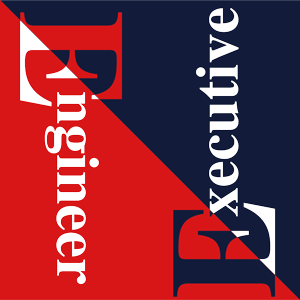
第6回
エンジニアに とって 「マネジメント」 と 「リーダーシップ」 は どう 違うのか 2017-10-13
-
-
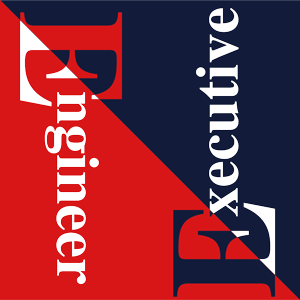
第5回
リーダーと マネージャーの 違いとは 2017-09-25
-
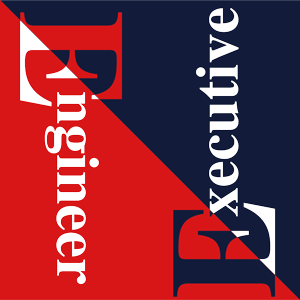
第4回
採用に よって バーンレートよりも 収益の 向上を 高くする 2017-09-04
-
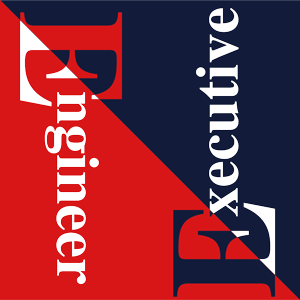
第3回
チームづくりに おける エンジニア出身社長の 強みとは 2017-08-21
-
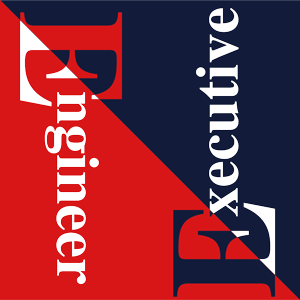
第2回
ビジネスモデルと 原価と 経費 2017-07-18
-
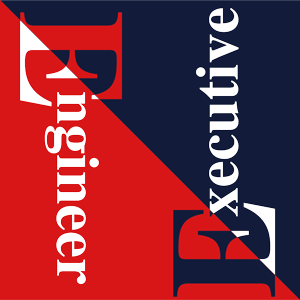
第1回なぜ、
エンジニア出身の 社長は 少ないのか 2017-07-03
-
おすすめ
ランキング