書籍『ピタゴラスの定理でわかる相対性理論』の補講 記事一覧
- 直近
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
-
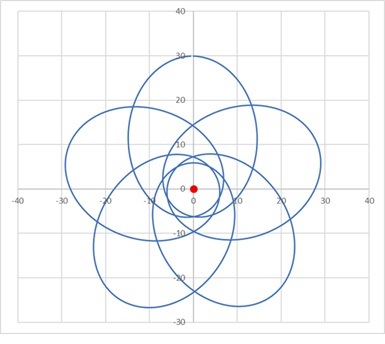
第18回
日常から 離れる 楽しさ:一般相対論を Excelで 2025-10-10
-
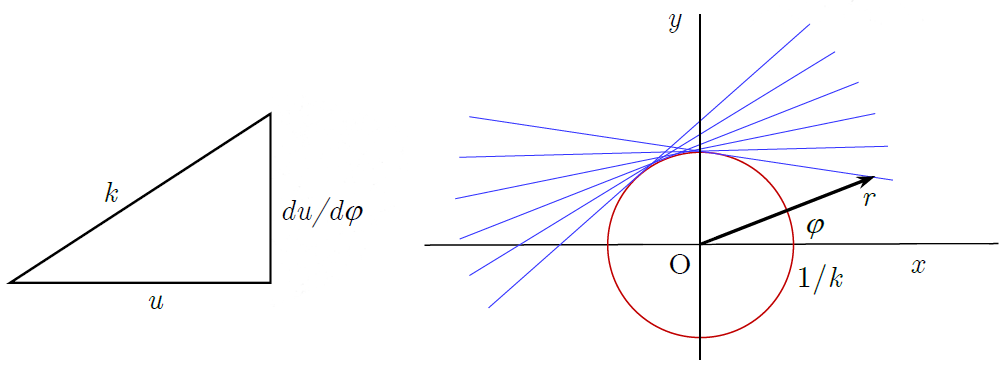
第17回
特殊相対論から 一般相対論へ Pythonに よる 幾何計算 2024-08-01
-
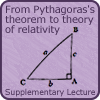
第16回
宇宙存在の 理由と 地球環境の 保全 ~本書 「ピタゴラスの 定理で わかる 相対性理論」 の 意味は 何だったか? 2009-09-28
-
-
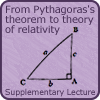
第15回
ライバル同士の 対話 2009-08-10
-
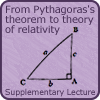
第14回
相対論から 量子力学への 展開と 日本の 時代 2009-06-19
-
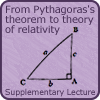
第13回
ピタゴラスの 定理に 宿される 秘儀―エネルギーと 運動量に 関係する 法則 2009-04-02
-
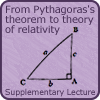
第12回
光量子仮説と 相対性理論― アインシュタインは どのように 考えただろうか? ー 2008-12-16
-
-
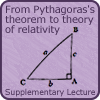
第11回電磁界の
エネルギーに ついて アインシュタインは こう 考えた 2008-10-30
-
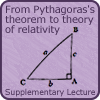
第10回
アインシュタインの 論文の 原文に 挑戦! 物体の 慣性は その エネルギー量に 関係するか? Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? 2008-08-11
-
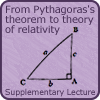
第9回
独創性の 原点、 アインシュタインの 第一論文 2008-04-15
-
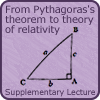
第8回双曲ピタゴラスの
定理の 計算プログラムで、 実際に 計算してみよう! 2008-02-12
-
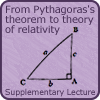
第7回
不思議な 波動、 移動縞 2007-12-21
-
-
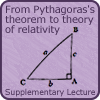
第6回光と
電磁波 2007-11-19
-
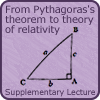
第5回
レーデル線図は コロンブスの 玉子 2007-10-01
-
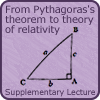
第4回
現代に 伝えられる ユークリッドの 『幾何学原本』 -3000年前の 英知が 蘇る - 2007-08-08
-
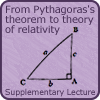
第3回
事実は 小説より 奇なり 2007-06-22
-
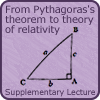
第2回
アインシュタインに 影響を 与えた オーストリアの 物理学者 2007-04-13
-
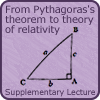
第1回
ガウス・ ボンネの 定理から 底辺×高さ÷2の 公式へ 2007-04-13
-
おすすめ
ランキング