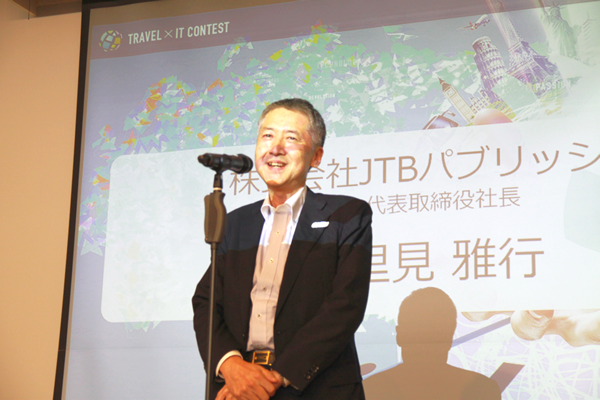2016年9月10日、株式会社JTBパブリッシング、大日本印刷株式会社、株式会社DNPデジタルコムの3社主催のアイデアコンテスト「TRAVEL × IT CONTEST」の最終審査会および授賞式がDNPプラザ(東京・市ヶ谷)にて開催された。
- TRAVEL × IT CONTEST
- http://www.dnp-digi.com/travel-jtbp/
本コンテストは、旅行ガイドをはじめ、「旅」に関するさまざまなメディア・コンテンツを提供するJTPパブリッシングが中心となって、これからさらに注目を集めるであろう日本、その日本での未来の旅を再確認し、新たに提案するためのアイデアの創出、その先にある市場形成を目標として行われたもの。
2016年6月から募集が始まり、7月に1次選考を終え、最終的に10組のファイナリストが残り、最終審査会へと進んだ。
審査にあたっては、6名の多彩な顔ぶれの審査員が集まり、「旅」と「IT」、それにまつわる「体験」、そして「ビジネス」というポイントをふまえて、6名それぞれの視点による審査・講評が行われ、最優秀賞、そして、当日急遽特別賞(2組)が選ばれることとなった。
表 審査員(50音順、敬称略)
| JulieWatai(フォトグラファー/アーティスト) |
| 鈴木正晴(株式会社日本百貨店代表取締役社長、群馬県桐生市PR大使) |
| 東泉一郎(デザイナー/クリエイティブディレクター) |
| 馮富久(株式会社技術評論社 クロスメディア事業部電子出版推進室室長) |
| 八幡暁(冒険家) |
| 吉里裕也(RealTokyoEstate-東京R不動産-) |
最優秀賞は「TraveRing」
最優秀賞に選ばれたのは、下穂菜美・河村拓両名が考えたアイデア「TraveRing」。
最優秀賞としてJTB旅行券50万円分を手にした下穂菜美・河村拓両名

このアイデアは「Ring」という単語が入っているとおり、ブレスレット型のリングでユーザ自身の旅の体験を広げ、価値を高めることを目指したもの。
旅という行為は、体験そのものに価値がある一方で、体験を記録に残すというのは実は難しかったり、手間になるというところから「旅を可視化する」という視点で生み出されたそう。
自身が行った場所や写真を撮った場所、日時など、旅に関わるさまざまなデータを専用デバイス「TraveRing」に蓄積することで、旅の可視化を実現する。
この点について審査員で冒険家の八幡氏は「私の旅は基本的に本当に必要なもの以外何も持って行かない場合が多く、結果として記録に残しづらい。もしこのアイデアが実現したらまっさきに使って将来のために記録を残したい」と自身の体験になぞらえたコメントをした。
また、今回は現段階では実装しきれていない技術も含められるという前提があり、本アイデアではモバイルデバイスの課題でもあるバッテリについて、人間の動きから発電しチャージできるといったような、近い将来可能になるかもしれないアイデアが含まれていた点も評価された。
惜しくも最優秀賞には届かなかった特別賞2組
今回、当初は最優秀賞1組のみの選出が予定されていた。しかし、ファイナリスト10組それぞれが大変ユニークかつ素晴らしいアイデアが多く、審査員から特別賞を贈ることが決まった。
友達かも?の次はドッペルゲンガーかも?が流行る?!「ドッペルゲンガーに出会う旅」
まず1つ目の特別賞は、永島一樹氏が考えたアイデア「ドッペルゲンガーに出会う旅」に贈られた。このアイデアは名前のとおり、ドッペルゲンガー(自分にそっくりの姿をした分身)を、ネットを通じて探し出し、その探索から生まれる行程を旅につなげていくというもの。
ストーリー仕立ての発表が印象的だった特別賞の永島一樹氏

サービス実現にあたっては、Facebookの顔認識技術「DeepFace」を活用し、まずはFacebook上で自分自身のドッペルゲンガーを探し出し、コミュニケーションと旅をつくっていく。
発表にあたり、もしこのサービスがあったらどうなるか?ということをストーリー仕立てで説明し、その点のわかりやすさが評価された形となった。審査員の吉崎氏からも「すぐにでもビジネス化ができそう」と評価された一方で、「Facebookを使っていないユーザへのリーチ」といった課題なども指摘されていた。
高齢化社会の日本に済む全員が真剣に取り組むべきアイデア「最高の人生の見つけ方」
もう1つの特別賞を受賞したのは、応募者の安藤克利氏自身が医療に従事する医師として活躍し、今、日本の医学分野の課題となっている終末期患者に対する周囲の対応を取り上げた「最高の人生の見つけ方」というアイデア。
特別賞安藤克利氏のアイデアには審査員をはじめ聴講者全員が改めて旅と人生を考えることになった

日本をはじめ、世界各国で医学が進歩することで人間の寿命が長くなる一方で、その終末期(病気が治る可能性がなく、余命の期間が予想される時期)が高い確度でわかり、結果として患者のケアをどうするか、その部分に関して取り組みが行われるようになった。この点については人それぞれの考え方や価値観があるため、正解がないかもしれない。
こういった背景を実際の現場で体感している安藤氏が「たとえば卒業旅行や新婚旅行など、ポジティブな時期と旅行が紐付くケースは多々見られるだろう。しかし、終末期も人間の大事な時期であり、人生の一部である。そこと旅行をつなげることも大事ではないか。また、それを望む患者が多くいることが実体験からわかり、今回のアイデアを考え応募した」と述べ、実際に起こりうる課題を、論理的かつ的確に指摘し、実現に向けたアイデアを取りまとめ発表した。
発表後に吉里氏から「非常に意義のある、そして、我々すべてが考えていかなければならない問題であり、具体的に実現するにはどうすべきか?」と質問が上がり、これに対し、安藤氏からは「医療現場の人間は意識はあるものの行動する時間がない。それをこういう場で発表し、賛同者・実現者を募れたら実現が早まると考える」と答えた。
この受賞に関しては、審査員を代表して東泉氏から「この“最高の人生の見つけ方”は審査員の満場一致で最高点だった。一方で、今回の審査の特性との兼ね合いを見て最優秀賞という評価とは違った形で評価したく、特別賞とさせていただいた」と、審査の補足が行われた。
審査員の1人でもあった筆者自身もぜひ実現に向けて進んでもらいたいと考えている。
高校生が考え発表した「自動走行キャリーバッグ」や、話題作にインスパイア(?)された「コメラ」など注目アイデアも
その他、7名のファイナリストも大変興味深いアイデアが多かった。共通していたのが、ITという切り口を含めたものの、いわゆるバーチャル体験的な要素を全面に出すのではなく、10組すべてが実際の「旅」をテーマに、実体験をどうするか、その点に向き合い、それをITを使ってサポートしたり拡充するという方向性が見られた。
表 ファイナリスト(受賞者を除く7組)
| アイデア名 | 発表者 |
|---|
| A-Pocket | 正田 創士
|
| 自動走行キャリーバッグ | 佐々木 雅斗 |
| i-Spotパネル | 川野 由香子、中道 上 |
| コメラ | 行田 尚史、船橋 良介、大澤 敦、井上 将宏、常盤 真之亮 |
| ISHIMURA PHOTO EVOLUTION SYSTEM | 石村 直己 |
| ワザトレ | 土居 隆昌、江野畑 陽子 |
| 写真は思い出の軌跡だけじゃない! | 廣瀬 美郷 |
審査および公表を行った審査員の顔ぶれ(右から八幡氏、吉里氏、東泉氏、JulieWatai氏、鈴木氏、馮

たとえば、「自動走行キャリーバッグ」を考えた佐々木雅斗君はこの4月に高校生になったばかりの若者。しかしその年齢とは関係なく、動画を駆使したプレゼンテーション、ITやネットに慣れている若い人だからこその視点がふまえられるなど、審査員からも驚きの声が多数聞こえた。ほかにも最近話題となった怪獣映画を思い浮かべるようなタイトルとなった「コメラ」は、ネットコミュニティとして今、若者には欠かせないニコニコ動画の世界観と旅をつなげ、ネットの中からリアルに近づくアプローチといったユニークな視点が見られた。
このように旅は世代を超えた形でさまざまな概念・価値観が持っていること、そして、どの世代にとっても求められていく社会的な行為であることとが再確認できたコンテストとなった。
旅の体験はITでさらに高まる
最後に、主催者を代表して株式会社JTBパブリッシング代表取締役社長 里見雅行氏からコンテストの総評が行われた。
総評を述べた株式会社JTBパブリッシング代表取締役社長 里見雅行氏
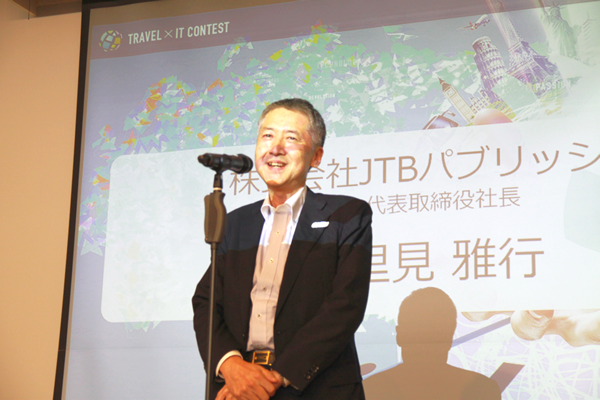
里見氏は「今回、約200ものアイデアが応募され、改めて日本人にとって旅に関する興味が強いことがわかった。また、長年旅に関わるコンテンツを創り出してきた立場として、応募作品を見るたびに、旅の可能性はまだまだあることも痛感させられた。とくに、日進月歩で進むIT/ネットはこれからの日本社会には欠かせないものになるわけで、それらをどう活用していくか、私たちコンテンツを産み出す立場の人間も意識しなければならない。今回最優秀賞を受賞した“TraveRing”をはじめ、多くのアイデアを参考に、新しいビジネス創出を目指したい。これが終わりではなく、これをスタートに、応募者をはじめとした多くの方々と一緒にぜひ“未来の旅”の価値をつねに探し続けていきたい」と、未来の旅に対する強い想いとともに、コンテストを締めくくった。
ファイナリスト全員の記念写真