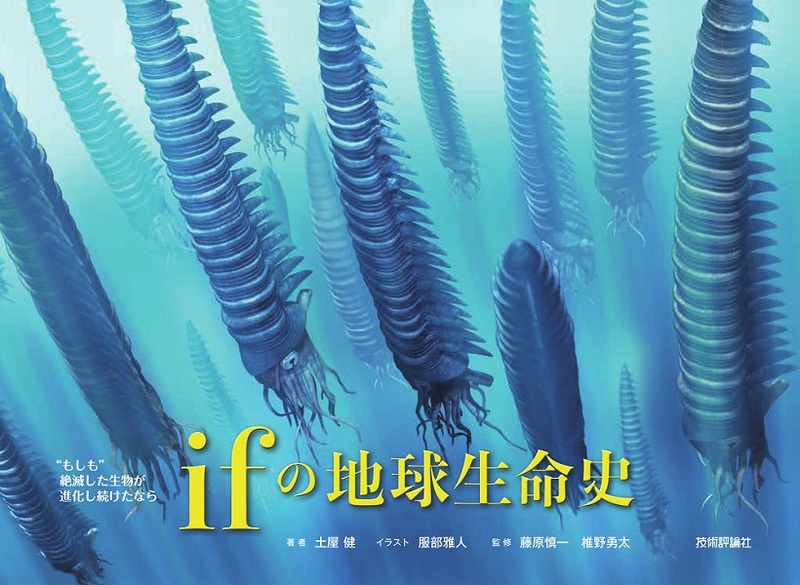Graphic voyage
“もしも”絶滅した生物が進化し続けたなら ifの地球生命史
-
土屋健 著
服部雅人 イラスト
藤原慎一,椎野勇太 監修 - 定価
- 3,520円(本体3,200円+税10%)
- 発売日
- 2021.2.1
- 判型
- B5
- 頁数
- 200ページ
- ISBN
- 978-4-297-11920-1
サポート情報
概要
大人が楽しめる、超リアルなビジュアルブック!
今回は、地球生命史における「if(もしも)の進化」に迫ります。
古生物は、すでに絶滅しています。
しかし、もしも古生物が“何らかの理由で”絶滅を回避し、子孫を残したとしたら、いったいどのような姿へと進化を遂げるのでしょう?
古生代の、あの甲冑魚が滅びなかったとしたら。
中生代の、あの肉食恐竜が滅びなかったとしたら。
新生代の、あの哺乳類が海洋進出をしなかったとしたら。
この本では、そんな「ifの物語」を、超リアルなCGを駆使して展開してみました。
もっとも、いくら「if の世界」であるとはいえ、この本に登場する“if の古生物” は、完全な想像ではありません。
これまでの研究によって明らかになっている進化の系統、生態、他の古生物たちとの関係、周囲の環境などの情報をもとに、専門家とともに
「この系譜で進化してきた古生物が、もしも、このまま進化を遂げたら、こんな種が登場したのではないか」
と“科学的思考実験”を行っています。
「あの魚、このまま進むとこんなになっちゃうの?」
「あの恐竜、こんな環境に進出しちゃうの?」
「あの哺乳類、食べ物を変えてこんな姿になるの?」
古生物たちの進化傾向と生存戦略を、直感的につかんでもらえます。
実在の古生物とifの古生物が交錯しながら展開する奇妙な世界。
古生物のもつ「思考実験を行う楽しさ」を感じてもらえる、マニアックな1冊です。
こんな方にオススメ
- 古生物ファンの方
- 古生物の各系統における進化や生存戦略に関心のある方
- 『フューチャー・イズ・ワイルド』などの架空生物が大好きな方
- SFやファンタジー系が好きな方にとくにおすすめです。
目次
Chapter I 古生代のif
古生代正史
ifの生物たち
- if case 1……アノマロカリス類(ラディオドンタ類)
- エスリオフルディア・マーテルマリス Esuriohurdia matrimaris
- if case 2……ウミサソリ類
- プテロバリスタ・ガジャルグ Pteroballista gadearg
- if case 3……三葉虫綱
- ヴァロプス・カラルマータ Valops cararmata
- if case 4……板皮類
- ドルシウェクシラ・カトストマ Dorsivexilla catostoma
- トルウォトルペド・ポタミンペラトリクス Torvotorpedo potamimperatrix
- if case 5……ディプロカウルス科
- ファスマトヴァクーム・ブフォニストマ Phasmatovacuum bufonistoma
- if case 6……腕足動物
- テギュラリットニア・マグニリムラ Tegulalyttonia magnirimula
- スピノコンカス・スマラグディヌス Spinoconchus smaragdinus
- if case 7……エダフォサウルス科
- パピリオヌンブラ・アンフィスバエナ Papilionumbra amphisbaena
- if case 8……パレイアサウルス上科
- アンブラーティトラブス・ケラトグナトゥス Ambulatitrabs ceratognathus
- パレイアバエヌス・ギガス Pareiabaenus gigas
- if case 9……分椎類
- ヘミスファエラルカ・カラッポイデス Hemisphaerarca calappoides
Chapter II 中生代のif
中生代正史
ifの生物たち
- if case 10……ステゴサウルス科
- バベリトゥリス・ウルネラータ Babeliturris vulnerata
- if case 11……偽鰐類
- フォネオカンプスス・エラーンス Phoneochampsus errans
- if case 12……スピノサウルス上科
- シェブロケルクス・プラタニストイデス Chevrocercus platanistoides
- if case 13……アンモノイド亜綱
- トルペドケラス・ムルティラミナートゥム Torpedoceras multilaminatum
- if case 14……テリジノサウルス上科
- ノトゥロサスクワッチ・マクロプス Nothrosasquatch macropus
- if case 15……アズダルコ上科
- マレオダクティルス・ルキフェル Malleodactylus lucifer
- if case 16……ケラトプス類
- アナティリュンクス・ヘルビセクトル Anatirhynchus herbisector
- if case 17……ティラノサウルス上科
- メガピュービス・アケイルス Megapubis acheirus
- if case 18……モササウルス上科
- クラケノファグス・ネモイ Krakenophagus nemoi
- リミナタートル・ドルミエーンス Liminatator dormiens
- ウァスティタナタトール・ボイデス Vastitanatator boides
Chapter III 新生代のif
新生代正史
ifの生物たち
- if case 19……ペンギンの仲間
- ケルビデュプテス・ロンギコリス Cherubidyptes longicollis
- if case 20……鰭脚類
- バラエノフォカ・プリアプス Balaenophoca priapus
- if case 21……肉歯類
- サルティヒアエナ・ヘルバティカ Saltihyaena herbatica
- ノクティクストス・スカンソル Nocticustos scansor
- if case 22……カリコテリウム科
- メリモルス・プーイーヨールム Melimorus pooheeyorum
- if case 23……グリプトドン科
- ルクタントフォルティス・ディプロハスタトゥス Luctantofortis diplohastatus
- if case 24……イヌ科
- カニス・ルプス・エクウス Canis lupus equus
- if case 25……ネコ科
- フェリス・シルヴェストリス・カピオマヌス Felis silvestris capiomanus
プロフィール
土屋健
著者。
オフィス ジオパレオント代表。サイエンスライター。埼玉県生まれ。
日本古生物学会会員。日本地質学会会員。
金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。
その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て独立し、現職。地球科学、とくに古生物学に関する著作多数。愛犬たちとの散歩と昼寝が日課。
「もしも、高校時代に地学の楽しさを知らなければ」、今頃、ロボット開発に勤しんでいるはずだった(天馬博士になりたかった)。
2019年、サイエンスライターとして史上初となる日本古生物学会貢献賞を受賞。
近著に『学名で楽しむ恐竜・古生物』(イースト・プレス)、『リアルサイズ古生物図鑑新生代編』(技術評論社)、『化石の探偵術』(ワニブックス)など。
本書と同じように「もしも」をテーマにした書籍としては、「もしも、古生物を食べることができたなら」というコンセプトのもとに執筆した『古生物食堂』(技術評論社)などがある。
服部雅人
イラストレーター。
「生命」をテーマとして古生物復元画を中心に描くイラストレーター。名古屋市生まれ。
幼い頃から絵を描くのが大好きで、ゴジラの絵をたくさん描いた記憶が今でも鮮明に残っている。
その後、なんとなく先生という仕事に憧れ、愛知教育大学教育学研究科芸術教育専攻で修士号を取得。
名古屋市の公立小・中学校に長年勤務した後、早期退職して現仕事に就く。
「もしも、他の動物になってみることができるとしたら」、鳥になって大空を縦横無尽に飛び回りたい(人間の今は怖くてジェットコースターにも乗れませんが……)。
藤原慎一
監修(脊椎動物担当)
名古屋大学博物館・講師。千葉県生まれ、埼玉県育ち。
東京大学大学院理学系研究科で博士号を取得。
専門は機能形態学・古脊椎動物学。
その後、日本学術振興会特別研究員PD、東京大学総合研究博物館特任助教、名古屋大学博物館助教を経て、現職。
2018年、日本古生物学会学術賞を受賞。
現在生きている動物の骨の形と運動機能の関係を調べ、そこから見つけた法則を絶滅動物に当てはめることで、過去の生物の生態を復元する研究を行っている。
「もしもドラえもんのひみつ道具をひとつだけ使えるとしたら」、(タイムマシンはお腹がつかえて乗れないので)タイムふろしきで包める(ような怖くない)サイズの化石を蘇らせて自分の仮説を検証したい。
椎野勇太
監修(無脊椎動物担当)
新潟大学理学部准教授。千葉県生まれ。
東京大学大学院理学系研究科で博士(理学)を取得。
その後、東京大学総合研究博物館特任助教を経て、現職。専門は古生物学、地質学、進化形態学。特に、腕足動物、三葉虫、放散虫などの背骨を持たない動物化石を好む。
「もしも、新潟で新潟の日本酒や食べ物に出会ってなければ」、菓子パンやカップ麺、インスタント食材ばかりを食し、カシスウーロンで晩酌する日々を送っていたかもしれない。
主な著書は『凹凸形の殻に隠された謎―腕足動物の化石探訪』(東海大学出版会)。
松田眞由美
監修(ラテン語担当)
東京都生まれ、千葉県育ち、埼玉県在住。
『語源が分かる恐竜学名辞典』(北隆館)の著者。
「もしも、プテラノドンが英語のように”テラノドン”と呼ばれていたら」、学名に興味をもつことはなかったかもしれない。
消えゆく言葉を大事にしたいと思う”趣味人”です。