失敗から学ぶマーケティング ~売れないモノには理由がある~
- 森行生 著
- 定価
- 2,970円(本体2,700円+税10%)
- 発売日
- 2021.12.3 2021.11.30
- 判型
- 四六
- 頁数
- 512ページ
- ISBN
- 978-4-297-12459-5 978-4-297-12460-1
概要
「あ、やっぱりダメだったか」
売れない製品が生まれてしまう理由とは?
豊富な事例を知り尽くした熟練コンサルタントが、マーケティングの失敗パターンを、成功確率を上げるマーケティング理論とともに体系化。
- U&E
- イノベータ理論
- ダブルイノベータ理論
- 価値観分類
- 認知ベース行動
- プロダクトライフサイクル理論
- クープマンの目標値
- プロダクトコーン理論
- ブランディング
- コンセプトの純化
- 意識のブリッジ理論
- Lて山スラッシュ理論
- 差別優位性
- DCCM理論
- 守りと攻めの戦略
30年以上のコンサルティング実績に裏打ちされたノウハウの集大成。
こんな方にオススメ
- 製品企画担当者、マーケティング担当者
- 経営者
- 他部署から商品開発部、広告宣伝部、新サイトの企画を任された方
- なかなかヒットが生まれず悩んでいる担当者の方
- これからマーケティングを学ぼうとする学生の方
- 直接ヒット商品には関係ないけれど、知的好奇心の強い方
目次
第1章 知られなければ「ない」のと同じ
1-1 「自分が知っているから他人も知っている」と勘違いする ~U&E
- 99%の商品が、名前を覚えられることなく、数年で消えていく
- 最初に開発しても、知名度がなければ優位な立場を利用できない
- U&Eは初期診断の大切な指標
- 知名度を上げる目的で使ってはいけない媒体
- 企業がテレビ広告に何億円も投資する理由
- 店頭の現物は立派なコミュニケーション・ツール
- 店舗形態では店の看板も知名度獲得に有効
- 知名度は60%を目指す
- 高額商品や医薬品は知名度が売りにつながらない
- コラム ネット媒体は知名度獲得ツールとしては未熟:ネット媒体の強みが弱みに変わる
1-2 インパクトだけを求めて、理解してもらうことを放棄する ~U&E
- 理解してもらうこと自体を放棄してしまう
- 理解されても好意/購入意向に結びつかない
- 理解度が上がらないおもな原因
- 好意/購入意向が上がらないおもな原因
- 理解度と好意/購入意向を上げる4つの方法
- 「名前は知っているけれど、どんな商品かよくわからない」か、「どんな商品かわかっているけれど、魅力を感じない」か
- U&Eによる診断のフロー
- リテンション・レートでお宝が見つかる
- コラム 企業広告は難しい
- コラム 企業は広告表現の細部に口をはさんではいけない
- コラム タレントのプロモーション広告のよりどころはハイダーのバランス理論
第2章 生活者を見誤る
2-1 ヒット商品を最初に買った人たちを捨て置く ~イノベーター理論
- 人口の多さに目がくらみ、その他大勢の一般大衆をターゲットにしてしまう
- 全方面に媚びを売り、「嫌われるわけではないけれど、だれからも愛されない」中途半端なブランドが完成する
- イノベーター理論とは
- キャバクラから火が着いたバージニアスリム
- イノベーター像はいつも誤解される
- イノベーター理論は力の弱い企業にこそメリットがある
- イノベーター理論の4つのデメリット
- 「買って失敗した」すら楽しむイノベーター
- イノベーターが悪魔になると手がつけられない
- アーリーアダプターはスピーカーや増幅器のような役目を果たす
- 個人世界と社会性が性格を決める
- イノベーターを見つける2つの質問
- コラム フォロワーに浸透する過程で意味が変わってしまう場合がある
2-2 人を属性で表面的に判断してしまう ~価値観
- 「女性のピンク好き」は70年にも満たない歴史の浅い文化
- 「男性は料理をしない」と決めつけるのはとても危険
- 他人の常識を知るのはマーケティングより難しい
- 外見で判断するデモグラフィック分類ではターゲットとして機能しない
- コラム 企業がデモグラフィック分類によるターゲット設定を採用する3つの理由
- 40代男性と20代女性の類似点は? ~価値観ターゲット
- 価値観が決まれば好みが決まる、好みが決まれば行動も決まる
- 価値観の考え方をベースに、業界別の価値観グループを作る
- 価値観分類はイノベーター理論と組み合わせて使うのが最適
- コラム ペルソナと価値観分類の違い
- コラム ターゲット設定とは「買ってほしくない人を決めること」
- コラム Z世代の真実
2-3 ゲームのルールが変わったことに気づかない ~ダブルイノベーター理論
- トップシェアを握っていた企業の対応が遅れたあげく、転げ落ちる
- 新たなニーズを顕在化することでルールが変わる
- ゲームのルールを変える革新型イノベーター
- 革新型イノベーターが発生しやすい3つの条件
- 「スキンケア」と「競馬」の組み合わせで商品アイデアを考えるのが、革新型イノベーターを発見する手段
- コラム 革新型イノベーターはブルーオーシャン戦略の立役者
2-4 事実は事実であることに疑いを持たない ~認知ベースの行動理論
- 客観的な事実があったとしても「知らない」「知ろうとしない」「信じようとしない」
- 生活者の認知に対して無策だと、悪いイメ―ジはもとに戻らない
- 認知ベースの行動の基本:「回ってる扇風機の羽根を触ってみたかった」
- 同じハンバーグなのに、2種類のハンバーグが生まれる日常
- 「我々はいかにしてだまされるのか」
- ひと晩明けたら、悪者が正義の味方になる
- 知識から事実・真実へとこじらせると、認知バイアスがより強固になってしまう
- 不利な状況に追い込まれた時の3つの対抗手段
- 「生活者の頭の中を覗くこと」で商品開発を再考する
- コラム 認知ベースの行動と社会的責任
第3章 市場を見ずに突っ走る
3-1 「時代に早すぎた」は「単なる戦略ミス」 ~プロダクトライフサイクル理論:差別化
- 性能を上げず、差別化して失敗
- トップシェアだったのに撤退への道をたどってしまう
- 時代で見極めるプロダクトライフサイクル理論
- 成長期では「イノベーターの選択基準の延長線上」を翻訳したベネフィットが成功のキーとなる
- コラム プロダクトライフサイクルが「長い」のと「ない」のとでは大きな違いがある
- コラム プロダクトライフサイクルは、商品ではなく「商品ジャンル」
3-2 生活者の変化に気づかない ~プロダクトライフサイクル理論:ベネフィット訴求
- 成長期にも規格訴求を続けてしまう
- 成長期はベネフィット訴求に切り替えよ、ただし需要の大きいベネフィットに限る
- 普及性能・普及価格帯の商品を投入する
- 成長期の戦略3点セットを忠実に実行して成功したアップル
- コラム 成長期の始まりは普及率16%では遅すぎる
3-3 自分を弱者と認めたくない ~クープマンの目標値
- 20倍もの大きさの大企業にも勝てるほどの守備力が、ガリバーの大きな強み
- 1位がひっくり返らないカギは「市場シェア41・7%」
- 「ガリバーとどう戦うのか?」その1:弱いものいじめの法則
- 「ガリバーとどう戦うのか?」その2:チャンスの芽を見逃さずに反撃に出る
- クープマンの目標値をさまざまな用途に使う
- コラム クープマンの目標値を普及率の基準に使う
第4章 商品の健康診断をサボる
4-1 訴求すべきポイントを勘違いする ~プロダクトコーン理論
- 【パターン1】新製品導入時に規格訴求せずに失敗
- 【パターン2】規格からメリットに移行できずに失敗
- 【パターン3】イメージから規格に戻らずに失敗
- 商品は「規格」「ベネフィット」「エッセンス」の3つで定義される ~プロダクトコーン理論
- 商品をプロダクトコーン理論でチェック
- 市場の半歩先を予測できるプロダクトコーン理論
- プロダクトコーン理論とほかの理論が結びつく
- 歴史は繰り返す ~ぐるっと回るプロダクトコーン
- コラム プロダクトコーン3要素の詳解
4-2 商品にロゴをつければブランドだと信じて疑わない ~ブランディング
- 一流企業が集まったところでブランドをかんたんに作れるわけではない
- ブランドの5つの条件
- ブランドの条件からブランド力を探る
- ブランドは結果であって、原因ではない
- ブランドはフォロワーのための戦略
- YOASOBIはブランドに成長した:ソフト産業のブランド
- コラム 局所的ブランド
- コラム 耳かきを追いかけた、ある男の話
4-3 あれも欲しい、これも欲しいとタダをこねる ~コンセプトの純化
- 約束を意図せずに破ってしまう危険性
- 「憧れ」と「身近さ」は両立するのか?
- ブランドが発症しやすい3症状
- 処方箋に向けて:健康診断と事前準備
- 「乱発&ボケ」「形だけのお付き合い」「昔の名前で出ています」3つの症状別の処方箋
- ブランド維持戦略における「記号性継続型」と「意味性継続型」
- コラム パンツ理論(別名「英雄色好む」理論)
4-4 「らしくない」ことをする ~意識のブリッジ理論
- イメージと相容れない商品、価格、デザインでは成功しない
- 一流企業名を冠しても、他業界に攻め入って成功するわけではない
- イメージは点ではなく、面や領域
- ブランドイメージ戦略は道筋を明確にすること
- 裏街道を行く「裏道攻勢」
- 「同じ技術である」訴求が裏道をつなぐカギになる
- 生活者の4枚目の認知地図を利用する裏道戦略
- チカラ技でねじふせる
- コラム 地盤が弱いブランド、強いブランド。
- コラム 意識のブリッジに気がつかないケースもある
- コラム 価値観や生活様式によってグループの数は増減する
4-5 有望株の芽を摘む ~Lて山スラッシュ理論
- 伸びる市場への参入をためらい、市場拡大の波に乗れない
- Lて山スラッシュ理論と4つの進行度
- 商品コンセプト案の評価と対策に使う
- 既存ブランドの健康度チェックに使う
- Lて山スラッシュ理論の留意点
第5章 競合商品にも顧客がいることを忘れる
5-1 自社商品ですら区別がつかない ~差別優位性
- 質問:ブランド名を当てることができますか?
- 「広告で差別化すれば、商品も差別化される」と勘違いする
- 差別優位性はマーケティングの基本だけに誤解も多い
- 優位性の限界①:メリットとデメリットの交点
- 優位性の限界②:人間の知覚の限界
- 差別性の「限界」は「拒否感」のこと
- 例外として限界が存在しない優位性もある
- 差別性、優位性はどれだけの差が必要か
- コラム 一見インパクトのみだがじつはきちんとメッセージを盛り込んだ広告もある
5-2 「市場が大きいから売上も大きい」の勘違いを犯す ~DCCM理論
- 差別優位性が強くても、説得性がない商品では売れない
- 差別優位性や説得性があっても、市場性が小さければ、本当のヒット商品にはならない
- 差別優位性に説得性と市場性を加えたDCCM理論
- さまざまな説得性の強化方法
- 市場性は拡大しすぎても狭めすぎても失敗する
- DCCM理論でマクドナルドを評価する
- DCCM理論をベースとしたマーケティング戦略
- コラム 差別優位性マトリクス
5-3 守るべきなのに攻める、攻めるべきなのに守る ~守りと攻めの戦略
- 守りの失敗:競合企業として相手にせず、成長の時間を与えてしまう
- 攻めの失敗:競合が強い市場に、差別優位性もなく殴り込みをかける
- 攻撃戦略は、正面からか、戦闘回避か
- 生活者に焦点を当てた浸透戦略
- 攻撃戦略と浸透戦略を組み合わせて、守りと攻めの戦略を理解する
おわりに
プロフィール
森行生
1955年生まれ。米国デューク大学にてコンピュータ工学および経済学をダブル専攻し、1978年卒業。大手嗜好品メーカー、外資系パッケージグッズメーカー、大手マーケティングコンサルティング会社などを経て、1992年、ブランドおよび事業戦略に関するマーケティングコンサルテーションをおこなうシストラットコーポレーションを設立。「プロダクトコーン理論」などを提唱。
著書に『ヒット商品を最初に買う人たち』『改訂・シンプルマーケティング』(SBクリエイティブ)、『21世紀のモノ創り 70のヒント』(毎日コミュニケーションズ)がある。
ホームページ:http://www.systrat.co.jp/
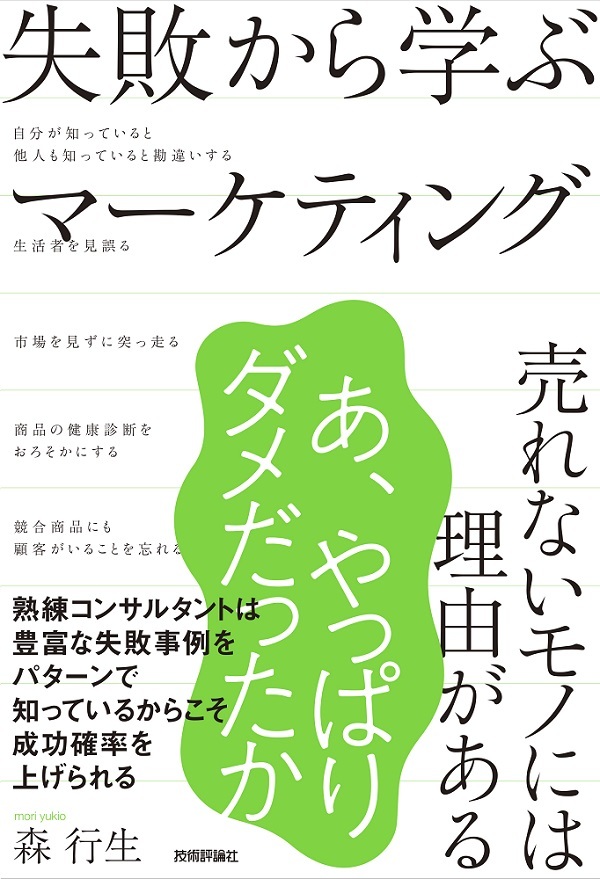
著者の一言
日本のスマートフォン出荷台数の7割を占めるiPhone。
日本の全世帯の3分の1が買ったNintendo Switch。
累計10億枚売れたヒートテック。
日本歴代映画興行収入1位『千と千尋の神隠し』を軽々と超え、2021年8月に403億円に到達した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。
すべての企業の開発担当者が夢見る大ヒット商品たちです。
しかし、残念なことに、大半は露と消えていきます。
「どこがマズかったんだろう」
「コンセプトはああしておけばよかった」
「製造部門や営業部隊が反対したからダメだったんだ」
「上司が頑固だったから、あそこを改良できなかった」
「競合相手が強すぎる」
「うちは高コスト体質だから価格を下げられない」
反省することしきり。「よし、次はがんばろう」と思っても、なかなかヒットは生まれません。
じつは、手がけた新商品や新サービスが成功する方法があります。それは「失敗から学ぶ」ことです。
マーケティング・コンサルタントを30年以上続けている私だけでなく、みなさんにもこんな経験はありませんか。
「なぜ、こんなアプローチをした商品を世に送るのだろうか? 失敗は目に見えているに……あ、やっぱりダメだったか」
「正解がわからずに試行錯誤しているようだな……あ、やっぱり話題にすらならなかった」
成功するかどうかはわからずとも、失敗しそうなのは感覚でわかります。それをできるだけ論理的に解説しようとしたのが本書です。
日本では「マーケティングの失敗例に学ぶ」まとまった書物はほとんどありません。私のアメリカの学生時代には、コトラーのマーケティング教科書とともに、失敗例だけを集めた副読本がマーケティング専攻の全学生に配布されたものでした。私が本書を記そうとした動機が、学生時代の原体験でした。
本音を言えば、編集者の傳さんからご連絡があり、本書のコンセプトを聞いたのがきっかけでした。私はすぐ「これはいける」とピンときました。もともと自分のメルマガで失敗例からマーケティングを学ぶスタンスの記事が大半を占めていたことも、すんなり納得できた理由でもあります。私があまりにも自然に話を進めてしまったため、傳さんが「本当にこの話を受けてくれるのか」と心配になったほどでした。
「失敗から学ぶ」が本書のコンセプトではありますが、それをどう書籍化するのか。「パッケージが赤だったから売れなかった」のような表層的な結論では元も子もありません。そこで、本書でみなさんに伝えたいのは2つです。
失敗にはパターンがあり、その多くはマーケティング理論から外れたことをしてしまったケースなのです。したがって、パターンを解析することで失敗を回避し、成功確率を上げることができます。そして、失敗パターンをマーケティング理論とつなげれば、対処方法もわかります。
誤解を恐れずに言えば、我々マーケティング・コンサルタントは成功事例と失敗事例、そしてそれにともなうパターンの両方を駆使して、成功確率を高めます。例えていえば、お祭りの射的で、普通の人は銃身の短いピストルを使いますが、我々は銃身の長いライフルを使い、かつ身を乗り出して的との距離を極力縮めることで、的の中心に弾丸を当てる確率を極力高めます。「ずるい」と言ってはいけません。ライフルを使うことがマーケティング理論および成功と失敗のパターンを駆使することなのですから。みなさんもぜひ、ライフル、いやアサルト・ライフルを使って的を当て、豪華な賞品を獲得してください。