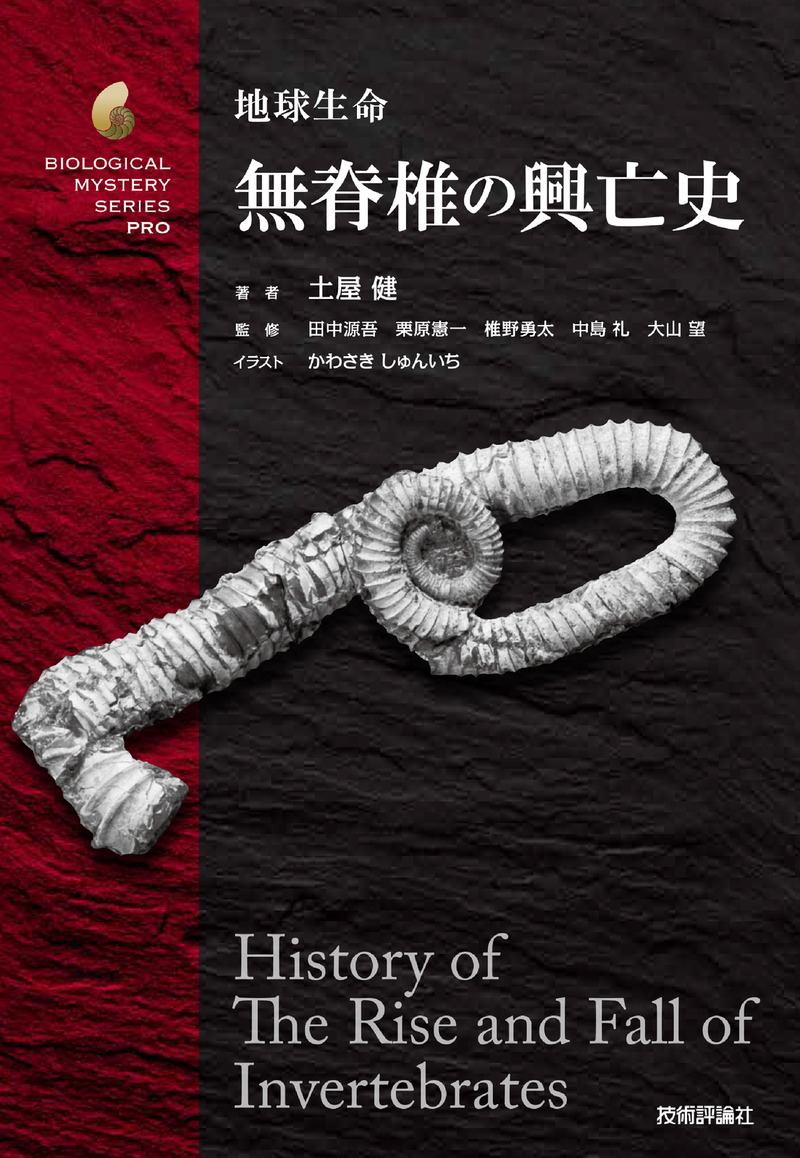生物ミステリー(生物ミステリーPRO)
地球生命 無脊椎の興亡史
-
土屋健 著
田中源吾,栗原憲一,椎野勇太,中島礼,大山望 監修
かわさきしゅんいち イラスト - 定価
- 3,960円(本体3,600円+税10%)
- 発売日
- 2023.7.24
- 判型
- A5
- 頁数
- 288ページ
- ISBN
- 978-4-297-13612-3
サポート情報
概要
魅惑的な古生物たちの世界。知的好奇心をくすぐり、知的探究心を呼び起こし、そして何よりシンプルに面白い。そんな世界を、みなさまにお届けします。
新シリーズ第二弾は、「無脊椎生物における興亡」をお届けします。
地球生命史を紐解くと、そのスタートは「無脊椎動物」です。サカナという脊椎動物が台頭するまでは、無脊椎動物は地球生命の主役でありました。サカナの台頭後には主役の座を譲ったものの、無脊椎動物は“名脇役”として存在感を放ち続けます。
本書は、そんな無脊椎動物たちの興亡にスポットを当てます。
- 謎多きエディアカラ生物群
- アノマロカリスに代表されるラディオドンタ類
- ラディオドンタ類から覇者を引き継いだウミサソリ類
- 隆盛を誇った三葉虫類、そしてアンモナイト類
- 現在まで脈々と命をつなぎ続ける腕足類、二枚貝類
- 古生代から着実な歩みを続ける昆虫類
などなど、無脊椎動物たちの歴史を、分類群ごとに綴りました。本書を最初から読んでいただければ、無脊椎動物たちの興亡を順番にご堪能いただけるでしょう。もちろん、お好みの動物群からお楽しみいただくという手もアリアリです。
無脊椎動物が繰り広げる生物史とは、どんな世界だったでしょう。地球生命史を語る上で欠かすことができない“無脊椎の興亡史”の物語を、存分にお楽しみください。
こんな方にオススメ
- 古生物ファン
- 美しい&貴重な化石を愛でたい方
- 無脊椎生物の興亡に興味のある方
※「生物ミステリーPRO」愛読者にドンピシャの1冊です。
目次
第1章 楽園の住人
- 楽園の住人
- 始まりの39億年間
- エディアカラの園
- アヴァロンの爆発
- エディアカラの不思議な仲間たち
- 萌芽……?
第2章 覇者、現る
第1節 最初の覇者とその仲間たち
- 生存競争、開幕
- 狩人の登場
- 狩人の仲間たち
- 成功者。そして、生き残り
- 覇者への道筋
- 覇者からの道筋
第2節 節足動物、覇権を握る
- ウミサソリ類の登場
- その尾剣は、「尾剣」として使えるのか
- 鋭い尾剣をもつ仲間たち
- どこで、いかに狩るか
- 泳ぐ、ばかりではない
第3章 新たな狩人
第1節 はじまりの“生きている化石”
- 海の賢者たち
- カンブリア紀のイカ型動物
- 殻のある小さな“最古”
- “殻あり”が先か、“殻なし”が先か。それが問題だ
- 先行するノーチロイド型頭足類
- 殻をつめる(!?)ノーチロイド型頭足類
- 丸くなり、そして、壊滅する
- そして、また、生き残る。しかし……
- 「生きている化石」へ
- 幕間:デボン紀ネクトン革命
第2節 海の名脇役
- アンモノイド類も丸くなる
- 命脈はつながった
- 生き残りが手にした栄華
- そして、多様化の時代へ
- なぜ、アンモナイト類は滅んだのか?
第3節 謎に包まれたグループ
- 鞘形類、現る
- 進撃するベレムナイト類
- イカ、タコ、コウモリダコ
第4章 進化の目撃者
- 進化の目撃者
- 王様、登場
- まず、栄えた
- 三葉虫の“一生”は、種それぞれ
- 共喰いのはじまり?
- 平和な海域で大きくなる?
- 立体的になった三葉虫たち
- 泳ぐ!
- 集団行動する三葉虫
- 襲われた三葉虫
- 凋落のはじまり
- 徒花を咲かせる三葉虫類
- オウムガイ類の殻を利用する
- 超複眼
- そして、シンプルが残った
第5章 海底の住人たち
第1節 無気力な方々
- 2枚の殻をもつ
- 「自分で動かずとも」への道
- 変わりもの?
- 世界とともに変化した
第2節 海の底の台頭者
- 身は詰まっている
- 始まりの、微小二枚貝
- 巨大で謎の二枚貝
- 中生代の海洋変革
- 氷山戦略者
- 礁をつくる二枚貝
- 泳ぐ二枚貝
- 地層の時代を決める大型二枚貝類
- 潜って生きる
- そして、長く生きる
第6章 空を飛び、成功者となる
- 空を飛び、成功者となる
- 圧倒的な多様性
- 最古の昆虫か、それともムカデか
- ギャップを埋める化石
- 「空」という新世界
- 大型化したものたち
- 翅の使い道
- 嫌われモノ(?)の出現と、その仲間の進化
- 新たな昆虫たちの出現
- 葉に潜る
- 恐竜形類の糞の中に
- 天敵の出現
- 擬態をする
- ほかにもさまざまな仲間たち
- 喰い痕が語る復活
プロフィール
土屋健
サイエンスライター。オフィス ジオパレオント代表。
日本地質学会員、日本古生物学会員、日本文藝家協会員。埼玉県出身。
金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。
在学中は、本書にも登場するイノセラムス(二枚貝類) に関する研究を行った。
その後、科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て、現職。
2019年にサイエンスライターとして初めて日本古生物学会貢献賞を受賞。
愛犬たちと散歩、愛犬たちとの昼寝が日課。
古生物に関わる著作多数。
近著に『生命の大進化40億年史 中生代編』(講談社)、『も~っと! 恐竜・古生物ビフォー・アフター』(イースト・プレス)、『古生物出現! 空想トラベルガイド』(早川書房)など。
田中源吾
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター沿岸環境部門准教授。
島根大学卒業後、静岡大学大学院にて博士(理学)を取得。
専門は層位・古生物学。とくに古生代の節足動物に注目し、眼や神経系、軟体部に関する研究を行っている。
栗原憲一
株式会社ジオ・ラボ代表取締役・CEO。北海学園大学人文学部客員研究員。
早稲田大学で博士(理学)を取得。
三笠市立博物館および北海道博物館にて学芸員として勤務後、株式会社ジオ・ラボを設立。科学的な知識を生かした地域活動の支援を日本各地で行っている。
椎野勇太
新潟大学教育研究院自然科学系地球・生物科学系列准教授。
静岡大学卒業後、東京大学で博士(理学)を取得。
腕足動物や三葉虫を対象に、生物の形態や機能がどのように進化したかについて研究を行っている。
中島礼
国立研究開発法人産業技術総合研究所地質情報研究部門。
北海道の貝類化石群集の進化を研究し博士(理学)を取得。
古生物を使った環境復元および地質図の作成に取り組む。
化石や地質の研究に関する普及活動も行っている。
大山望
パリ国立自然史博物館・古生物研究センター海外特別研究員。
九州大学総合研究博物館専門研究員。
九州大学でナギナタハバチ類の初期進化を研究し博士(理学)を取得。
専門は、昆虫の進化。
中・古生代の昆虫化石相および昆虫が化石になる過程についての研究を行っている。
かわさきしゅんいち
画家・イラストレーター。1990年大阪生まれ。
2017年に絵本『うみがめぐり』でデビュー。
その後『アノマロカリス解体新書』や本シリーズで挿絵や装画を手掛ける。
個展等 情報発信はTwitter @nupotsu104より。